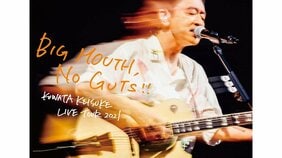「PATROL with REIKOの巻」(ジャンプ・コミックス第145巻収録)
今回は、住民調査のため地域を巡回中していた両さんと麗子が、まるで夫婦漫才コンビのような空き巣と出会うお話をお届けする。
本作が描かれたのは2004年。1990年代のバブル経済崩壊によって景気低迷や失業率の上昇が起こり、住宅侵入窃盗や車上荒らしの発生件数が増加していた時期だ。
『こち亀』最初期にも、本作に似たエピソードが存在する。コミックス第1巻に収録されている1976年に描かれた「気のあうふたり!?の巻」だ。物色中の泥棒が両さんの訪問を受けて家の主になりすましてやりすごそうとすると、そこにさらに別の泥棒が忍び込んでいた……というお話だ。
警官が主人公の漫画ゆえ泥棒も登場しているが、初期の『こち亀』には窃盗をめぐるお話が非常に多い。『こち亀』が連載スタートする前の1973年には、1年間の窃盗発生件数がピークとなり、年間約200万件におよんでいたとのこと。これは、第二次世界大戦敗戦後の混乱期、高度成長期における急激な社会の変化や貧困が原因だ。
『こち亀』がはじまったのは、「戦後」の日本社会の雰囲気がまだ残っていた時代だったのだ。
ちなみに、なぜ毎月18日が「防犯の日」なのかというと、18の「1」を「棒(ぼう)」=「防」と読み、「8」=「犯」と読む語呂合わせだ。警備会社・セコムによって制定されたという。
それでは次のページから、両さんと麗子が出くわす空き巣事件の顛末をお楽しみください!!