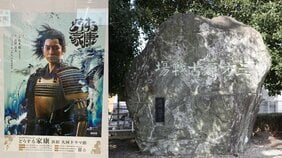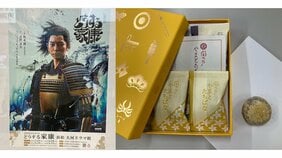「日本国王」の称号を受けた足利義満
源頼朝は、平家を滅ぼし、本格的な武家政権である幕府を鎌倉に樹立します。しかし、源氏は3代しか続かず、本来はその家臣に過ぎなかった北条氏が、ちょうど天皇家を藤原氏がコントロールしたように実権を握り、「北条執権体制」が始まります。
武士が天皇家を滅ぼすチャンスが巡ってきたのが、北条義時のときでした。しかし、この時代には天皇は神の子孫で特別な家系であるという信仰が完全に確立していたため、他の国なら君主になれていたはずの義時ですが、天皇家を滅ぼすことはついにできませんでした。
その鎌倉幕府が滅んだのは、後醍醐天皇が一時的ではあったものの、反幕府の武士たちをまとめるのに成功したからです。
とはいえ、このとき足利尊氏を筆頭とした武士たちが望んでいたのは幕府という武士による支配体制をなくすことではなく、あくまでも幕府のリニューアルでした。そのため尊氏は、最終的には後醍醐天皇を追放して、新たな武家政権「室町幕府」を開きました。
ではそれ以降、武士の中に天皇を超えようとした人間は一人も現れなかったのでしょうか?
実はいました。それが織田信長と、その後継者とも言える徳川家康です。
そして、その前にもう一人。ただ、彼の場合は、正確には天皇を超えようとしたのではなく、「天皇と対等になろうとした」と、見るべきだと思っていますが、その人物とは、室町3代将軍・足利義満です。
足利義満というのは、京都の金閣寺を建てたことで知られる将軍ですが、実は日本で武士の身ながら初めて天皇の権威に挑戦した人間として特筆すべき人物なのです。
そして彼の独創的な点は、天皇の権威に対抗するために「国際的な権威」を利用しようとしたことです。
彼が利用したのは、大陸の大国「中国」の権威でした。
紀元前、中国にも戦国時代というのがあり、7つの国家が覇権を争っていました。この時代の中国における最高の身分を表す言葉は「国王」でした。つまり、7人の国王が群雄割拠し、覇権を競っていたのです。
その中で天下を統一したのが「秦」という国でした。秦の国王である嬴政は、王をすべるものとして新たな称号を創設します。それが「皇帝」でした。つまり、始皇帝です。
これ以後、近代に至るまで、中国全土を支配する人間の称号として、この皇帝が使われることになります。そして皇帝が生まれて以降、国王というのは、大中国に臣従する周辺国家の首長を意味する称号になりました。
日本は昔から中国と深い関係を持っていましたが、白村江の戦い以前の日本は弱小国家で、卑弥呼の時代からずっと、中国へ朝貢(貢ぎ物をし、その代わりとして庇護を受ける)し、「国王」に任じてもらっていました。
しかしその後、国家意識を高めた日本は、国王という称号を使うのをやめ、独自に「天皇」と名乗るようになります。これは明らかに、もはや日本は中国の臣下ではない、という対等意識の表れです。このような考えのもと実行に移したのは、東アジアでは日本だけです。
ところが、その「天皇」を超えようと思った足利義満は、中国(当時は明国)に使いを送り、「日本国王」の称号を受けたのです。