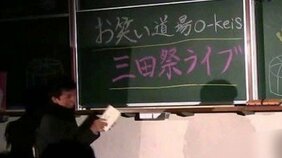大企業に就職するお笑いサークルの若者たち
日常のコミュニケーション様式にお笑い的なスタイルが広がってきて久しい。90年代にダウンタウンが芸能界の覇権を握ったことでボケとツッコミというタームが一般層にも浸透した、雛段芸人と呼ばれる属性の登場が集団でのコミュニケーションのあり方を変えた、など様々な論があるが、実はビジネスパーソンが語る「成長」と「お笑い」の文脈が近い場所で結びつき始めている。
お笑いサークルってなんだか大企業に就職する傾向があって。
(「芸人で会社員で社長!三足のわらじを履く理由」NHK 大学生とつくる就活応援ニュースゼミ、2022年7月15日におけるラランドのサーヤの発言。すでにサーヤは勤めていた会社を退職)
企業の面接とかで「お笑いサークルで漫才やっていました」とか言うと、「コミュニケーション能力が高いね」みたいな評価を得られるらしい。(中略)いわゆる芸人というものが、頭の回転が速く、コミュニケーションが上手で、人付き合いも上手くて、盛り上げて、わりと根性もあって、就活に一番効くパーソナリティを形成するみたいになっている。
(「第1回 お笑い地政学~氷と炎の歌~」THE SIGN PODCAST、2022年11月24日より、おぐらりゅうじの発言)
お笑いがコミュニケーション能力の基準になる
大学生がサークル活動としてお笑いに取り組むこと、そしてそれが就活における武器になっていること。この話のキーになるのは、本書でも何度か取り上げている「コミュニケーション能力」である。
場を和ませて、かつ鋭い指摘を繰り出せる存在としてのお笑い芸人の姿は、今の職場において求められる人材像ときれいに重なる。
適切なコミュニケーションの前段にはロジカルな視点からの現状把握やそれを踏まえた解決策についての検討が必要であり、そういったことを瞬時にこなせる点で、その能力は今の時代のポータブルスキルとも合致している。
コラムニストの小田嶋隆は生前Twitter(現X)において、「松本人志がヤンキーのヒーローたり得たのは、勉強漬けのインテリの知的武装をワンフレーズのボケで無効化してしまうその地頭の良さにあった」という言葉を残している。
お笑い界のドンの魅力を示す言葉(実際にはこのツイートは松本に対して批判的なものだが)と、第三章で触れたコンサルファームで採用される人材の要件を表す言葉が一致しているのは非常に興味深い。東大生が入りたい業界の採用基準にトップクラスのお笑い芸人が肉薄しているという不思議な状況が生まれている。