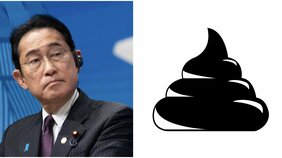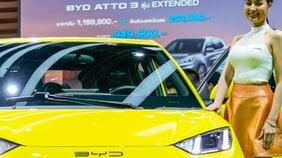液化バイオメタンという新手法
他にバイオガスの活用法はないか。そう考えた同社は、産業ガスメーカーのエア・ウォーター株式会社(大阪市)に声をかけた。
同社のエネルギーソリューショングループGI(グリーンイノベーション)事業部バイオメタンチームの大坪雛子さんは、「糞尿を適正に処理したい酪農家が増えている一方で、バイオガスの使い道がないという問題があります。産業ガスメーカーとしても放置できないと考え、解決に取り組みました」と言う。
エア・ウォーターはサンエイ牧場ともう一カ所の牧場と連携。環境省の実証事業として、「最終的に一般の人にも使ってもらえるようなエネルギーを作る」という試みを2021年から開始した。
バイオガスからメタンを抽出・精製する。プラントでそれを液体窒素で冷やして液状の「液化バイオメタン」にし、容積を600分の1にすれば、輸送に便利で扱いやすくなる。
液化バイオメタンを液化天然ガスの代わりに工場のボイラーやトラック、船舶の燃料にしたり、気体のバイオメタンを家庭で使う都市ガスに混ぜたりしてきた。
乳業発「カーボン乳(ニュー)トラル」?
2024年5月からは商用利用に移った。エア・ウォーターは〈カーボンNEWトラル!〉というキャッチフレーズで、バイオメタンが持続可能な新しい国産エネルギーであることを発信してきた。展示会への出展や広告展開で、認知度を上げようとしている。
カーボンニュートラルは、「炭素中立」と訳せる。温室効果ガスの排出と吸収の釣り合いを取り、全体でみたときの排出をゼロにすること。政府は2050年までにこれを実現すると宣言している。
繰り返しになるが、動植物に由来する有機性の資源である「バイオマス」を微生物の力を借りて発酵させたのが、バイオガス。
このバイオガスは、もともと大気中の二酸化炭素を動植物が成長の過程で吸収しているので、燃やしても排出量は差し引きゼロとみなされる。
よつ葉乳業株式会社(北海道河東郡)と雪印メグミルク株式会社(東京都新宿区)が、道東の工場でバイオメタンをボイラーの燃料に使っている。エア・ウォーターは、このモデルを他地域にも広めたいという。
まずは酪農を取り巻く乳業の世界で、循環の輪が生まれている。取材していて、「カーボン乳トラル」という言葉が頭に浮かんだ。
「酪農家がバイオガスプラントを建てようとすると、初期投資額は大きい。でも、バイオガスを売ることでその投資を回収できる。メタンで動くトラクターなどの農機も開発されていますし、いずれ自分で作った燃料で農機を動かすのが当たり前の時代が来るかもしれません」鈴木さんはこう語る。
その周囲には、バイオガスプラントを建てたいけれども、売電できないために二の足を踏んでいる酪農家が多い。彼らはガスそのものを売ることに興味津々だという。
バイオガスプラントは、建設に億単位の費用がかかる。そのため国内ではサンエイ牧場のような大規模な牧場に導入が限られている。
だが、海外では規模の小さい牧場でも導入例がある。鈴木さんが視察に訪れたドイツの牧場は、300頭を飼う程度の規模ながら、バイオガスプラントを導入していたという。
ガスの販売が広まっていけば、日本でもそれが当たり前になるかもしれない。