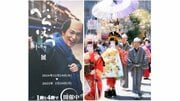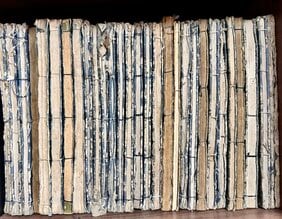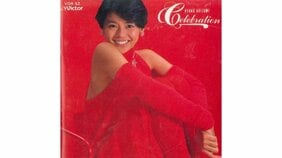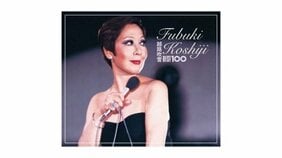遊郭を生み出した社会課題はなくなっていない
――「当時と今は違う」という意見に対して、遊郭はなくなったとはいえ、その跡地では今も多くのソープランドが軒を連ねて営業している現実があります。
吉原遊郭はなくなったけれど、遊郭を生み出した社会課題はなくなっていない、ということですよね。ソープランドその他の現代性風俗業で働いている女性と、かつての遊女を混同できないことは言うまでもありませんが、地続きの問題を今も抱えている点は見逃してはいけないと思います。
だからこそ、フィクションであったとしても、「当時は当たり前」で済ませたくないのです。
男は女を支配できるという考えが生き延びているからこそ、戦後に遊郭制度は廃止されても、赤線として延命された。ここ数年に限っても、オリンピックやコロナといった時代の荒波に社会が洗われるとき、男性による女性へ向けた性加害や尊厳の軽視が繰り返し顕在化している。
先ほども述べたとおり、ドラマには制作側の意図が投影されている。その意味で、過去を扱ってはいても、現代の視点、そして現代の問題なんです。
――ほかにも、メディアが遊郭を扱う際に、気をつけなければならないことはありますか?
遊郭をはじめ、性売買に従事する女性たちの境遇を考える時に、経済状況について、つまり、「どれだけ稼いでいるか?」という視点は多くの人の関心を呼ぶのか、よく取り上げられます。ネットニュースでもよく見かけますよね。
例えば「低級な遊女もいたが、同時に高級な遊女もいた。だから悲惨な側面ばかりではない」とする考えです。私は少し危険に感じます。対価さえ与えれば構わないという論理と隣接している。昨今の示談金騒動とまったく相似形だと思いませんか?
さらには「稼ぎの低い人は、人間としても価値が低い」といった価値観と連動している。
――ちなみに、これまでに遊郭が舞台となったフィクションで、そのあたりがきちんと描かれていると感じられる作品は?
きちんと描けているか、という質問の答えにはなりませんが、多くの人の記憶に強く残っているのは、五社英雄監督の『吉原炎上』(1987年公開)ではないでしょうか。名取裕子さん演じる主人公は、少女が豪華で煌びやな存在に成り上がっていく、分かりやすいステレオタイプな遊女像です。彼女を軸にストーリーが展開されます。
一方、かたせ梨乃さんが演じるのは不器用な遊女で、最下層の遊女に身を落としてしまう。名取さんよりかたせさんの役柄が好き、という人は少なくないのではないでしょうか?
同作の舞台は明治末期ですが、合理性を良しとする近代明治にあっては「不器用」と切り捨てられてしまう生き方の中にも、私たちが忘れてしまった大切なものがあるのではないか、という五社監督の問いかけが、かたせさんの役に投映されているのではないでしょうか。
だから、少なくない人がかたせさんの役に惹かれてしまう。名取さんの役だけ、かたせさんの役だけでは成立しない。明暗が対の関係にあるからこそ活きる。そして「名作」として語り継がれている。
――『べらぼう』のかたせ梨乃さんは「場末の女郎屋の女将」という役を演じていますね。
かたせ梨乃さんの『べらぼう』での役名は「きく」ですが、『吉原炎上』では「菊ちゃん」と呼ばれる役です。江戸時代の中期が舞台の『べらぼう』と、明治時代の末が舞台の『吉原炎上』では時代設定がだいぶ異なりますが、その精神性は受け継いでいる、という制作者の意図を感じますね。ある種のファンサービス、五社監督へのリスペクトですかね。
――そもそも渡辺さんが遊郭の文献や資料を収集するようになったきっかけは?
小さい頃から、声の小さい人、言葉を持たない人への興味がぼんやりありました。その最たる存在は遊女じゃないだろうか、と思い、遊廓や遊女に感心を持つようになりました。私たちは小学生の頃から、政財界の偉人のあれこれを習いますよね。大人になって博物館へ行くようになっても同じです。
もちろん各界のリーダーのお陰で私たちの生活、例えば蛇口をひねれば美味しい水が出るし、スイッチをひねればお湯が沸く、こうしたことを当たり前に享受できるありがたい世の中になっている。リーダーには感謝しても感謝しきれない。
でも、リーダーや成功者の陰で、容易ではない現場の労働に従事して、名も残さず消えていった数え切れない人々がいたことも忘れたくありません。なぜなら、私もまた「名もない人間」の一人で、そうした人を軽視する社会になったら、私にとって苦しい社会になるからです。