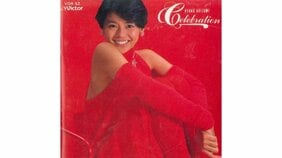「校則の見直しを進めるという学校が少しずつ広がってきている」
――2022年に「こども基本法」が成立し、また「生徒指導提要」が12年ぶりに改訂されました。校則をめぐる動きに変化はありますか?
私たちのプロジェクトが動き始めたのは、ある公立高校の生徒が黒髪矯正をさせられたといったことに対し裁判を起こしたことがきっかけになっています。
私たちが実態調査を行なって発表したところ、大きな反響があり、そこから校則の問題が全国的に広がっていきました。
弁護士会や議員さん、自治体の首長さんなどが動き始めて、国会でも取り上げられるようになりました。コロナ禍以降もその動きは続いています。
今では、別のNPO団体が「みんなのルールメイキングプロジェクト」というものを立ち上げました。自分たちで新たなルールを変えたりできるように、学校の中に持続可能な取り組みを作ろうというプロジェクトです。
学校側と生徒側が連携して積極的に話し合いの場を持ち、校則の見直しを進めるという学校が少しずつ広がってきています。
ある調査では、9割の教員が「今の校則が変わっていいと思う」と答えていますが、なぜ変わらないのかというと、「校則を変えるルール」がほとんどないからなんです。
校則を作ったはいいが、変えたり、なくしたりするルールが明記されていない。だからずっと惰性で続いてしまっているという側面があります。誰も幸せにならないシステムになっているんです。
子どもが大人と対話の場を設けて、子どもと大人双方の言い分を整理しながら、変えるものは変えることが必要です。流動的に議論が続けられ、アップデートが常に行なわれるような教育環境であることがベストではないでしょうか。
※
この数年で校則を見直す動きが広がってきている、と話した須永さん。一方で、「小手先の見直しをしただけの学校もあり、まだまだ道半ばです」とも話していた。
※「集英社オンライン」では「ブラック校則」をはじめ、学校トラブルに関連した情報、体験談を募集しています。下記のメールアドレスかX(旧Twitter)まで情報をお寄せください。
メールアドレス:
shueisha.online.news@gmail.com
旧X(Twitter)
@shuon_news
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班