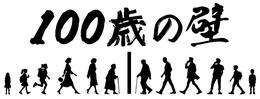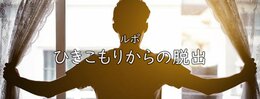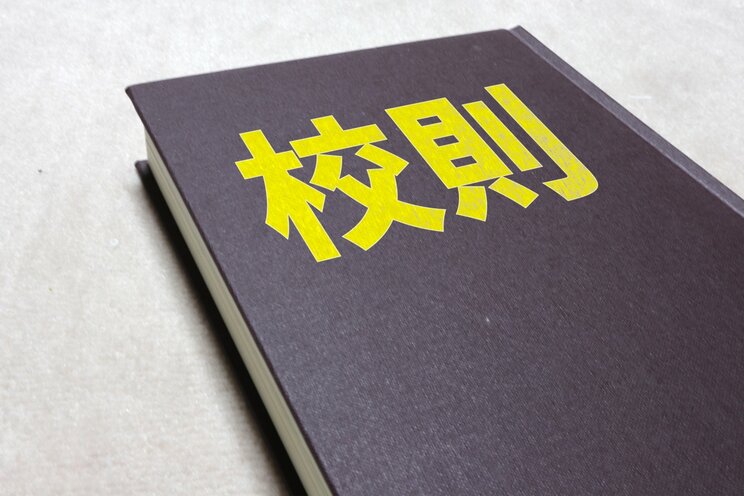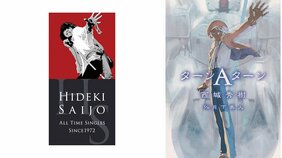若手の教員たちが声をあげて議論につながったケースも
――そもそも校則は誰が決めるものなのでしょうか?
校則については法律では触れられていませんが、「生徒指導提要」という学校に配られる生徒指導の基本書があります。
それも順守しなければいけないというよりは、生徒指導のための「指針」という位置付けです。
裁判でも明確になっていますが、校則に関しては校長が最終的に権限を握っています。教育委員会などが指示を出して決められるものではなく、それぞれの学校が決めることになっています。
――不登校が大きな社会問題となっていますが、校則とは関係しているのでしょうか?
文部科学省が研究者に依頼して実施した調査(「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」 )では、小学校6年生と中学校2年生に「学校に行きたくない理由」を聞いています。
それによると、「学校のきまりなどの問題(学校の校則がきびしかった、制服を着たくなかったなど)」を理由として挙げている中学生の子が7.8%にのぼることが判明しています。
小学6年生だと同じ理由を挙げている子は2.7%なので、中学生のほうがより多く、不登校の原因として「学校のきまり」が関係していることが分かっています。
――校則を変えたいと考えた場合に、具体的にどのような段取りになるのでしょうか?
たとえば、理不尽な校則に関するニュースをきっかけに、生徒会を中心にアンケートを実施して顧問の先生に持っていき、それを職員会議にかけて細かい校則を緩和したという事例もあります。
ほかには若手の教員が「自分たちも厳しい指導をするのがきつい、もう少し緩く指導させてほしい」と声をあげ、それを上の教員が汲んで議論につなげた、という事例もあります。
あとはNPOなどの外部団体が教員側にアプローチしたり、教育委員会が管轄の学校に「人権侵害をするような校則がないか点検するように」と通知した事例もあります。また、自治体の首長が積極的に教育委員会に提案をして動くケースもあります。