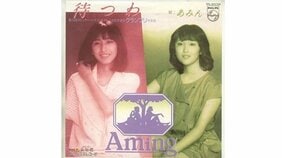フランスでカルト指定された日本の宗教団体
このように、チャーチとセクトという概念で宗教教団を区別する見方にはいろいろと問題があり、そもそもキリスト教にしかあてはまらない部分がある。イスラム教だと、神秘主義の集団を除いて教団組織を形成しないので、いくらその地域で支配的であると言ってもチャーチとは言えない。
ただ、フランスでは、カトリック教会が中心なので、セクトということばが、他の国のカルトと同じ意味を持つことになった。それでも、反セクト法では、セクトを特定したわけではない。リストアップされたのは、あくまでセクト的な行動をとる団体なのである。
では、セクト的な行動とは何なのだろうか。
1995年に国民議会調査委員会が左派社会党のジャック・ギュイヤールを報告者として議会に提出した「ギュイヤール報告書」では、10の基準が示されている。
それをあげれば、精神の不安定化、法外な金銭要求、元の生活からの引き離し、身体に対する加害、子どもの加入強要、反社会的な言説、公序に対する脅威、訴訟を多く抱えている、通常の経済流通経路からの逸脱、公権力への浸透の企て、である。
そして、セクト的な行為をとる173の団体のなかには、幸福の科学、フランス神慈秀明会、霊友会、崇教眞光、創価学会インタナショナルといった日本発の新宗教も含まれていた。そして統一教会もである。
この報告書であげられていた基準は、その集団がどのような行動を行ったかである。集団がどのような組織構造を持っているのか、あるいはどういった教義を掲げているのかはまったく問われていない。
カルト(セクト)と言えば、一般的にはカリスマ的な教祖を中心とした小規模の過激な集団というイメージがあるが、そのイメージに重なり合うようなことは、基準にまったく含まれていないのだ。
つまり、ギュイヤール報告書は、カルト(セクト)についての定義をまったく行っていないと言える。
こうした報告がなされ、セクト的行動を規制する法律が作られたことについては、フランス社会の特殊性が深く関係している。
フランスでは、フランス革命が起こった際に、カトリック教会から権力を奪うために、聖職者を処刑したり、教会の財産を国家に移転させるなどの処置が施された。その後、フランスでは、厳格な政教分離を求める「ライシテ」の原則が確立され、それは憲法にも織り込まれた。
そのため、公共空間において信仰を誇示する行為には制約が課せられるようになる。イスラム教徒の女性が公共空間で「ヒジャブ」と呼ばれるスカーフを被ることが法律で禁じられるまでになったのだ。
こうしたフランスの特殊な環境がなければ、反セクト法が生まれることはなかったであろう。伊達聖伸は、「反セクト法は、フランス社会および政府による反セクト闘争の絶頂期に制定されたが、その勢いはほどなくして沈静化に向かう」と指摘している(島薗進編『政治と宗教―統一教会問題と危機に直面する公共空間』〈岩波新書〉の第4章「フランスのライシテとセクト規制」)。絶頂期とは、まさにカルトの事件が頻発した1990年代をさす。