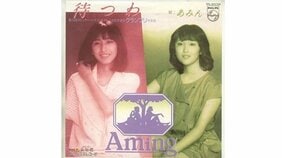生活に支障をきたす過敏性腸症候群
腸を調べても大腸がんや大腸ポリープも見つからない、潰瘍性大腸炎のように大腸に潰瘍ができていることもないのに、下痢や腹痛、便秘を繰り返す症状のことを過敏性腸症候群といいます。
日本では、20代以上の男女の実に20%がこの症状に悩まされているというデータがあります。
症状は下痢型、便秘型、混合型の主に3つに分類されます。
下痢は週3回以上、腹痛とともに、水のような排便が続きます。
便秘型は週3日以上排便がない状態が続き、排便の際には苦痛が伴います。排便したとしてもコロコロした便になります。
混合型は、下痢と便秘が交互に起きます。便秘がしばらく続き、硬い便が出たと思ったら、下痢が続くといったパターンが多いようです。
その他、お腹がなる、おならがよく出るという症状もあります。
また、特に下痢型の場合は、急に症状が起こるため、通勤や外出することが怖くなってしまい、そのストレスや不安によって余計に症状が悪くなってしまうというケースもあり、生活の質の低下を招く原因になっている人も少なくありません。
過敏性腸症候群の原因にはいくつかあります。
そもそも腸の中は善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類で腸内細菌のバランスは成り立っています。
悪玉菌が多くなると日和見菌も悪玉菌となり多くなっていき、腸内細菌のバランスが悪くなり、下痢や便秘になりやすくなってしまって過敏性症候群になるのです。
この腸内細菌のバランスは、家族間で同じ食生活をするため、腸内細菌のバランスも似てくるので、遺伝が関係していると考えられています。
また、他の原因として挙げられるのは生活習慣です。
脂肪分が多い食事を摂ることが多い、喫煙、アルコールを多く摂取すると悪玉菌が増えるため、過敏性腸症候群になりやすくなります。
さらによく原因として言われているのがストレスです。
ストレスや過度な緊張も腸内細菌のバランスに関係していると考えられています。脳と腸は一見関係なそうですが、脳がストレスを感じると、それが信号となって、腸に伝わり、腸の動きをコントロールする自律神経のバランスが崩れて、腸の動きが悪くなり、過敏性腸症候群の症状が現れるのではないかと言われています。
ストレスは心理的なこと以外にも、過労や睡眠不足による身体的なストレスもあり、そこに重ねて、高脂肪食をよく食べる、アルコールの摂取が多い、運動不足といった不規則な生活が続くと、さらに腸の動きが悪くなり、過敏性腸症候群となるのです。