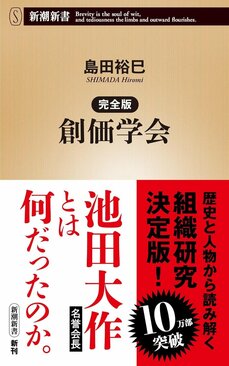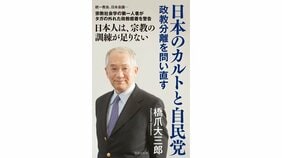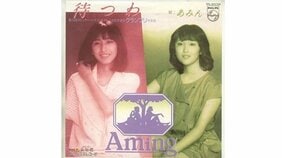封じ込められたカリスマ
池田については、創価学会の側だけではなく、創価学会と対立したり、敵対する側も膨大な情報を流してきた。けれども、その実像ということになると、正確なところはほとんど伝わってこなかった。晩年になればなるほど、創価学会の外部の人間で、池田に直接会ったことのある人間は少なくなっていく。私も結局、一度も会うことがかなわなかった。その姿を直接見る機会もなかった。
過去には、ルポライターの児玉隆也によるもののように、池田の日常に迫ったルポルタージュもあった。あるいは、松本清張や内藤国夫、田原総一朗のように、池田と対談した作家やジャーナリストもいた。
田原の場合には、創価学会の会館に出向いて対談しているが、松本と内藤の場合には、池田は対談場所にたった1人で姿をあらわした。松本も内藤も、そのことに驚き、単身で乗り込んできた点については評価していた。
とくに内藤の場合には、創価学会にかなり批判的な立場をとっていたため、創価学会の内部では、内藤との対談に反対する声が上がっていた。それでも池田は内藤との対談を決断した。対談の場でも、「なんでも質問してください」と前置きして、かなり意地悪な質問にもすべて答えていった。
こうした池田の姿は、創価学会が伝えようとしているものとも、外部のメディアが描く独裁者、権力者のそれとも違っていた。もちろん、これをもって池田の実像だと言い切ってしまうのは問題がある。
というのも、池田にかぎらず、カリスマ的な指導者は多面的な顔をもっており、相手や場にあわせて発言の内容を変えたり、態度を変化させることが少なくないからだ。
カリスマは、その場の空気を読むことにたけており、それに合わせられるだけの柔軟性をもっている。彼らは演技する存在でもある。池田は、自ら演技していると語ったわけではない。だが、巨大教団のトップに50年以上君臨したわけで、その間に、さまざまな顔を備えてきたと考えられる。
その点で、カリスマ的な存在について、実像と虚像とを区別することはほとんど不可能に近い。本人にとっても、もはやこれが自分の実像だと言えるようなものは持ち合わせていなかったのではないだろうか。
この相手に合わせて変化する多面性が災いすることもあった。
外部の人間から質問を受けた場合、池田は世間の一面的なとらえ方をくつがえすために、率直でオープンな指導者として振る舞おうとした。しかし、インタビューや対談は、学会員も読むわけで、一般の読者だけではなく、彼らをも満足させなければならなかった。
どんな意地悪な質問をされようと、臆することなく、忌憚のない素直な答えを返していかなければならない。そうなると、池田の答えは、あけっぴろげで、ざっくばらんなものにならざるを得なかった。
学会の組織にとって、とくに巨大教団を管理、運営していかなければならない学会本部にとって、外部の人間に直接池田を会わせることは、組織の維持という観点からは都合の悪いことを池田に言わせてしまうことにもなりかねない。
池田と対談した田原は、実際の対談内容は「中央公論」(1995年4月号)に掲載されたものとは異なり、池田はもっと大胆なことを語っていたと述べている。ところが、学会本部の側が、発言を無難なものに変えてしまったのだという。
池田を独裁者、絶対的な権力者として見ようとする人々は、池田の一存で巨大教団が動いているかのようなとらえ方をしていた。けれども、池田の発言は教団本部によって封じ込められている面があった。とても、その一存で組織を動かしているとは言えなかったのである。
前掲『池田大作』の最後に載せられたインタビューのなかで、池田は、自分が生涯にわたっていわれなき中傷や批判を浴び続けてきたとし、「私ほどみんなに監視され続けた人生も少ないと思いますよ」と述べていた。池田を監視してきた存在のなかには、当然外部のメディアも含まれるだろうが、同時に創価学会の組織、とくに教団本部も含まれるように思われる。
写真/shutterstock