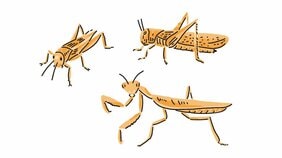世界一小さなエール
産まれたての赤子を扱うように、火種をそっと火口に入れて包み込み、長く優しく息を吹きかけて酸素を送ってあげる。
火種はとても消えやすい。絶対に絶やすわけにはいかないという緊張感と、限界を超えた筋疲労で、火口を持つ文の手はプルプルと震えていた。一方の縄は、文の耳元で世界一小さな声でエールを送り続けている。
縄「(ついてるついてるついてる。ついてるよ!)」
大きな声を出せば、火種が消えてしまうと思っているのだろう。それほど繊細で、緊張感のある時間が続いていた。文が火口に息を送り続けて30秒が経過しても、まだ煙は大きくならない。そこで、試しに空気を送り込む角度を変えてみる。すると、火口は一気に大量の白い煙に包まれ、その奥が赤く輝いた。
縄「ついてる ついてる ついてる!」
縄の応援の声量は次第に大きくなっていき、それに呼応するように、ボッと炎が燃え上がった!
興奮はピークに達したが、ここでもまだ油断はできない。急いで火口を地面に置き、上に乾いた小枝をのせていく。空気が入るよう、隙間を確保しながら慎重に、そしてスピーディーに。やがて中くらいの太さの枝に火がついたころで、ようやく炎は安定した。何も言わず、顔を見合わせる2人。
縄「……もう喜んでいいかな?」
原始の火には神様がいた
このとき、僕たちは初めて大声を出し、抱き合って喜んだ。その火はまぎれもなく縄文時代の人々が見ていた原始の火だった。
文「美しいなぁ」
縄「うん、美しいなぁ」
「美しい」という言葉があんなに自然と口から出たのは、このときが初めてだったかもしれない。それは、「綺麗」とか「かっこいい」という言葉では足りない、神々しさを含んだ存在だった。そう、その火には神様がいたのだ。
やがて夜の闇が降りてきて、僕たちの火が森の中で唯一の灯りとなり、まるで宇宙の中心に浮かんでいるような感覚になった。持てる力をすべて出し切った僕たちは、ただ黙ってその火を眺めていた。この小さな宇宙を満たしていた静かな充足感は、この先どんなに大変でも、この活動を続けていこうという決心を僕らに与えてくれたのだった。
文/週末縄文人(書き手:文)
写真/『週末の縄文人』より出典。撮影=横井明彦