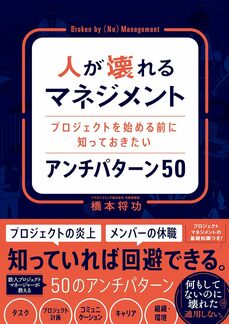「褒めてるつもり」ではダメ
日本では「評価に対する考え方」と「長い経済的な停滞」という2つの大きな要因が、仕事において無意識にネガティブなフィードバックが多くなりやすい状況をもたらしています。超少子高齢化の現代においては、この環境を変えなければ希少な人材を維持したり、個人の意欲を高めて労働生産性を上げて他社との競争に打ち勝ったりすることはできません。
ネガティブなフィードバックが蔓延し、「進んで新しい仕事を実施してリスクを取ることが損である」という社内文化を変えることは難しくても、自分の行動を変えていくことはできます。
まず個人で明日からすぐにできる方法としては、「ネガティブなフィードバックの割合を減らすこと」が有効です。部署やチームで仕事をする際は部下やメンバー個人個人のアウトプットの方向性や品質が高いものである必要があります。そこで、「ダメ出し」という形でネガティブなフィードバックをすることは避けられませんが、その際に相手から見てネガティブな評価ばかりにならないようにすることがポイントです。
たとえば、提出されたアウトプットに対して、「ここがすごく良かった」と相手の努力や創意工夫を認めたうえで、「この部分は修正が必要だから直してほしい」や「この部分は方向性が違うからこう変更してほしい」と、ポジティブな評価とネガティブな評価をセットにして伝えるようにするのです。
完璧主義者のマネージャーはしばしば「褒めてるつもり」や「態度で示しているつもり」と考えていることがありますが、明確に言葉にしなければ相手に伝わりません。必ずポジティブな表現とセットで伝えるようにするとフィードバックのバランスを保ちやすくなります。
文/橋本将功