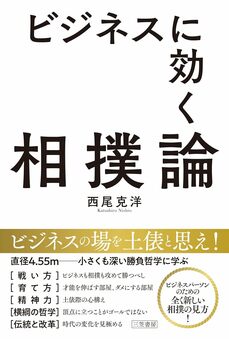中堅になってもなお、成長を止めないためには
千代の富士はこの時点でスキルと経験の限界に差しかかりましたが、ここから自身の相撲内容と脱臼グセに向き合います。
有名なエピソードですが、脱臼グセを克服するために千代の富士は当時まだ珍しかった筋力トレーニングを取り入れて肩の周りの筋肉を強化しました。
千代の富士といえば力士とは思えないような筋骨隆々(きんこつりゆうりゆう)なあの体型を思い浮かべる方も多いと思いますが、彼は1日1000回もの腕立て伏せと筋トレを行いました。
それは壮絶なもので、部屋の畳を4ヶ月に一度取り替えなければならないほどだったと報じられています。相撲のスタイルも、脱臼しないような形に変わりました。
相手を引っ張り込んでの強引な投げではなく、前まわしを引きつけて頭をつける、私たちが知っている強い千代の富士のスタイルに変更したのです。
1981年に初優勝を飾ったときの相撲もまさにこの形でした。
北の湖に頭をつけて素早く攻め、上手投げで仕留めたあの一番は、大相撲の名場面として今でも映像がたびたび紹介されます。この取組の視聴率は52.2%を記録し、相撲中継としては現在でも歴代最高の視聴率となっています。
その後は北の湖からバトンタッチを受け、一人横綱時代を経て35歳まで大相撲の第一人者として息の長い活躍を見せ続けました。脱臼グセは引退まで続きましたが、引退の1年以内に優勝も経験した本当に強い横綱でした。
優勝回数歴代3位の31回が、何よりもその強さを物語っています。
千代の富士のように素晴らしい才能を持っていても、どこか弱点があるとなかなか勝つことができないのは、体重制限のない大相撲の厳しさだと思います。
しかし千代の富士は二つの限界に真摯に向き合い、克服するための道を模索し、答えのないところに答えを導き出しました。これほどの小兵で、いわゆる横綱相撲とは異なるスタイルで一時代を築いた力士は千代の富士以外に存在しません。
持つ者だけが成功するわけではないということを、千代の富士は私たちに教えてくれました。
足りない部分があっても、自分の武器と苦手を克服するための方法にたどりつけば成功することも夢じゃないのです。
最後に勝てるビジネスパーソンになるために
一方でその道が過酷であることも事実です。
答えを教えてくれる人が誰もいない中、自分で考え、道なきところに道を作る。それが誤った道になることだってあり得ますし、角界は保守的な世界なので人と異なることをすると親方やファン、解説者から批判を受けることだって考えられます。
それでも挑戦し続けることで、「最後に勝つ人」になれるのです。
若い社長やキャリア組は限られています。席が空かない中でも試行錯誤を繰り返し、ようやく巡ってきたチャンスをものにして上がっていくしかありません。
チャンスが訪れるそのときまで諦めない粘り強さと、自分の強みを分析する客観的な目線を持つことが求められます。天才ではない以上、誰もが平等に苦労しなければならないという現実を受け入れていくべきです。
持たざる者にとって、成功への道が決して平坦ではないことを胸に刻み、日々精進していきましょう。
文/西尾克洋 写真/shutterstock