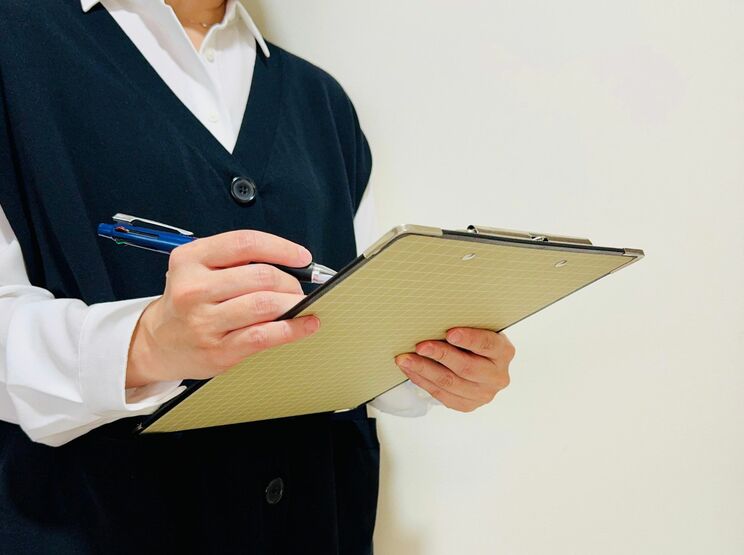信頼関係以前の問題もある…専門家の見解は?
スクールカウンセラーが制度化される前、調査研究委託事業の段階から20年以上にわたり、新潟県内の小・中学校でスクールカウンセラーを務める心理学者の碓井真史氏に、校内での相談内容の取り扱いについてなど話を聞いた。
「守秘義務はありますが、チームでの守秘義務と捉えている学校がほとんどでは。確かに、『担任が苦手だ』とか、LGBTQに関わるセンシティブなもの、『伏せてほしい』と念を押された病気のことなどの共有を控えたことはあります。
しかし、非常勤のスクールカウンセラーは、立場も弱く対象者から聞いた話を何も共有しなければ学校で孤立してしまいます。生徒を守るため、難しい悩みを抱える生徒や保護者とつないでもらうためにも、まずは学校側、教員と信頼関係を築くことが重要です」
文科省ではスクールカウンセリングにおける実施のガイドラインにおいて、“守秘”について以下のように定めている。
《守秘については、クライアントのプライバシーを守るために相談内容を秘密にするということ、ただし命に関わること、他者またはクライアント自身を傷つける恐れのあること、犯罪に関わることなどはそのかぎりではない》(文部科学省HPより)
つまり基本的には相談者のプライバシーを守らなくてはいけないが、内容に応じて「チームでの守秘義務」となっているのが実情のようだ。
子どもとの秘密を守り、やる気を持って働くカウンセラーも取材を進めるといるのだが、いっぽうで教員側から聞こえてきたのは信頼関係以前の問題だ。山梨県の公立中学校に勤務するY先生に話を聞くことができた。
「週1回、毎週水曜日の午後に複数名のカウンセラーが順番でスクールカウンセリングに来てくれています。職員室に常設されたデスクがあるため、話しかけやすい雰囲気はあるものの、人によって“能力の差”が大きいんです。
教員や生徒に寄り添ってくれるカウンセラーもいますが、子どもに『不登校は甘え』『悩みが大げさ』と突き放す人もおり、過去にはカウンセリングの後に不登校になった生徒も。そのため、信用しきれないところがあるんです。
カウンセリング後、生徒にアンケート記入をお願いし定期的に評価してもらい、不適切な者には研修を受けさせることで能力の差を無くしてほしい」
これを碓井氏に伝えると「能力の差はありますね」と共感した上で、このように続けた。
「スクールカウンセリング制度が始まった当初は、臨床心理士、公認心理師、精神科医のなどの有資格者で担われていました。しかし、全校配置を目指したことで有資格者のみならず、それに“相当する者”として、臨床経験のある人、心理学科の卒業者、現場経験者などにも拡大されました。
都心部には有資格者がたくさんいるため、2023年には東京都でスクールカウンセラーの雇い止めがあるほどだったのに対し、地方都市には有資格者が少なく能力に差が生じやすいのです」
また、スクールカウンセラーの特殊な職場環境も能力の差を作る要因だと指摘する。
「1人職場という環境では、教員のように大先輩を見て日々研鑽を積むようなことができない。横のつながりを持てる場を増やしていくべきではないでしょうか。また、スクールカウンセラーの在り方がまだ固まっていないことも一因でしょう。今後、現場の意見交換のもとコンセンサス(理念)を少しずつ固めていく必要性を感じています」