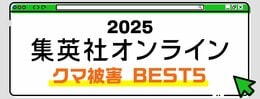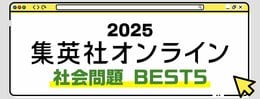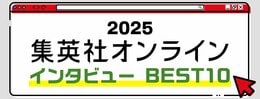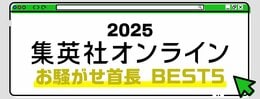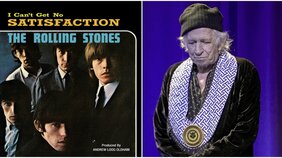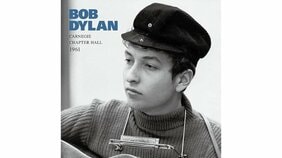「脂肪肝」を招く怖い「果糖」、「甘いものは別腹」は本当
ブドウ糖などの糖質は小腸から体内へ吸収されて血糖値を上げますが、果糖は小腸から門脈を通ってほとんどが肝臓で処理されます。ブドウ糖は約80%が筋肉で処理され、残りの約20%が肝臓で処理されるのに対し、果糖はほぼ100%が肝臓で代謝されるのです。
肝臓へ送られた果糖は肝臓で燃やしきれず、貯蓄されるのですが、その貯蓄のために中性脂肪に変換されます。果糖の摂取が多すぎると、肝臓に中性脂肪が蓄積して脂肪肝になるのです[Diabet Med 2015;32(9):1149-1155]。肝臓を作る肝細胞のうち30%以上が内部に中性脂肪をためている状態を脂肪肝と呼びます。
脂肪肝に陥ると、インスリンの効き目が悪くなるインスリン抵抗性が生じるため、質を量で補おうとインスリンが大量分泌されるようになり、肥満ホルモンとしての作用で太りやすくなります。
それだけではありません。肝臓で果糖を代謝する際に、非常に多くのエネルギーが消費されます。するとエネルギーが減り、肝臓からは、脳へ「もっと食べろ!」という指令が送られます。
こうしたメカニズムがあるため、ジュースなどから果糖を摂るとお腹が空きます。「甘いものは別腹」というのは本当で、果糖の仕業なのです。
果糖を摂るとなぜ食欲が増すのか。それに関して米国コロラド大学の研究者が「果糖生存危機仮説(Fructose survival hypothesis)」という興味深い仮説をアメリカ肥満学会の機関誌『Obesity』に発表しました[Obesity(Silver Spring) 2024; 32(1): 12-22]。
肝臓でエネルギーがどしどし消費されている状況を、脳は生存の危機を迎えている状態だ(冬眠の直前の時期で、いまこそ脂肪を蓄え、エネルギー消費を低下させておかないと、冬眠中に餓死してしまう)と解釈します。
このため飢餓感から食欲が高まり、飢餓に備えた備蓄エネルギー源である体脂肪の合成を促したり、分解を抑えたりするというのです。