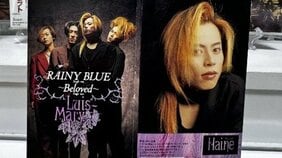意外と幅広い昼ドラの題材と作風
「昼ドラと言えば女性週刊誌に載っているような通俗的なメロドラマのノリがお馴染みで、不倫などを題材にした作品が主流でした。普段は清純そうな人のドス黒い人間関係や隠れた欲望を描くことで、視聴者の興味を惹くという形が昼ドラ特有の世界観の根底にあったように思います」と話す木俣氏(以下同)。
昼ドラの歴史は意外と古い。日本では1969年から2009年3月まで40年間に渡って放送されていた『愛の劇場』(TBS系ほか)や、1964年から『ライオン奥様劇場』(フジテレビ系)として昼の帯ドラマシリーズ枠が始まった。
“新人女優の登竜門”とも言われる朝ドラ(近年は趣が少し異なるようだが)と同様、昼ドラも主婦などの視聴者を意識し、女性を主人公に描かれる作品が圧倒的に多い。
また、1970年代の昼ドラでは家族や主婦を題材にしたコメディやホームドラマ、「連続テレビ小説」のような女性の一代記的な作品が主で、ドロドロ愛憎劇だけではなかった。
現在、昼ドラと聞いて一般的に想起されるドロドロ路線のドラマが目立ち始めたのは、1986年の『愛の嵐』(フジテレビ系)以降のこととされる。
「朝ドラは明るく爽やかな作風で倫理観の高めな作品が圧倒的に多く、これに対抗するように昼ドラは、欲望渦巻くドロドロ愛憎劇という真逆の方向性で差別化されていったように感じます。
朝ドラと昼ドラの作風の違いは当然、NHKを好む視聴者層と民放を好む視聴者層の属性的な違いも反映されていたのだと思います」
もっともリアルタイム視聴が主だった時代は、NHKの朝ドラも民放の昼ドラも 視聴者が明確に棲み分けられていたわけでもない。家事の合間にそれぞれの時間帯で楽しまれていたドラマだったようだ。
「朝ドラが戦前~戦後を生きた女性の一生などを題材にした物語を基本にしながら、たまに若年層を意識した現代作品などにも挑戦するように、昼ドラも昼メロの合間にほのぼの系作品がわりとありました。
そもそも昼ドラは2002年の『真珠夫人』(フジテレビ系)、朝ドラは2013年の『あまちゃん』を機に、その後の新たな視聴者を獲得したところもあります。それ以前はお茶の間のテレビから“なんとなく流れている放送枠”だったのかなと」