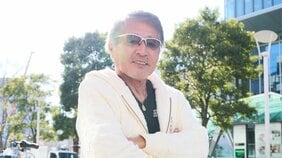どこからでも盗塁できる
特徴的なのは、清原、デストラーデ以外は「足」があること。エンドランを仕掛けるのに十分なスピードがあるだけでなく、それぞれが単独スチールを仕掛けることもできました。
もちろん、それは単純に足が速いからというだけでなく、チームとして準備をしていたからできたことです。
特に森さんの野球では、リスクを負って盗塁を仕掛けるより、送りバントで確実にスコアリングポジションに走者を進める戦術が多用されました。そういう意味では、まさに「ここ一番」というところで盗むのが西武の盗塁だったと思います。
先頭打者が塁に出て、バントで送れば一死二塁です。でも、これが一死三塁にできるのならそれに越したことはありません。そういうチャンスはないかと、いつも狙っているのが西武流で、盗塁はそのときに活用する戦術のひとつでした。
たとえば、試合終盤で先頭打者だった2番平野さんがフォアボールで出塁したとします。相手チームの監督にしてみれば、先頭打者のフォアボールほど嫌な予感に襲われるものはありません。昔から、先頭打者へのフォアボールは得点になりやすいと言われ続けています。
そこでピッチャーを代えるケースもけっこうあります。先頭打者へのフォアボールで焦ってしまったピッチャーがガタガタに崩れることも多いので、ひとつ流れを断ち切ろうという考えです。
バッターは3番秋山なので、バントはありませんが、相手ピッチャーにしてみれば、打ち取るのが難しいバッターです。失投すれば2ランホームランを叩き込まれてしまいます。できることならダブルプレーで……と、いろいろと神経を使います。
その初球、代わったばかりのピッチャーも、それをリードするキャッチャーも、一塁走者の盗塁にまで神経が回らなくなっているんじゃないか。西武のランナーは、いつでもそうやって相手の隙を狙っていました。
今の例で言えば、初球に走ることに意味があるのであって、2球目に走ったのではダメなのです。
どういうことかというと、この初球、相手バッテリーは打者にばかり気を取られて、一塁走者への警戒が薄くなっていました。その1球を見た上で、じゃあ2球目行けるんじゃないかと思っても、それに気づくのは自分たちだけではありません。
相手ベンチもそれを見て、ちゃんとランナーを警戒しろ、モーションが甘いからクイックで投げろと指示が出てしまいます。
つまり、選手だけでなく、ベンチも含めて、エアポケットに入るような瞬間、その隙をつかなければ意味がない。だから、それをいつも狙っていたというわけです。