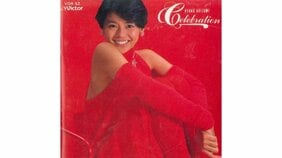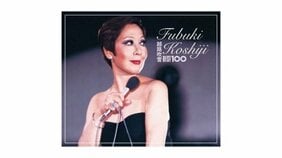在留外国人急増の対応策は…
今回の一連の騒動や現行制度に関して大濱崎氏の見解を聞いてみた。
「まず医療は、本来あるべき形(健康・健常)に近づく(ゼロからプラスではなく、マイナスからゼロにする)という観点から、利益を生み出す側面とは離れており、受益者負担の原則はなじまないと考えます」
と主張。その理由について、
「高額療養費制度や国民健康保険制度は、所得の高低で提供される医療の質に差が出ることを防ぐことに着眼がなされていますが、実際に1984年の『健康保険制度抜本改革』では、一部負担の導入により、旧日雇労働者健康保険の受診率が2割以上減少したとする研究があります。
これは、医療負担が受診行動に大きな影響を与えることを示しており、高額療養費制度における自己負担額の設定も、慎重に検討すべきであることを示唆しています」
さらに今回の同制度を巡る上限額引き上げの議論と、玉木氏の外国人に対する議論についても一線を画すべきだと警鐘を鳴らす。
「数万円支払うことで何千万円分もの治療が受けられる、という論は、在留外国人のみならず、所得の低い者や国民健康保険の加入後わずかしか時間が経過していない若者、あるいは生活保護者にも該当する話であり、反外国人の問題とは別枠で議論すべきではないでしょうか」
その一方で、2024年6月段階で国内の在留外国人の数が約359万人と過去最多を記録するなど増加の一途を辿っている。その事実を「貴重な労働資源」とも捉えられる一方、埼玉県川口市の「クルド人問題」のように移民増加に伴う摩擦が生じるといった問題もある。
今後、在留外国人が増える中、制度改正などの観点からどんな対応が求められるのか。
「まず、世論形成をはかる政治家にこそ、反外国バイアスなどを排除した冷静な議論が求められます。データやエビデンスに基づいた議論を前提にすべきです。
そのうえで、国民皆保険制度である国民健康保険は、所得再分配の手段として機能している側面があります。今後、在留外国人が増えたときに、持続可能性と公平性の観点から、所得再分配の手段としての機能が保ち続けられるかは、重要な視点だと考えます。
医療先進国である日本に、医療ツーリズムとして来日する外国人は、今後も増えることが想定されます。医療ツーリズムをひとつの産業として捉えるのであれば、例えば自由診療における医療費未払い問題の解決(医療費負担能力の証明や、身元確認の強化、医療費請求に関する二国間協定の締結など)が優先すべき課題のはずです」
政治家も国民も一人一人が、明確なデータを基に、冷静に現状を分析し、議論に参加することが求められている。
取材・文/集英社オンライン編集部