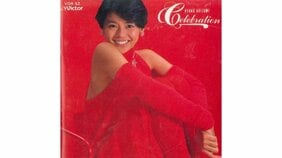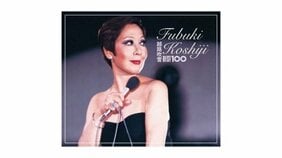コロナ禍で肥大化した不安
小山田 古川さんは帰省されたときに親戚の方々が交わす会話を聞きながら、これは小説にできるなとメモを取られたりするんですか?
古川 そうですね。ただ、それは小説にしたいからというよりも、メモを取らざるを得ないからなんです。基本的に島に帰ると、みんなとにかく僕の知らないことをよく喋る。どこどこの誰々さんの娘さんがどうのこうの、と。小説家になる前からうんざりしつつメモを取っていました。ただ、確かにそのなかには聞いているうちから情景が目に浮かんでくる話もあって、それは小説になりそうだなと思いますね。
小山田 初めて『縫わんばならん』を読んだときに、ご自身より遥かに年上の人が若い頃に見ていたもの、感じていたことをこんなにありありと描けるものなのかとびっくりしたおぼえがあります。当時の景色などだけではなくて、その人が若い頃感じた戸惑いとか後悔、高揚などまですごく本当の感じがして。話を聞くのと、実際にそれがどう見えていたかを理解したり追体験して文章にすることはまた別のことじゃないですか。古川さんはどうやって親戚の方の昔の姿を自分の前に浮かび上がらせているんだろうと気になっていました。
古川 意外とすらすら出てくるんですよ。この人ならこういう景色を見るだろう、こう感じるだろうというのが。
小山田 それをデビュー作の時点からできていたんですね。新潮新人賞を受賞する前にも何度か作品を応募していたとインタビュー記事で読んだんですが、そのときから島の一族の話を書いていたんですか?
古川 そうですね。最初に島のことを書いた小説は二次選考を通過できたんですが、翌年、全然別の小説で挑んだら一次で落ちちゃって。だからもう一度、島の話に戻したら受賞できました。
小山田 そこからずっと島の話を書き続けているわけですね。でも『背高泡立草』で芥川賞を受賞したあとは一度、島の話から離れたじゃないですか。また『港たち』で戻ってきたのはどうしてですか?
古川 コロナがきっかけです。コロナ禍が始まってからしばらく帰省ができなくなって。だったらこの機会に小説で帰省をしてみよう、と思いました。帰省できるのが当たり前だったときとはまた違う小説が書けるんじゃないか、と。執筆していた時期はワクチンがちょうど開発されたくらいの時期だったので、いつ収束するのか見通しが全く立っていませんでした。そうするとふだんよりも帰りたいという気持ちが強くなって、書く対象との精神的な距離も近くなったような感覚がありました。それはあの時期に特有の現象でしたね。
ただ、最後の「間違えてばかり」を書いていたときは、その感じも薄れてきていて。コロナに対してアンテナを張り続けるのに疲れてきていた頃だったので、危機意識は弱まっていました。買ったものを消毒して冷蔵庫に入れるみたいな生活をこれ以上してると神経まいっちゃうなと感じて、緊張を弛めた時期の作品です、あれは。
小山田 確かに「間違えてばかり」には、あまり不安のような意識は書かれていませんね。
古川 実際にあの作品を書いていたときは島に帰ることができるようになっていましたし。不安や心配の気持ちは「港たち」の執筆時が一番強かったです。あのときは婆さん、死んじゃうんじゃないかと思っていたので。
小山田 故郷にいる親戚が亡くなると、その空間じたいが持つ意味が変わるんですよね。私は今回、「おおばあちゃん」という短編のなかで大伯母が亡くなる話を書きましたが、実際に亡くなったのは祖母でした。祖母がいない実家は、なんだか全く別の故郷になってしまったような感じがして。故郷は場所じゃなくて、人に帰属しているものなんだと気づかされました。私は結婚して家を出ていたので、大事なところにはあまり関われなかったんです。亡くなる前にレコーダーを回しながら昔の話をしてもらったんですが、もっと話を聞いておけばよかったなという心残りもあります。
文字を読むから小説は面白い
古川 コロナ禍って時間の感覚がどこかぼんやりしていた気がしませんか? 二〇二三年くらいまでの時間を振り返っても、いつ誰が死んだのか、あのできごとは何年の何月のことなのか、記憶がないまぜになっているというか。
小山田 それはよくわかります。思い出そうとすると混乱する。最初の頃はコロナのことを書くと、時間が規定されちゃうから無意識に避けていました。そういう書き方がダメだということでもないんですが、どこか不安な感じがしたというか。だからあの時期は昭和の終わりから平成の初めくらいまでを舞台にしたものばかり書いていたんですが、だんだん書かないと忘れるなと気づいて、それからは意識的にコロナのことを書くようにしました。むしろ今を書いておこうって。
『最近』はそのときに書いた連作なんですが、もともと編集部から長編を書きませんかという依頼があったんです。長いのは無理ですとお断りしたら、じゃあ連作ならどうでしょうと言われて、それならできるかなと思って引き受けました。連作だからそれぞれの短編に通じるものを決めた方がいいだろうと考えて、新型コロナウイルスと夫婦の話を書くことにしました。
古川 小山田さんの小説はどの短編を読んでも、小山田さんらしいなと思うのと同時に、新しいことをされているのがよくわかります。今回の『最近』もそうで、例えばLINEのやり取りが文中に出てきますよね。そこだけ文字が横書きになって、歪な感じがある。
あと思わずメモをしたのが、収録作の「ミッキーダンス」で妻の大伯母の法要が終わったあとの会食の場面です。黙々と食べる聡明の横で、お義母さんが義弟の登くんにローストビーフをわけるくだりがありますよね。遠慮がちな登くんにお義母さんは「いいのよお母さんにはこれ多いからほらこれお肉、ロースト、ビーフ……!」と言いながらお肉を取ってあげる。動作にぴったりのセリフ体になっている気がしました。他にも「?!」がところどころに見られるんですが、その使い方はどこか漫画的な感じがしました。LINEの横書きも三点リーダーも「?!」の使い方も視覚的な表現上の工夫だと思うんですが、どれも自然に導入されているのがいいですね。
あえて省略するような書き方がされているのも面白かったです。これも『最近』に収録の「カレーの日」の中に出てくるくだりですが、「雄大な、偽物のような色の空、真っ白い雲、広大な赤銅色の大地に聳えるごつごつした山、表面がカリカリしてパンはふわふわ」……といった具合で、シームレスにパソコンの待受画面とカレーパンが繋がるところなんか、小山田さんって感じがします。
それから読点をあえて使わずに書いているのも小山田さんの文章の特徴だと思います。あれは心の動きの速度が反映しているということですか?
小山田 そうですね。語り手の呼吸に合わせているというか。そこら辺は以前だったら編集者に鉛筆で指摘されて悩んじゃうところなんですが、今は自分を信じて無視できるようになりました。文法的に間違っていたとしてもこれでいいと思って書いています。
LINEのところは雑誌掲載時には縦書きだったんですよ。絵文字の部分だけ英語で横書きにしていました。LINEの絵文字ってスマホの通知画面に表示されると(sweat)とか出るじゃないですか。汗かいて焦ってる絵とか。あれをそのまま書いたら面白いんじゃないかと思って。
本にするときにLINEの文面は全部横書きにしませんかと提案してもらったのでやってみたら、想像していた以上に異様な字面になりました。ただでさえ改行も会話もないのに、そこだけ横書きになっていると波打って気持ち悪く見えて、やってよかったなと思いました。LINEの絵文字って自分が思っていた意味と違うときがあるんですよね。自分でもわけがわからないまま送ってるときがあるので、その感じを出したかったんです。
古川 僕はよく水原涼さんとLINEをするんですが、お互いになぜか般若のスタンプを送り合うんですよ。「すみません、寝てました。般若スタンプ」「こちらこそすみません。般若スタンプ」みたいな感じで。確かにこれも文章にしたら異様ですよね。
小山田 そうそう。そういうコミュニケーションも文字にすると変じゃないですか。第三者が見たら、何言ってるんだ? ってなりますよね。私はそれを読者に味わってもらいたかったんです。小説って必ず一文字ずつ追いかけながら読むじゃないですか。私がどんなに瑣末でしょうもないことを書いたとしても、必ず目でそれをなぞらざるを得ない。よく考えたらそれって魔法みたいですごいことなんじゃないかと思うんです。
先日、三軒茶屋の本屋twililightさんで柴田元幸さんとトークイベントをしたときに、柴田さんが面白い話をしてくれました。ある人が、映画を見る習慣のない人たちに手の洗い方を伝えるような内容の教育的な映画を見せた。上映後にどう思ったか聞いてみると、多くの人がニワトリが元気だったみたいな感想を口にしたらしい。作品の内容ではなく、手の洗い方を説明している後ろでニワトリが歩いているところに目がいってしまったようです。多分、手洗いよりニワトリに興味があるから。映画のようないろんなものが映る表現だと、そういうことが起こりうるんですよね。
漫画もきっとそうだと思います。一コマ一コマどう読むかはきっと読者によって違うし、それが面白さでもあると思います。でも小説は文字しかないから、絶対にそれを追わなきゃいけませんよね。どんなに細かい描写でも、作者が書いたものを読者は一緒に読んでくれる。小説を書くこと、読むことにはそういう面白さがあるんだと今更ながら気づいたので、今回、その特徴を活かして書こうと思いました。
古川 なるほど。だから『最近』には、日常生活の些細なことや小さな時間が念入りに描かれているわけですね。
小山田 でも、それは古川さんの小説にも言えますよね。例えば、方言も映像の中で聞いていたら、一つひとつの言い回しなんか気にしないかもしれない。小説だから意識が言葉だけに向かうんですよ。稔のような孫世代の気持ちになってそれを読むことができるのは小説ならではなんだと思います。古川さんの書く方言が私はとても好きで、祖父母世代、親世代、稔世代のそれぞれの声を、音声としてではなくて文字として聞き分けながら読んでいる感覚があります。意味やリズムなど小説の一部として調整しておられるんだろうなと思うんですけど、そこからはみ出すような本当らしさがあって。
現在に縛り付けられている感覚
小山田 ちなみに方言に関していうと、私は今回、方言を書かなかったんです。自分の小説は何を書いても広島の話になると思って書いているんですが、読者には舞台が広島かどうかわからないようにしたかったんです。だから登場人物の会話もできるだけニュートラルな言葉で書きました。
というのは、読者に自分にとっての最近のできごととして受け止めてもらいたかったからです。読みながらあの頃の日々を思い出して、それぞれの最近の話にしてほしいなと思いました。そのためには、土地じゃなくて書かれている時間の方に注目して読んでもらう必要があるので、なるべくどこの地方の話かわからないようにしようかなと。
古川 だからタイトルが「最近」なんですね。
小山田 はい。でも、初稿のときは違って、「豊かな世界」という案が出ていました。日常の小さいことがいかに豊かであるかみたいな意味だったんですけど、編集者さんと話しているなかでちょっと違いますかねとなって変えました。古川さんの「港たち」はどういう意味で付けられたんですか? 「港」が複数形というのは珍しくてハッとしました。
古川 最初に、人間とはなんぞや、みたいな哲学的なことを考えていたんです。人間が現象としてあることを証明するのは、人と人の間にある何かなんじゃないか。互いの間には声があり、それを発したり聞いたりすることで、そこに人がいることがはっきりとわかってくるんだよな、と考えをめぐらせていました。
人の間を行ったり来たりする声が船ならば、そこにある空間は港だと言える。お盆で何人もの人間ががやがやしているんだから、港の複数形でいいだろうと思ったわけです。
小山田 じゃあタイトルを先に決めてから中身を書いたんですね。
古川 ええ、『港たち』に関してはタイトルが先でした。
小山田 とてもいいタイトルだと思います。確かに人と人がいれば、必ずそこには声が出入りする港があって、水嵩が増すこともあるし、足が濡れることもある。
古川 「最近」っていうのもいいタイトルですね。現在の時間が刻まれているのがよくわかる。
小山田 今回の収録作はできるだけいつのできごとなのかわかるようにしたかったんです。新型コロナウイルスの流行は何も終わってないのに、いつの間にか終わったことになっている。だからこそ、あのとき何があったのか書き留めておかないといけないなと思いました。物事が進展する過程にはいろんなフェーズがあるから、書いておかないと全部なかったことになっちゃうな、と。
でも、それはコロナだけに当てはまることじゃないですよね。ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるパレスチナでの虐殺。これまで「ふつう」だと思っていたものが「ふつう」ではなかった。「ふつう」ってこんなに移り変わり続けるものなのか。そう気づかされたのが今の時代なんだと私は感じています。「ふつう」が変わってしまう感覚を小説にしておきたかったので、今回それを連作として言葉にできてよかったと思っています。
古川 僕はコロナ禍が始まってから、しばらく気になるニュースを逐一メモしていました。でも、そのうちにちょっと追いつかなくなって。最初は、今日は何を食べたとかそういう日常的な記録の端っこにニュースを書き留めておこうと思って始めたんですが、ニュースを書くためだけにメモ帳をまるまる使わなきゃいけなくなった。これをずっとやってたら疲れちゃうなと思って、結局やめてしまいました。
地震や戦争、気候変動やインフレ。いろんなできごとが間断なく起こり続けていて、今という時間に自分が縛り付けられている感じが二〇二〇年以降ずっとしています。そんな世界で小説を書くと、現在の時間がどうしてもそこに反映せざるを得ないんでしょうね。例えばノスタルジーに傾斜した「鳶」のような作品ですら、純粋に過去への郷愁の念だけを書くのは難しい。そこには必ず現在が溶け込んでしまうんです。
小山田 そうですよね。小説を書いていた時点の現在が刻まれるんだと思います。『港たち』の作品はどれもその繋がりが自然で豊かだと感じました。昔から馴染んだ親族や家族の声や仕草と、その時々で思い出す過去、そしてそれを思い出すに至った現在の自分の外側にある世界と。
『最近』に収録された作品をゲラで読み返した時、書かれていることがちょっと古いなという気持ちにもなったんですよね、すでに。読者にもその落差を感じながら読んでほしいです。小説のなかのできごとと今の自分との距離を考えながら、あのときのことをとにかく思い出してほしい。読者の方々が自分の記憶を小説のなかにどんどん混ぜていってくれたらいいですね。
古川 小山田さんは「あとがき」にまだ書き終えていないと書かれていましたね。
小山田 いくらでも書けるという気持ちがあるんですよ。小説のなかにいる彼らは私でもあって、あなたでもあって、この社会にいる全員でもあるということを私は書きたかったので、今後もそのことを書いていきたいと思います。どういうかたちになるかはわかりませんけれど。
古川 僕は小山田さんほど腰がすわっていないので、うろちょろうろちょろしながら違うものを書いていきたいと思います。『港たち』では一つの共通した世界を書いたから、もしかしたら次はもっと政治的でジャーナリスティックな小説になるかもしれません。
小山田 今後も古川さんの作品を拝読するのを楽しみにしています。
(2024.11.28 神保町にて)
「すばる」2025年3月号転載