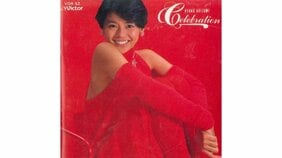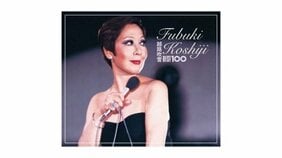現実を虚構のなかで語り直す方法
小山田 私も古川さんに聞きたかったことがあります。おそらく古川さんの小説は、ご自身が見聞きしたことが根底にあるんだと思います。一家の話や島のできごとなど現実がベースになっていると思うんですが、書いていくうちにどこから小説になっていく感覚をおぼえますか?
古川 どうなんでしょうね。確かに小説に書かれていることは、記憶や経験のかけらとしてまず自分のなかにあるものです。例えば「シャンシャンパナ案内」だったら、原っぱに雷に打たれたトンビがバタバタと死んでいた場面や、吉川の納屋に敷き詰められた漁網の上に寝っ転がるところは、僕が実際に経験したことです。
ただ、一つひとつは別の日のできごとで、それを僕が勝手に繋げているだけですね。小説には納屋で寝ていたら雷雨の音がして目がさめたと書いているのですが、現実にはそのとき嵐まではやってこなかった。だから小山田さんのおっしゃるように、あたかも本当にあったことのように思い出しているのかもしれません。
小山田 納屋で寝っ転がったことと嵐に遭遇したことは別々のできごとだったんですね。書いているうちに自然にひと繋がりになるんでしょうか?
古川 というか、別々のできごとをくっつけてしまうのは自分の実力不足のせいなんだと思っています。一つひとつを別々に書ければもっと小説としていいものが書けるような気がするんですが、どうもうまくできない。だから、仕方なく同じ日のできごとにしています。
小山田 でも、親戚の方の話や自分の経験したできごとをうまく取り出して組み合わせることで、これだけ面白い小説に仕立て上げられるのが古川さんの力なんだと思いますよ。トンビの死体が転がっている情景はマジックリアリズム的な表現なのかと思わされましたし。
古川 あれは子どもの頃の記憶ですね。前日、婆さんちで勉強かゲームをして遊んでたら雷がゴロゴロ鳴り出したんですよ。でも嵐はすぐに去ったので翌日の昼に海に泳ぎに行ったら、原っぱに真っ黒焦げのトンビがバタバタと落ちていて。トンビも雷に打たれるのか、と。
小山田 意外です。地球に長いこと生息しているトンビも雷の日に身を守る術を持たないんですかね。ちなみに「鳶」という題の短編も収録されていて、こっちの鳶は幻想的な雰囲気で。稔は幼い頃、父親と島を歩きながら、たくさん飛び交う鳶を見かけた。一羽の鳶が空中に停止している姿に目を取られていると、気づけば同じく化石のように止まったまま浮かぶ鳶たちがあたりを囲んでいたという。そのうちの一羽を父が素手で触ってどかすんですよね。この光景、すごいなと思いました。
古川 あれは嘘ですね。
小山田 こっちは完全な虚構なんですね。だけど鳶の実感はとても生々しかったです。やっぱりにおいとか音とかが明晰に語られるところとフワッと不思議なところが、人の記憶らしく入り混じっていて。
古川 この作品の最後も我ながら小山田さんっぽさがあるなと感じています(笑)。過去と現在がシームレスに繋がる感じが特に。「鳶」を編集者さんに送ったときには、小山田さんを目指して書きましたと言いました。この書き方を一度やってみたかったんです。
小山田 恐れ入ります。そう、「鳶」では、親族の結婚式というざわざわ落ち着かない現代の話と、子どもの頃の不思議な記憶とが交互に書かれていて、その二つが一つになっていく書き方がすごくいいなと思いました。
並んで歩くときの温かさ
小山田 『港たち』の収録作はどれもいいんですが、私は特に「シャンシャンパナ案内」が好きでした。最後のページなんて読み返すたびにちょっと泣いてしまって。古川さんの小説にはデビュー作からずっといつも温かさがあるんですよね。人間を信じているというか、優しい眼差しでいろんなものを見ているんだろうなって毎回思わされます。
「シャンシャンパナ案内」は、稔がタッコ婆とシャンシャンパナと呼ばれる磯を一緒に歩く小説ですね。タッコ婆は目がよく見えないから代わりにまわりに何があるか教えてあげなきゃいけないんですが、そこに何があるかはタッコ婆の方が詳しい。「もうトリジェ辺りやろね、ここいらは」と言われても、地図には載っていないような地名だから稔にはなんなのかわからない。タッコ婆に聞いてもこのあたりをそう呼ぶとしか教えてもらえないから、はっきりとした正解のないまま稔のなかでトリジェはトリジェであり続ける。二人のそんな会話に優しさが滲み出ているのがいいですね。
古川 ありがとうございます。「シャンシャンパナ案内」は何でもない狭い磯を歩きながら、最後に「ずいぶん広かねえ」と言わせたいがために書いた小説でした。
小山田 そのラストを思い出すだけでじんわりきます。単なる広さではなくて、お互いの言葉や記憶をやりとりしながら歩くことで、その感覚に至るんですね。この作品には他にも好きなシーンがいっぱいあるんですよ。例えば、散歩に行こうと言い出したタッコ婆に稔が「どこさな 行こうか?」と聞くと、「納屋ん方ば行こうや、わがの小説の」と笑いながら言うところ。私も田舎の親戚の集まりに行くと、孫や姪である自分が小説を書いていることをいじられることがあるので、身におぼえのある会話だなと微笑ましくなりました。
あと、エグチンマエと呼ばれる場所を通り過ぎたあたりから、二人で昔のことを思い出していくのもよかったです。みんなで釣りをしたときのことや、テトラポッドで房状になったイカの卵を獲ったこと。最後には亡くなった祖母が磯で泳いでいる稔にお弁当を持ってきてくれた日のことも思い出される。祖母が作った唐揚げのお弁当を美味しそうに食べる子ども時代の稔がとても印象的でした。
目の見える稔がタッコ婆を一方的に案内というか先導するわけではないんですよね。お互いがお互いを案内するように歩くから、今だけ、二人だけのシャンシャンパナが初めてここにできあがる。もしかすると二人それぞれが見ている、思っているシャンシャンパナは全然違うものかもしれないし、こうやって歩いたことを二人は忘れちゃうかもしれないけど、でも、言葉にして小説に刻んだからこのことはずっと残る。だからこの小説は温かいままであり続けるんだと思います。
古川 今の小山田さんのお話を聞きながら、そういえば今回の短編集には誰かが誰かと一緒に歩いている場面が多いなと自分で気づきました。「鳶」だったら稔と父親の明義、「港たち」だったら稔と浩が並んで歩いていますし。短編の長さだと誰かと誰かが二人で会話している方が収まりがいいからそう書いただけなんですが、結果的に二人が随伴して歩くことで互いの意識と記憶が重なる場面が多くなったような気がします。
小山田 確かにそうですね。だから温かさを感じるのかもしれません。そういえば『文學界』の「身体を記す」というリレーエッセイでも、古川さんはお兄さんと一緒に歩くことを書かれていましたよね。小説のなかで誰かと誰かが会話をしている場面を描くときって、会話だけを書くのは難しくて、だから自然と何か動作をしながらになる。動きや視線が変わるのに応じて言葉を繋いでいった方が書きやすいですから。
思い出すという行為も何かをしながらの方が自然にできると思います。『港たち』ではそれを一人でやるんじゃなくて、二人でやるからより一層、得がたくありがたく温かく感じるのかなって。もちろん古川さんが読者がグッとくるように温かいものを書いてやろうと意識的にされているとは思いません。島の親戚との会話を書いていると結果的にそうなるのが古川さんの小説の面白さなんでしょうね。
ボツになった小説とどう向き合うか
小山田 前作『ギフトライフ』は古川さんの作品のなかでも異質な小説でしたね。島の親戚の話ではなく、生体贈与が行われる近未来のディストピアSFになっていました。ただやはりあの小説にも温かさはあるんですよ。物語が舞台とするのは救いようのない世界だし、嫌なこともたくさん書かれているのですが、古川さんらしさはありました。あの作品はどんな意識で書かれたんですか?
古川 実は『ギフトライフ』の前に当時『新潮』の編集長だった矢野さんに二度ほどボツにされたんです。で、もう何も浮かばなくなって、SFの短編でも書いてお茶を濁しておこうかなと思って書き始めた小説でした。
小山田 ボツになったのは島の親族ものですか?
古川 そうですね。矢野さんに『背高泡立草』から何も動いていないとダメ出しをされてしまい、まぁそうだよな、と。全く違う可能性を探ってほしい、悪を書けと言われたので、自分から遠い世界の物語を漫画のような展開で書いてみました。
小山田 そういう注文があったんですね。私もずーっとボツが続いた時期がありました。書いたものが全ボツになったこともあるし、言われたものが書けなかったこともあって。あのときはすごく苦しかったですね。
でも、私が敬愛しているある小説家の方とそのことについて話していたら「私もこの前、長編まるまるボツになりましたよ」とおっしゃってて、変な言い方ですが鼓舞された気持ちになりました。こんなすごい人もそういうことがあるんだと思ったら気が楽になったというか。
古川 僕は『新潮』の矢野さんには「これを読め!」みたいな原稿を渡したくなっちゃうんです。でも、そういう小説って力が入りすぎて、ガワだけは勢いあるんだけど中身が追いついてないものになりがちで。だから矢野さんにはよくボコボコにされていました。
小山田 なるほど。私は広島に住んでいて単純に距離があったこともあって矢野さんに直に指摘を受けたことが多分なくて……怖いような羨ましいような。でも、直すのって難しいですよね。小さい指摘は簡単だけど、大きい漠然としたダメ出しだとそこからの修正がいつもなかなか大変で。
古川 矢野さんは時間をめちゃくちゃかけて指摘してくれるんですよ。アドバイスの数があまりに多いから聞いてるうちに、わかりました、全部直します、という気持ちになります(笑)。
小山田 そうなんですね(笑)。私は直し始めると嫌になってきちゃって、自分で作品ごとボツにしちゃうことがあります。だからしっかり直せる人はすごいなと思います。
古川 基本的に矢野さんの言うことはもっともな指摘ばかりなんです。だから受け入れるしかないというか。ただ、『ギフトライフ』のときは、書き直した新しい小説もダメだと言われたので、さすがに、どうしようかとなりました。
小山田 それを乗り越えて新しいものを書かれたんですね……確かに、ボツにされた作品が世に出てたらと思うとゾッとはするんですよね。一生懸命書いた作品がボツにされるときは苦しいし、私も電話越しに感情がうまく伝わらなくて涙ぐんでしまうこともあるし、ここがダメという指摘はわかるんですが。迷惑かけてるな自分、と思います。
古川 小山田さんはボツになった作品はがらっと変えて書くんですか?
小山田 全く違う小説にしますね。部分的に使ったりとかはあるかもしれませんが、基本的には一から書き直します。一度、長編だと思って書いていたものがダメだと言われ、ふと短編にしたらうまく書けたということはありました。それは指示に従ってやったわけじゃなくて、直し方がわからないから、思い切って短くしてみたらたまたまうまくいったケースですね。
古川 捨てがたい場面を否定されていたらどうしますか?
小山田 嫌になるし、受け入れられないかもしれないけど、編集者がダメだと感じたこともまた確かなんですよ。私は編集者の方を信頼しているので、指摘してくれることをありがたいと思って受け止めようと思っています。うまく直せないかもしれなくても。