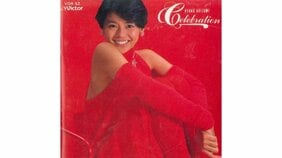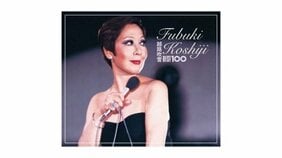戦争を「起こさなければならない」とき
むしろ、多くの国がロシアや中国への対抗連合を組織している事実は、ロシアや中国こそが潜在覇権国であることを示しています。だからこそ、ヨーロッパの国々はNATOを形成してロシアに対抗、東アジアでも日本、韓国、台湾、フィリピンなどが緩い協力体制を築いて中国に対抗しているのです。
そして、どちらの対抗連合にもアメリカは加わっています。
なぜ、最強の国であるはずのアメリカは恐れられないのか?
なぜ、アメリカより弱いはずのロシアと中国は最も恐れられるのか?
この疑問に答えるには、まず勢力が経済力や軍事力だけでは決まらないこと、加えて地理が国の勢力に多大な影響を与えることに注目する必要があります。
アメリカは太平洋と大西洋という2つの大洋に囲まれているため、他国に攻め込むのが地理的に難しい状態です。実際、第二次世界大戦後の戦争での勝率は約6割です。このため、中国やロシアのような大国は、アメリカから直接攻められる心配をそれほど深刻に考える必要がなく、結果として「対米包囲網」を作る切迫した理由がないのです。
特に、隣接する国同士の関係においては、地理的な近さゆえに互いの軍事力の増強が直接的な脅威として認識されやすくなります。
ここで国家をより身近な隣人との関係になぞらえて考えてみましょう。
あなたと隣人がお互いに相手よりも強くなろうとして、競争が発生する状況を想像してください。あなたと隣人は共に、相手が武器を増強することを警戒し、自らを守るために強くなろうとします。
ここで大事なのは、あなたと隣人のどちらも、相手を攻撃するつもりはないことです。あくまで両者は自分を守りたいだけであって、相手を攻撃しようとはしていません。それでもお互いに「攻撃されるかもしれない」という不安を元に、武器を強化せざるを得ません。
この状況を「安全保障のジレンマ」といいます。これは、ある国が自国の安全を高めることを目的として軍備増強をすると、不安を感じた別の国が同様に軍備増強をする結果、双方に攻撃をする意図がないにもかかわらず、戦争の可能性が高まってしまう現象です。
国家は本来、自らを守ることにしか関心がありません。戦争を起こす国が決まって「これは防衛戦争である」と宣言するのも、その国は本当に自国の防衛にしか関心がないからです。
どんな国でも、隣の国が急速に軍備拡大をすれば多かれ少なかれ恐れるものです。今日の中国と日本の関係は、この典型例です。中国は自らを守るために軍拡を行っているはずですが、日本は「中国に攻撃されるかもしれない」と考え、防衛力を強化しています。
ただし、安全保障のジレンマには「起きやすい場合」と「起きにくい場合」があります。つまり、規模的には同じ軍拡を行ったとしても、状況や性質によって、他国がそれを恐れる場合と恐れない場合があるのです。
これは、アメリカの世界における立ち位置を理解する上で重要です。なぜなら、ロシアや中国は安全保障のジレンマを他国と抱えやすい環境にいる一方、アメリカは最強の勢力を持つにもかかわらず、安全保障のジレンマを抱えにくい環境にいるからです。