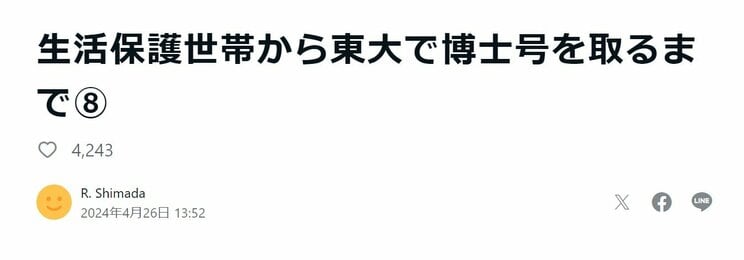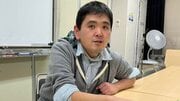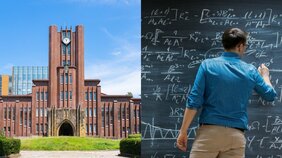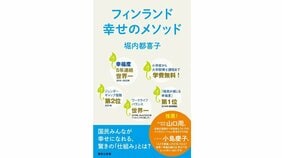社会への怒りを表明したワケ
無駄のない人だと思った。R.Shimada氏は余分な前置きを排して質問にまっすぐ返してくる。「noteによる発信でもっとも実現したかったことは?」と問いかけたときのことだった。
「貧困という境遇のためにチャレンジする機会さえ奪われている次世代を励ますこと、今なお放置されている格差という問題を指摘すること、が主な目的でした。
ただ、執筆していくうちに、こうした問題の当事者である私が”怒る役割”を担う意味もあることに気がつきました。現代社会において、怒りを表明することはさまざまなリスクが伴います。たとえば会社員であればなにかの拍子に失職するかもしれません。
しかし大学の研究職は、その職務をまっとうする限りにおいては、自らの思想信条を表明することが比較的守られていると考えます。また、数学者である私が政治について考えていることを発言するのも、政治学を専門とする人が言うよりは受け入れられやすいのではないかとも思いました」
R.Shimada氏のnoteはSNSを中心にさまざまな著名人や文化人によって拡散された。狙いは奏効したと言っていいだろう。これほどまでに訴えたかった思いの背景には当然、生活保護世帯で過ごした日々が深く関わる。
「私は高知県に生まれました。漁師だった父は家にお金を入れない人で、母はいつも困っていました。家計はおそらく母の仕事で支えられていたのだと思います。しかし母は精神的にやや不安定なところがある人で、幼少期、妹と私を並べて『どちらかが死ぬか選べ』と包丁を突きつけてくることもありました。
今になれば、母なりに切羽詰まっていたのだとわかります。母方の祖父が亡くなったのをきっかけに家族で祖父が住んでいた家に移り住みましたが、その頃にはもう父と母はあまり顔を合わせなくなっていたように思います。
また、記憶が定かではないものの、小学生のときの私はやや問題児寄りだったのでしょう。担任の先生に髪の毛を鷲掴みにされて、廊下の端から端まで引きずられるほど怒らせたりもしていました。母や教師など、大人を怒らせてしまって、毎日泣いてばかりいた記憶があります」
中学生になると、R.Shimada氏は勉強の真髄に触れることになる。だが当時はまだ、神童の片鱗は見えない。
「友人に誘われて訪れた地元の小さな個人塾での一幕は忘れられません。当時の私は、be動詞について先生が説明しているとき、『A動詞やC動詞もあるのでしょうか?』と真剣に聞いたほど、勉強はできませんでした」