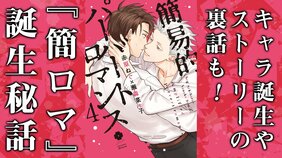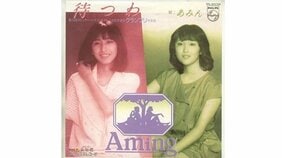早朝から夕刻までは舞台を勤め、夜は男色の相手をする
といっても、若衆歌舞伎の時に役者が性を売っていなかったわけではなく、武井氏によれば、むしろ若衆歌舞伎のほうが「男色を売りもの」にしており、「野郎歌舞伎以後、『容色』から『技芸』へと、芸の重点が移っていく。売色のためその美しい容姿を舞踊によって展観するのが、若衆歌舞伎までの舞台の大きな意味であった」(武井氏前掲論文)と言います。
しかしだからといって役者の売笑はなくならず、夜の仕事としてきっちりカネを取るというふうに、商業的かつシステマチックになったということなのでしょう。
「少なくとも元禄期までの歌舞伎界においては、若女方・若衆方など、若くて美貌の歌舞伎若衆は、早朝から夕刻までは舞台を勤め、夜は茶屋で客の求めに応じて男色の相手をする、というのがしきたりであった」(暉峻康隆 『新編日本古典文学全集 井原西鶴集 二』解説)
承応年間以後、元禄年間、少なくとも一六五二年から一七〇四年までのあいだ、歌舞伎役者は夜の勤めをしていたわけです。
もちろん「命乞ひは三津寺の八幡」の言うように、承応年間以前にも若衆がゆるい感じで客と遊ぶことはあった上(そもそも風紀を乱すというので若衆歌舞伎が禁じられたくらいなので)、元禄以後も個々に客の求めに応じてはいたでしょうから、実際には役者買いというのはもっと長い期間行なわれていたわけです。

異なる性を演じる「境のゆるい中で」感じるエロス
先に私は、「性や年齢を超えて変身する、演じるという能の特性は、性や年齢の境を薄くして、男同士、女同士の性的関係をより結びやすく導く働きがあるように思います。江戸時代の歌舞伎役者が、芝居のあとで男にも女にも性を買われていたのも、男をも女をも演じ得る存在だからこそ、どんな性にも応え得る存在に見えていたのではないか」と書きました。
歌舞伎はもともと女が男を演じ、同時に男も女を演じ……という性の境のゆるい中で、エロスが醸成され、権力者からは「風紀を乱す」としてたびたび禁令が出されてきました。
そんな中、役者に近づきたい、性的関係を結びたい、その時間や性を買いたいという欲求が、観客側に出てくるのは自然な成り行きです。
そして役者買いというと、私などは男が男を買う図が頭に浮かぶのですが、白倉敬彦によれば、男色が盛んだったとされる元禄期でも、それは「上方のことであって」、江戸では庶民のあいだに流行するには至っておらず、江戸で活躍していた鳥居清信が描いたのは奥女中たちの役者買いの風俗であり、それよりあとの奥村政信も似たようなものだったようで、「清信にしろ、政信にしろ、役者買いの主力を、女性と見ていたのではないか」と言います(『江戸の男色――上方・江戸の「売色風俗」の盛衰』)。