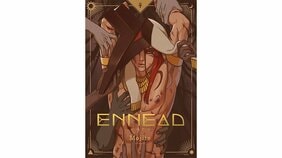自身の性で以て、ターゲットとなる相手(男)と結びつく
それで、自身の性で以て、ターゲットとなる相手(男)と結びつくことで、権力を広げていったと思うのです。
もっとも院政期以前に大貴族や中・下流貴族が男色で結びついていなかったかというと、そうでもなかったのではないか……と私は思っていて、というのも『源氏物語』には、主人公の源氏が受領の妻である空蟬に会えない寂しさから、空蟬の弟の小君と同衾するシーンがあって、その後、小君は源氏に取り立てられるのです(源氏が須磨謹慎の折、小君は距離を置いたため、帰京後の源氏は小君につれなくなります)。
こうしたことは現実にもあったのではないか。ただ、あくまで政治の本流は「女と男の性」で動いていたために、男色が政治を動かすというほどではなく、さして盛んでもなかったのではないか。それが私の考えです。
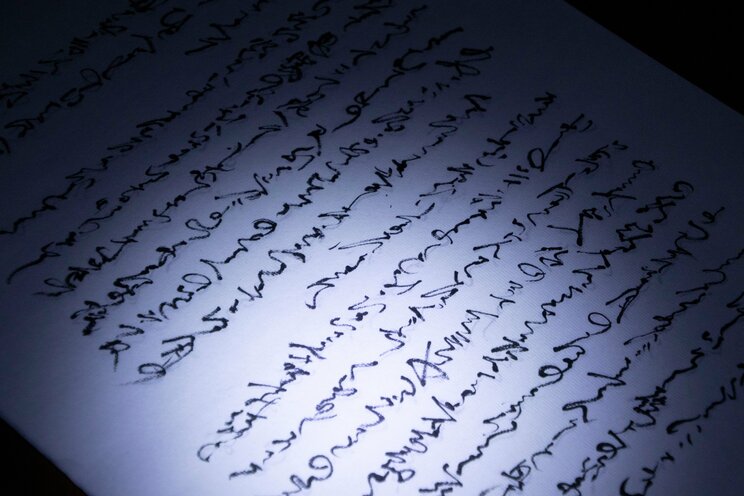
この時代の事件や戦いには必ずといっていいほど男色の愛憎が絡む
話を院政期の男色に戻すと、五味氏の指摘するように、この時代の事件や戦いには必ずといっていいほど男色の愛憎が絡んでいます。
保元元(一一五六)年、鳥羽院が崩御すると、崇徳上皇(院)方と後白河天皇方に分かれて保元の乱が勃発します。
その根っこには男色関係以前に、上流社会の親子関係のひずみがありました。
鳥羽院は保延五(一一三九)年、寵愛する美福門院得子腹の体仁親王(のちの近衛天皇)を東宮にした。そして、永治元(一一四一)年、待賢門院璋子腹の崇徳院(当時は天皇)が譲位する時の宣命に〝皇太子〟と書くべきところを〝皇太弟〟と書かせた。体仁は崇徳の異母弟ながら、崇徳の妻の養子になっていたのに、です。そのため、崇徳は〝コハイカニ〟(これはどういうことだ)と恨みを抱きます(『愚管抄』巻第四)。当時は天皇の父=上皇が執政する院政期。体仁が皇太弟では、崇徳は兄ということになって、天皇の父として院政を行なえなくなるからです。