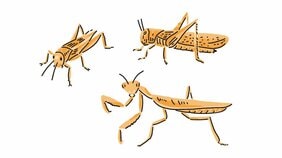いずれは食肉よりも昆虫食が身近に…?
「コオロギ食についてのご理解をどうか深めていただきたく、ご連絡いたしました」
コオロギ食論争が加熱するなか、このようなメールが集英社オンライン編集部に届いた。話を聞くべく記者が向かったのは東京都調布市にあるオフィスビル。2016年から食用コオロギを使ったお菓子やおつまみなどを開発している株式会社MNHだ。
取締役社長の小澤尚弘氏が語る。
「弊社はもともとお菓子メーカーではなく、地域貢献できるソーシャルビジネスモデルを作ろうとスタートした会社ですが、コオロギ食のお菓子の量産を始めたのは弊社がどこよりも早いと思います。これまで地域貢献として引きこもり経験者や福祉施設利用者を積極的に雇用してきており、その方たちの働く場所として始めたのがお菓子づくり工場でした。工場というよりは工房の雰囲気に近いかもしれませんね」
雇用を創出することを目的に始めたお菓子工場は、工場の流れる工程速度に人が合わせるのではなく、働く人たちの速度に工場が合わせていくのが運営方針だという。その方針があったからこそコオロギ食へ参入していった。
「当然ですが、このやり方は非効率的。そうなるとどの企業も手を出していなくて高付加価値、かつ大手が参入しづらい分野でやっていかざるを得ないんです。
万が一コオロギと関係ないところで事故が起きたとしてもコオロギのせいだとなる可能性を想定すると大手は手が出しづらいのです。弊社としてはコオロギ食はタピオカなどの一時的なブームとは違って今後も世界で必要とされていく流れがあると感じています」(小沢氏、以下同)
世界的な人口増加や食糧問題という背景から、「コオロギ食」という分野は今後も伸びると小澤氏はみている。

「世界で色々な昆虫食がありますが、最も養殖されているもののひとつがコオロギ。今はまだ需要と供給のバランスが取れず、コストも高いのでコオロギ食は割高になっていますが、本来、生産効率はいいんです。
このまま食糧問題が進めば、今後、豚肉や牛肉の価格が高騰してコオロギの価格が安くなることもあり得る。現に豚肉や牛肉は今どんどん高くなっていますよね」