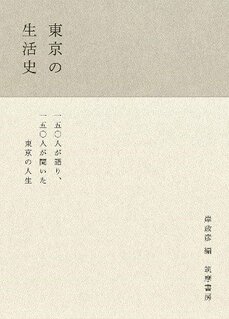原稿を「売れる」本にするために
――柴山さんはさまざまな本を手がけられていますが、企画はどのように着想されているのでしょうか?
あるていど経験を積んでいくとその分野の蓄積ができてくるので、駆け出しのころよりは楽になったはずなんですが、気づけば出がらしになっていて、企画にはいつも困っています。
僕は鈍いというか遅いというか、担当した本の冊数が本当に少ないタイプの編集だと思います。着想はこれという瞬間に出てくるものではなくて、自分の生活や環境とある程度関連するテーマで、ずっと引っかかっていることや考え続けていることを形にしていくイメージです。
――本づくりは編集者と著者の共同作業です。書き手に伴走する仕事として心がけていることはありますか?
著者のやりたいことを大切にして、それを実現するためにはどうすればいいかを考えること、でしょうか。「伴走する仕事」と言っていただけるのはうれしいですけど、はたしてできているのか、著者に伴走しているというのはちょっとおこがましい気がします。
著者の方がずっと考え続けてきた大切なことを、原稿にして預けていただいている感覚なんです。いただいた原稿をどうやったら多くの人に読まれる本のかたちにできるのか、それをうんうん考える。そういう意味では、僕は本が「売れる」ことを重視しているし、一般書として出す以上は読まれるものにしましょうというのはいろいろな著者に言っています。本は書いたら読まれないといけない。
――近年の柴山さんの担当書にはヒット作が多く、売れる本を作るという意味では成功を収められているのではないでしょうか?
そうは言っても、人文書のパイはどんどん小さくなっているし、なかなか厳しいものがあります。最近ではスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの『戦争は女の顔をしていない』のコミカライズがヒットしました。そういう、ひとつの本から展開していくものが何かできないかと考えているところです。
文芸やコミックと比べて部数が少なくても、社会的に大きなインパクトを与えることができるという一面が人文書にはあります。それはこのジャンルの強みではあるけれど、商業的にはやはり難しい。だからこそ、人文書一冊が単体として黒字になって、著者にもちゃんとお金が入り、またデザイナーや印刷所など本づくりを支える方たちにも還元できる本づくりを目指していきたいです。
前編はこちらから
撮影 関純一
取材・文 嵯峨景子