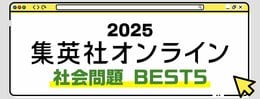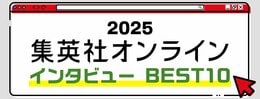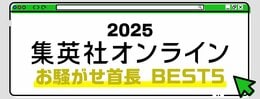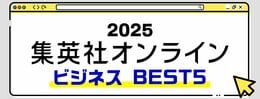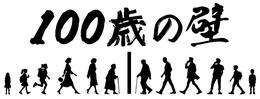偽装工作企業「光明影片公司」
実は、この中国映画界に「何等の基礎のない」「一資本」のその「資本」の出所と管理が東宝と上海軍報道局であり、それを偽装する映画会社が「光明影片公司」だった。つまり、この記事は戦時下上海で、リアルタイムで進行中の映画工作の所在を匂わせているのである。
これこそが当時、上海で軍と東宝が現地映画人を巻き込み行った極秘の「文化工作」であった。極秘の、と記すのはつくられた映画が日本軍と東宝による偽装中国映画で何よりその事実を隠さねばならなかったからである。東宝と軍は協働で一九三七年から三八年にかけて上海映画の観客の娯楽映画への欲求に応えた復興を演出するために『茶花女』以下四作の映画を「中国製」として製作する「文化工作」を行ったのである。
この事実は映画史の中では断片的に語られてはきた。それはしばしば、東宝の側の文化工作の中心にあった東宝映画株式会社第二製作部長・松崎啓次の個人プレーのように語られがちであったが、今では、中国大陸に映画市場と利権を拡大する東宝の思惑による「業務」であること、資金提供だけでなく契約の際の立会いなどに軍の後ろ盾があったことが明らかになっている。それは、事実を詳細に裏付ける同社の事務方である東宝映画株式会社総務課長・市川綱二の事務記録「市川文書」の存在が確認されたからである。同文書には「光明影片公司」との契約書をはじめとし、フィルム代から上海での銭湯の代金、市川および松崎の上海滞在日数と給与、興業成績の報告などの金銭の詳細な動き、本社とやりとりされた文書の控えなど、この偽装中国映画製作が東宝の業務として行われた「文化工作」であったことが細部まで裏付けられる証拠として残されている。
国策に協力する民間企業
現在の東宝という映画会社のイメージからすると、民間の映画会社がそのような政治的工作を行ったとは信じ難いという人には、ひとまず東宝の営業用パンフレット『国策と映画』に示された映画活用の営業項目に「外交宣伝」「政治工作」などの文字の躍るさまからまず実感してほしい。同社の性格がうかがえるだろう。
市川綱二は東宝の職員であるとともに、上海にあっては支那派遣軍総司令部軍報道部の嘱託の身分でもあった。前章で見た外地のまんが家たちがしばしば新聞社などの所属として「文化工作」に従事したのと同様である。
ちなみに市川綱二は先に名の出た市川彩とは別人である。コロンビア大学で映画学を学び、帰国後、外資系映画会社を経て東宝の前身であるP.C.Lに入社する。映画史には録音技師としていくつかの作品にクレジットされるが、P.C.L、東宝本社、東宝が関与した南満洲鉄道映画・芥川光蔵の記録映画製作、東宝映画技術研究所、航空教育資料映画製作と東宝が戦時下に行った「文化工作」の事務方として一貫して生きる。東宝は日本映画においてアメリカナイズされた技術や製作体制を積極的に取り入れてきたが、プロキノ(プロレタリア映画運動)など左派の映画人の受け皿であった文化映画、記録映画にあっては、コロンビア大で映画学を学んだというキャリアはいささか特異であった。
内部文書で明かされる工作の内幕
いずれ市川綱二の詳細な評伝は書かねばならぬと思うが、その膨大な市川文書の中にはこの偽造映画工作に軍の関与があったことを証拠立てる文書がある。すなわち「東宝映画株式会社取締役 代理人」と表記される松崎啓次、「立会人」と表記のある支那派遣軍総司令部報道少佐・金子俊治が、中国側映画人・劉吶鷗(本名・劉燦波)と黄随初(本名・黄天始)と結んだ契約書の控えが含まれるのだ。彼らはこの偽装映画工作の中心的プレイヤーである。
この契約書には一本あたりの製作費の金額を東宝が七五〇〇元と定めて提供、四作を製作、日本・朝鮮・台湾、満洲・華北各地の配給権を持つことが定められている。市川彩の「大映画劇場チェーン」と対になる記述である。
これは「裏」の契約書で「表」の契約書もある。そちらには「一九三八年三月」とあるが日時の記載はなく、甲・劉吶鴎、乙・沈天蔭、丙・黄天始の三名が光明影片公司を設立、甲すなわち劉が当面費用を立て替えるとある。この「表」の契約書によって、東宝や日本軍、その資金の出所は隠されているのである。
この二通の契約書に加え、松崎が上海軍報道部に提出した一九三八年四月付「上申書」(「上申書」、特集「牧野守所蔵東宝上海偽装映画工作文書」「TOBIO Critiques」#4)では東宝が軍に補助金を申し入れていることが確認できる。そこではこの映画製作が「日本資本ノ投資ヲカモフラージュ」し、現地従業員に対しても「何処迄モ日本人ガヤルトイフコトヲ秘シ隠サネバナラナイ」とあからさまな偽装ぶりが内部文書とはいえ、堂々と語られる。
この「上申書」からは、一連の工作が一九三八年二月、松崎が陸軍省新聞班の依頼で上海に出張、その報告書を三軍報道部と陸軍省に提出し、それが発端であったことも確認できる。このように上海における松崎啓次により一九三八年二月頃に発案され、三九年二月まで松崎・市川が実行した『茶花女』をはじめとする偽装映画は、軍および国策映画会社・東宝が行った「文化工作」であり、松崎の行動は全て「公務」だったことが資料的に立証されるのである。