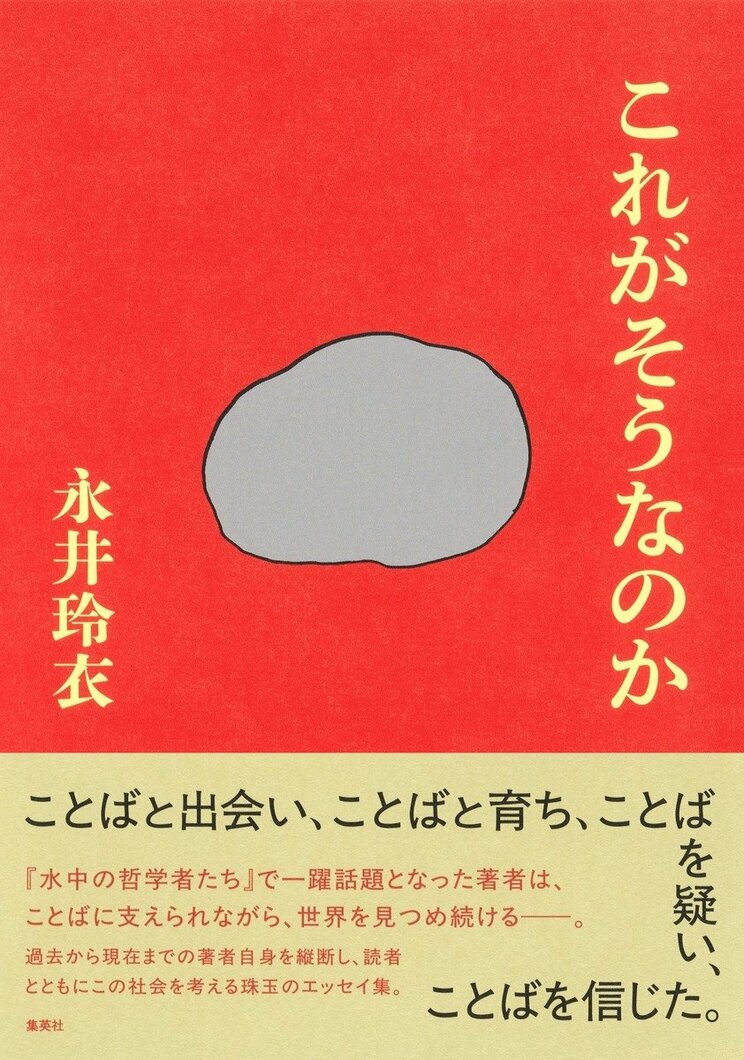災いから問いが始まり、それを言葉にする身振りに惹かれる
――『これがそうなのか』は、新語に隠された意味を問う第一部「問いはかくれている」、永井さんの言葉を育んだ読書体験を軸にした第二部「これがそうなのか」の二部構成になっています。頭木さんはどのように読まれたのでしょうか。
頭木 第一部は「推し」「あーね」など新語から話が始まりますが、そういった場合はたいてい、いま流行っているこの言葉にはこういう社会問題が反映されていて、いいことではないという批判に話が展開していくものです。でも永井さんは、「こんな言葉を使うなんて」と否定するのではなく、「なぜ使うんだろう」と話を深めていかれますね。そこが意外で、とても素敵だと思いました。
永井 そんなふうに読んでくださってありがたいです。わたしは全国いろいろなところに行って、人々ときき合い、考え合う場を作る対話の活動をしながら、そこできいたり考えたりしたことをエッセイ等に書いています。開く場所はさまざまで、学校や企業もあるのですが、最近はとりわけ強い体験をした人のところや地域に出向くことを大切にしています。
わたしは人が丹念に力を振り絞って探す言葉に惹かれながら、どんな言葉であってもそこに人の切実さがあると思っているんですね。対話をやればやるほど感じるのは、きいてみないとわからないということ。第一部は「推し」「あーね」など、コロナ禍やそれ以降に流行った新語を取り扱いましたが、その新語ひとつにさまざまな切実さやその人の人生の反映、断片みたいなものが潜んでいるんだろうなという思いがわいてきて、徐々に書き進めることができたように思います。
頭木 なぜその言葉を使うのかを考えていくと、切実さが表れてくる。そういう言葉は馬鹿にできないですよね。
永井 日常の経験で、人によっては「ちょっとしたこと」としてしまえるような断片にも、実はさまざまな切実さがある。そこに触れてしまうのが言葉や文学の力なのかなと思っています。
頭木 「あーね」の章に出てくる、「喫茶店のマスター的コミュニケーション」のお話も興味深かったです。カウンター席の女性の話をマスターがすごい返しで受け止める。ここも、普通ならくだらないと批判されるような話なのに、掘り下げる方向へと向かわれる。批判するほうへ行かないように意識しておられるのでしょうか。
永井 哲学っていいなと思うのは、どんなことでも馬鹿にしないところです。たとえば、目の前のコップをみんながコップだと言っているけれど、哲学は「本当にコップ?」「他の人にもコップに見えているんだろうか」「そもそもなぜコップと呼ばれているのか」と言い出すわけです。何を馬鹿なことを言っているんだと言わずに、探究しようとする。その身振りが面白い。何事でも世界の奥行きを確かめていけるのが哲学だと信じて、いろいろな対話の現場に足を運んでいます。するとそこで、きいてみなければわからない体験をたくさんするんですね。だから現場で教えられることは多いです。
――お二人はともに、人がふとしたときや止むに止まれず口にした言葉に胸打たれて、エッセイを書かれています。そういう言葉に惹かれるのはなぜなのでしょうか。
永井 昔から詩や文学に育てられてきて、対話の中で人々からぽろりと出てきてしまった詩のような言葉に出会うと、いつも心を動かされてきました。人は誰もが問いを持っていると思っていて、その問いの下に集って一緒に考えることが哲学ではないかという発想がわたしにはあるんです。では問いとは何かというと、ある種の災いのようなもの。恐らく痛みや苦労、悩み、違和感などと世間一般の呼び方で言われているようなものから問いは始まって、その言葉にならないものを人が何とか言葉にしようともがく。その身振りに出会い、惹かれてきました。対話で出会う人々の在り方と、その身振りが通底しているような気がします。なぜそれと出会うと心が震えるのかは、まだ自分でもわからないのですが、いまはその言葉を胸に置きながら深めていっているところかなと思っています。
頭木 『これがそうなのか』も含めて、永井さんの書かれるものはどれも詩みたいですよね。他のご著書をオーディオブックでも聴いたんですが、リフレインが心地よく、高まりが詩のようになっていくのが素敵だなと感じました。
永井 わー、嬉しいです。
頭木 ところで、僕は哲学対話を体験したことはないんですが、何かルールはあるのでしょうか。
永井 「約束」と呼んでいるのですが、よくきくことや、自分の言葉で話してみることですね。要は「カントはこう言っています」ということだけではなく、自分はこう思うというのを、拙くてもいいのでぜひ教えてほしいと伝えています。そして重要なのは「人それぞれでしょう」と諦めないこと。
頭木 第一部の最終章「問いをかくす言葉」でも、対話が終わってしまう言葉として「ひとそれぞれだから」「結局、承認欲求ですよね」「人間の本能じゃないですか」の三つを挙げておられます。確かにいろいろな意見が出ていても、これを言われちゃうと終わりですもんね。
永井 そうなんですよ。その三つは文学の言葉も閉ざしてしまう。じゃあ人それぞれの言葉というのは何であって、誰かの言葉をきくことによって生まれる言葉は何なのか、というふうに諦めないで対話をし、考えていく。そのしぶとさがあるといいなと思って、そういう約束にしています。
頭木 企業みたいな利益追求の場でもやっておられると知ってびっくりしました。
永井 哲学対話は人々の問いをきき合うところから始めます。企業で行うときは、よく「良いリーダーとは何か」とか、企業人としてのよそ行きの問いを立てられるんですが、皆さん本当にそれをやりたいですかと伺うと、やりたくないという答えが返ってくる。
頭木 え、そうなんですか(笑)。
永井 だから、皆さんがまだ言葉になっていないようなもやもやとしたものを問いの形にしてください、とお願いするんです。すると、出てくるのは本当に詩の言葉なんですね。「子どもの頃はあんなにドキドキしていたのに、大人になるとしなくなっちゃうのはなぜだろう」とか、「『趣味でスポーツをやっています』と言うと『ああ、いいですね』と返ってくるけれど、何が『いい』んだろう」というような。誰もが問いと同じように詩の言葉を持っているのに、なぜ語れなくなっているのか、というような問いにいつも襲われます。
頭木 面白いですね。『痛いところから〜』にも書いたんですが、僕は大学三年生で潰瘍性大腸炎という難病になって入院したとき、六人部屋だったんです。六人の年齢も職業も病気もそれぞれ違いましたが、苦しいものどうし、あれこれ対話することがよくありました。
永井 そうなりますよね。
頭木 ある患者さんが問診のときに、医者から「ここがズキズキするんですよね?」と聞かれると、逆らいたくなくて「そうです」と言ってしまう。後で「じつは“ズキズキ”じゃないんだけど」と他の五人に言うから、「それはちゃんと伝えないと。診断が違ってくるかもしれない」となって、次に医者から質問されたときになんて答えたらいいかを皆で相談したこともあります。でもその痛みを表現するのにふさわしい言葉が、既存の言葉にないんですよね。すると新しい言葉を作らなきゃいけなくなるから、だんだん詩人の会議みたいになってくる。中原中也の詩『サーカス』に出てくる「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」みたいな。突き詰めていくと、そういった文学的表現に自ずから到達してしまいます。
永井 なるほど。詩人の会議という表現が素敵です。
頭木 自分の症状を説明するような究極的に実用的なシーンで、意外にも詩が必要になってくるんですよね。