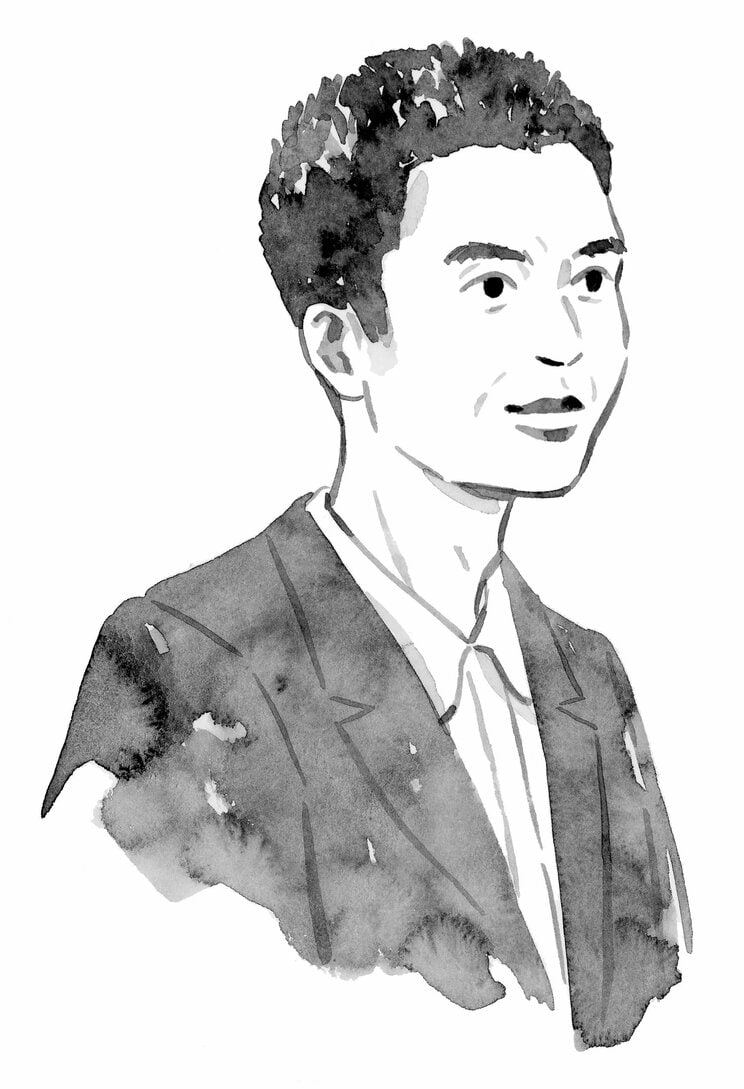自分の文章よりも、引用の一行を光らせる
――作品に詩や短歌、哲学者の言葉などをたくさん引用されているお二人ですが、その意図は何でしょうか。
頭木 僕の病気の話というのは、あくまで僕個人のことでしかなく、他人にはどうでもいいことですし、たとえ理解しようとしてくれても、同じ経験をしていないとわからないという壁があります。でも、そこに文学の言葉を置くと、文学というのは普遍性がありますから、私の体験と重なるところもあれば、他の人の体験と重なるところもあります。その重なり合いによって、いくらか伝わるし、わかってもらえるんです。
永井 不思議ですね。わたしはこれまで本にすごく助けられてきました。世の中にはストーリーを楽しむ本がたくさんある一方で、このたった一行に出会っただけで人生が変わってしまった、なぜかあの一行だけが忘れられない、そういう言葉の強度に揺り動かされるような読書をしてきたんです。
頭木 文学は追い詰められたときに救いになりますよね。病院の六人部屋でも、ほとんど本を読まなかった六人がいきなりドストエフスキーにはまったことがありました。
永井 対話の場で出会った人の語りや文学の言葉で、忘れたくない、なかったことにしたくない言葉があることを紹介したくて、文章を書いているところがあります。だから自分の文章よりも引用とか、みんなに知ってほしい言葉を優先して書くことが多いんです。頭木さんの文章も素敵で、特に引用が光っていますよね。
頭木 引用に一番光ってほしいですね。できれば、その一行の引用に出会ったことで、出典の本全体を読みたくなる、ということも起きてほしいです。
対話で偶然生まれた初めての言葉に出会えた喜び
――第二部は、永井さんの読書体験をなぞりながら、そこで出会った言葉を紐解いています。
永井 頭木さんの読書体験をお伺いしたいです。
頭木 僕が本を読むようになったのは二十歳で難病になってからで、それまではぜんぜん読んでいませんでした。永井さんは詩や文学に育てられてきたとのことですが、どういうふうだったんでしょう。僕にはそういう子ども時代の経験がなくて。
永井 わたしにはもう本しかなかったんです。川下りとか花火とか、みんなが幼少期にやるような経験が人より少なくて、代わりに本だけがある子どもだったから、ある意味孤独でした。世界が耐え難かったから本を読んでいたともいえます。最近よく思い出すのが、大変な状況にある子どもと一緒に過ごしている友達が言っていたことです。その子どもが友達に「あのね、僕の家の隣の室外機からロサンゼルスの音がするんだよ」と言うので、「ロサンゼルスの音ってどんな音?」と友達が聞いたら、「アメリカの音だよ」って。たったそれだけなんですが、すごくよくわかる。つまりロサンゼルスの音というのは、彼にとってここではないどこかの音であり、でも魔法の国とかではなくて室外機から聞こえる音だと夢想している。それがわたしには本のような感じがするんです。ここではないけれど、まったく別の場所ではない何かとしての言葉や本の世界。そういうものが自分には必要だったんだと思いますね。
頭木 僕は子どものころ、自然の豊かなところに暮らしていたせいか、本を読もうとしても、本の中の世界では風も吹いていない、虫もはっていない、鳥や獣も鳴いていないと、なんだか書いてないことばかりが気になって、入りこめませんでした。本には現実のごく一部しか描かれていなくて、現実のほうが豊かな気がして。でも病気になってから読んでみると、文学は、言葉にならない現実をどうにかして言葉にしようと頑張ってくれている場だと感じて、「文学がなかったら困る。なんて大切なんだろう」と初めてわかりました。
永井 現実の一部しか本には描かれていなかったというのは面白いですね。いまもそんなふうに感じられることはありますか?
頭木 いまは逆に、本の中にないものは気にならないです。そこで初めて何が言葉になっているか、どういう現実が初めてとらえられているか、ということがいちばん大事だと思っています。
永井 対話の中では、この瞬間に偶然言葉になっちゃったというところに出会うことが本当に多い。生まれたての言葉に出会えるんですよね。