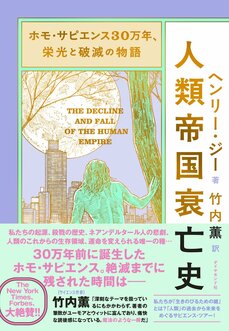多様性が失われたバナナ
現代の私たちが学ぶべき教訓が、ここにある。膨大な人口が少数の作物に依存し、しかも世界中の国々が互いに強く結びついている現在、食料の安定供給を維持するのは非常に難しい。
この文章を書いている今も、ロシアによる侵攻と広範な占領が続いているウクライナは、世界の小麦供給において重要な生産国のひとつなのだ。
この戦争によって小麦の生産と流通が妨げられ、世界中で食料価格が劇的に高騰する事態を招いている。
しかし、人々は教訓をそう簡単に学ばないものだ。農家が栽培している作物は種類が少ないうえに、その多くは集中的な栽培で高収量が見込める特定の品種に限られている。
たとえばバナナを見てみよう。この植物はおよそ7000年前に東南アジアで栽培化されたが、現在の世界の生産量の半分は「キャベンディッシュ」という単一の品種に依存している。さらに悪いことに、キャベンディッシュはすべてクローン――つまり遺伝的にまったく同じ個体であるため、さまざまな害虫や病気にとって格好の標的となっている。
この作物の生産が脅かされているのはそのためだ。バナナがなくても世界は回るかもしれない。だが、これはすべての作物にとっての重大な教訓であるのは間違いない。
狩猟採集民は常に飢えの瀬戸際にあるような生活を送っているが、通常は、農業の発明によって生じた深刻な栄養失調や健康問題には悩まされていない。農業がもたらしたのは、人口密度の上昇、感染症の流行、そして飢饉といった新たな負担だった。
また狩猟採集民は、農業の発明以後の人々に比べて、はるかに多様な食物に依存して生活している。農耕民は限られた種類のデンプン質の作物に頼るため、それらが不作になると飢饉のリスクが一気に高まるのだ。
迫りつつある飢饉のリスク
農業の恩恵は明らかだというのに、私の議論は悲観的すぎると感じるかもしれない。確かに、今なお何十億もの人々が安全な水やバランスのよい食事を十分にとれていない。
しかし、それは必ずしも作物の不作そのものが原因というよりも、貧弱な統治、腐敗した政治、戦争といった人間社会の欠陥によるところが大きい。
私たちは本当に数世紀前より「良く」なっているのだろうか?
国際通貨基金(IMF)によれば、食料不安は2018年以降、上昇傾向にある。これは、気候変動によって引き起こされる洪水や嵐、干ばつなどの「気候ショック」の頻発に加え、各地での紛争が拍車をかけているためだ。
ロシアによるウクライナの穀倉地帯への侵攻以前から、こうした傾向は見られていた。2023年時点で、48か国の約2億3800万人が「高度な食料不安」に直面しており、その数は2022年より10パーセントも増加していると、国際支援情報サイトReliefWebは報告している。
飢饉が、かつてない速さで私たちに迫ってきている。しかもそれは、非常に都合の悪い時期に起きている。というのも、人類の歴史の中でこれほど多くの人々が、これほど少ない作物にカロリー源を頼っていた時代はなかったからだ。
苦境に立たされているのは作物だけではない。遺伝的な多様性という資源を失いつつあるのは人間も同じなのだ。
#2に続く
文/ヘンリー・ジー 写真/Shutterstock