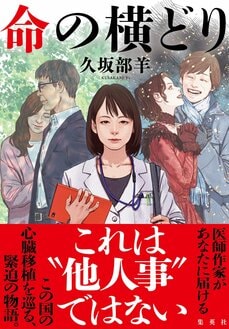「自分らしく生ききった」という納得感が大切
――メディアがサプリメントや健康食品のCMを盛んに流しているのも日本人にとって死が“得体の知れない恐怖”になったからでしょうか。
あのコマーシャルは罪深いですね。本当に効果があるのかも分かりませんし、仮にあったとしても、おまじない程度に過ぎません。
日本人がいかに命や健康を大切にしているか。以前、興味深い経験をしました。私が外務省の医務官としてオーストリアのウィーンに赴任した1990年代のはじめのことです。ウィーンの病院の事務長が「日本の人間ドックについて教えてほしい」と私を訪ねてきました。
「オーストリアでも人間ドックをはじめるのですか」と聞いた私に、彼は「いや、オーストリア人は人間ドックなんて受けない。東欧やオーストリア在住の日本人向けのコースだ」と答えました。オーストリア人は身体に異常を感じていなければ、検査は受けないそうです。
「日本人はいいお客さんだよ。異常がないのに、お金を払って検査を受けてくれるんだから」と彼は笑っていました。
――確かに、日本人は検査や健診が好きなイメージがあります。
日本人は「手遅れ」と言われるのをとても恐れます。医師の立場で言わせてもらうと、定期健診は、時間や費用の無駄になることも少なくありません。もちろんがんの早期発見で助かる人もいますが、早期に発見されたとしても亡くなる場合もあります。
逆に進行性のがんで身体に異常を感じてから検査を受けて助かる人もいます。なかには治らないけど死なないがんもあります。昔は、がんは治るか死ぬかのいずれかでしたが、いまは医療の進歩によって治らないけど死なない状態がつくれるようになりました。いわゆる「がんとの共存」です。
また健診には、検査被曝による発がんというリスクもあります。日本は検査被曝による発がんが世界中で断トツに高い国です。欧米はすべてのがん患者の1%前後が、検査被曝が原因です。一方で日本は3%。日本のがん患者の30人に1人は検査によってがんになった計算になります。
――海外の人と比べても、日本人が過剰に死を怖がり、命や健康を大切にするようになったのですね。それはなぜでしょうか?
太平洋戦争の反動だと思います。80年前の戦争で、日本人は命を粗末にし過ぎました。特攻隊だけではなく、〈生きて捕囚の辱めを受けず……〉と記された『戦陣訓』に従って、捕虜になれば生きることができたにもかかわらず死を選んだ兵士もたくさんいました。
その反省に立ち、現在の日本は、何よりも命を大切にする国になりました。もちろん、それ自体は素晴らしいことですが、医療の進歩もあり、死に接する機会が減った結果、死を意識することすらなくなってしまった。
――メディアも死を真正面から扱うよりも、病気や事故から奇跡的に助かる美談を盛んに取り上げます。
それも「死を遠ざけたい」という視聴者の意識を反映しているのかもしれません。誰だって死について考えるのは憂鬱です。それなら、死から目を背けて毎日を楽しんだ方が楽に生きていけますから。
私たちは生まれた瞬間から日々死に近づいています。どんなに医療が進歩したとしても死なない人はいません。いずれ必ず来る死に抗うのは、無駄な努力です。
命や健康を守ることに、「過剰な」時間や労力を使うなら、いまの人生を楽しんだ方がいい――それが、私の持論です。命のため、健康のために必要以上の労力と時間を使ってばかりいたら、病気になったときに一体何のための人生だったかと後悔しかねません。
死は避けられない。だとしたら命や健康よりも「人生」を大切にした方が、最期の日に「自分らしく生ききった」という納得感が得られるのではないでしょうか。
構成/山川徹