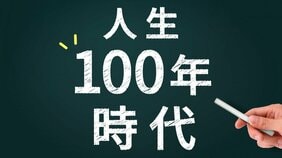退職金の使い道を金融機関に相談しない
公的年金が脆弱であるせいか、日本政府は、老後資金の不足金額が2000万円だと説き、株式投資や個人年金などに誘導している。確かに、これからの時代、現状と同じ程度の退職金や年金が支給される保証はない。
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、大卒で入社した人の平均退職給付額は、2003年の2499万円から2023年の1896万円へと、20年間で600万円以上も減少している。
同調査によると退職給付制度を設けない企業も増えており、2003三年に「退職給付制度なし」が13.3%だったのが、2023年には24.8%にまで増えている。
ということは、4社に1社が「退職給付制度なし」ということだ。このような時代の移り変わりも視野に入れたうえで、定年後のマネープランを立てていくべきだろう。
しかし、そのマネープランを作る際、自分の退職金の使い道を、金融機関に相談してはいけない。というのも、定年後の人たちの個別の人生とは関係なく、金融機関は様々な金融商品を押し付けてくるからだ。
それは往々にして、金融機関の利益を見込める商品であり、時にはリスクまで定年後の人たちに押し付けてくるものなのだ。
株式投資はAIが相手なので勝機なし
一方、現在、銀行に退職金を預けても、ほとんど増えない。そのため、これからは投資で増やすべきだ、と勧める人がいるのも確かだ。しかし下手に投資すると、大きな痛手を負い、老後破産を経験するという最悪のシナリオもある。
そうしたなか、素人が最も避けたいのは、FXや暗号資産への投資。これらは投資というよりも投機やギャンブルに近いと言える。
ギャンブルに嵌まると怖いのは、勝ち負けのコールのたびに脳内麻薬が分泌され、結果、投資依存症に陥ってしまうことだ。すると、損失を出したときにマイナスを取り戻そうとしてさらに深みに嵌まり、全財産を失うということもある。
では、株や投資信託はどうなのか?
長期的に利益を狙う堅実な投資方法であれば、ギャンブル的な要素は少なくなる。しかし、いずれにせよ手数料がかかってくる。そのため多少の利益が出たとしても、取り引きを繰り返すたびに手数料を取られ、利益は小さくなる。結局、いちばん儲かるのは、証券会社や銀行なのである。
マルクスの『資本論』を勉強してきた私からすると、投資によっておカネを増やすことに対しては抵抗がある。加えて、確率的に言っても、現在はAIによって「秒」で株銘柄の売買が行われているため、素人が勝てる可能性は低い。ファンドや機関投資家が勝つのだ。
実際、金融投資に関しては、素人と玄人の力の差、すなわち情報格差があまりに大きい。柔道でもボクシングでも体重別に階級がある。しかし投資の世界では、大人と子どもが同じ土俵で戦っている。
それでも金融投資をするなら、失敗して失ってもかまわないという余裕資金の範囲内でやることだ。
そのときの金額としては、まずは年収の5%が目途。たとえば年収500万円の人ならば、投資に回していいのは25万円まで。いわんや定年後の年金生活者は、さらに低い数字をリミットとすべきかもしれない。