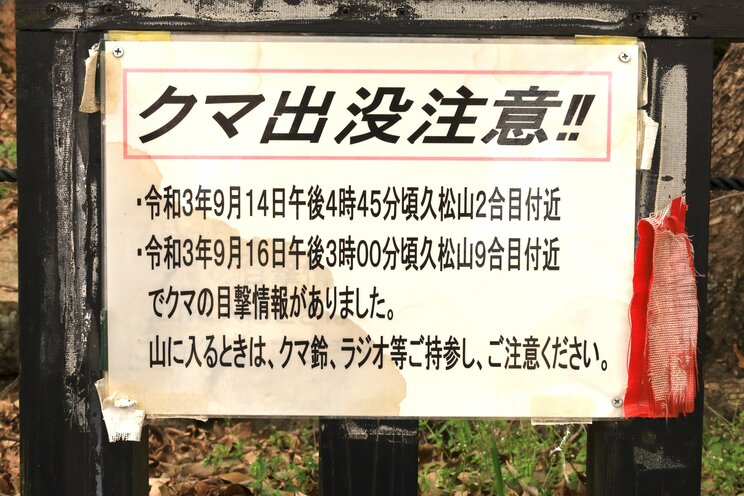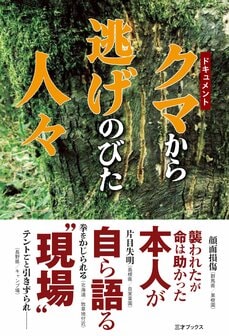人口減少と里山衰退が続く中、どう人とクマが棲み分けるか
クマと人間の軋轢――。今後は、どんな対策をすることが求められるのか。
環境省では、「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)」を策定し、「クマ類を保護するゾーン」「緩衝地帯とするゾーン」「人間活動を優先するゾーン」にわけてゾーンごとに適切に管理するゾーニング管理などを推し進めている。
「ゾーニング管理とは、つまりは“棲み分け”をするということ。クマとの関係を考えるとき、“共存”という言葉が使われることがあります。定義としては間違っていませんが、今はこの“棲み分け”という言葉が使われます。
簡単にいえば、人間が生活する場所とクマが生活する場所をゾーン分けして、その中で管理していくわけですが、クマが人間の生活する場所に出没した場合は、クマを捕獲・駆除しなくてはなりません。
クマと人間が共に暮らしていくことは難しい。クマの分布域はこれまでにないほど広がってしまっているので、その拡大を食い止めなくてはならない。かわいそうですが……。
もちろん、クマが50年先も、1000年先も、生き残っていくことが大前提です。ツキノワグマは外来種ではありません。人間よりもずっと以前、30~50万年前から日本列島で暮らしてきた動物です。クマにとって大事なコア生息地はきちんと残していかなければなりません」
だが、今後も加速すると見られる人口の減少、里山の衰退などにより、棲み分けは簡単なことではないと山﨑教授は語る。
「生き物の根本は、繁殖をして子孫を増やすこと。野生動物は陣地を増やすというのが本能です。今後もクマの生息数や分布域は拡大していく可能性が高いですが、人口の減少や里山の衰退がさらに進めば、それにブレーキをかけるのがもっと難しくなる」
狩猟者の減少と高齢化も課題になっている。あと10~20年経つと、担い手を育てるのも困難になるかもしれない。2025(令和7)年に改正鳥獣保護管理法が成立し、市街地にクマが出没した際、条件が整えば猟銃使用が可能になったが、制度ができても従事者がいないということになりかねないのだ。
「日本では、クマの駆除を主に猟友会が担ってきましたが、今後は海外の先進事例を参考に国や自治体がレンジャーなどの雇用や育成することを考えていくべきなのかもしれません」
クマに愛護的な人々とクマを排除したい人々の両極端な意見がネットを賑わせているが、「正しいクマの姿や保護管理の仕方を、ぜひ知ってほしい」というのが、山﨑教授の意見だ。
「研究者としてクマの普及啓発活動をしてきましたが、2023(令和5)年の大量出没のようなことが起きると、あっという間にイメージが悪くなり、クマはいなくてもいいという論調になってしまいます。
捕獲は、対策の一つ。それですべてが解決するわけではありません。たとえばゴミの処理を徹底するなど、クマを人間の生活空間に近づけさせない、執着させない取り組みも大切です。そうしたクマを呼び寄せない環境整備も並行して、改善していかなければなりません」
文/風来堂