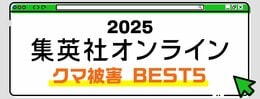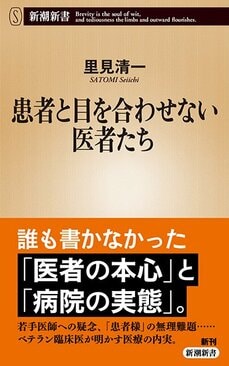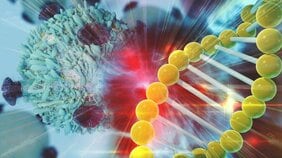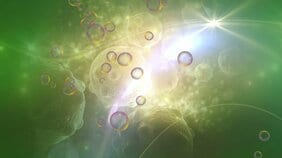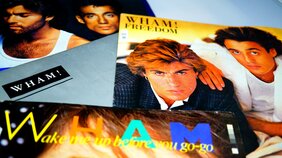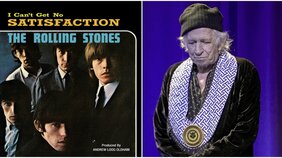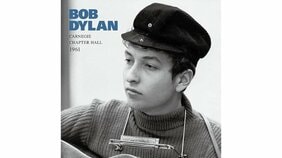かえって寿命を縮める可能性が高い検診も
特に問題になるのは高齢者の癌検診である。血液検査や検便ならまだしも、大腸内視鏡なんかになると危険性も伴う。現在、アメリカでは一般の人には大腸内視鏡による癌検診は10年ごとが推奨されていて、75歳以上の人はやらなくていいとなっている。オランダとアメリカの先生たちの研究では、65歳以上の人で検査間隔を短縮したり、また75歳以降も検診を継続したりすると、内視鏡検査による合併症のためかえって寿命を縮める可能性が高いと報告されている。
そうは言ってもやはり「心配だ」と検査を希望する高齢者は多い。オハイオ州のクリーブランド・クリニックの調査では、75歳以上で大腸内視鏡検診を受けた老人の多くは、もともと重大な基礎疾患をもってたりして、余命が10年以内と推定され、本来は検診の対象にならない(早い話が、癌を見つけて治療している場合ではなく、他の病気で先に死んでしまう)ような人たちだったらしい。入院を必要とする合併症は1%以上に起こり、当然年齢が上がるほど危険は高くなる。大腸癌発見率は0・2%に過ぎず、それも治療はしなかった例が多かったというから、何のための検診かわからない。
それなのに、検診をやった医者の方は、「大丈夫だった」人に対しても、「また検査にいらっしゃい」と言う。ニューハンプシャー州の研究者の調査によると、「きれいな大腸(クリーン・コロン)」もしくはそれに準じる内視鏡検査結果で、かつ余命が5年以内と推定されるような人でも、58・1%が検査後に将来の再検査の勧告を受けたのだそうだ。単なる習慣で口にするのかもしれないが、考えてみれば、「あなたには検診の意義は薄い」なんて時間をかけてデータを説明しても医者は一文も儲からない。また検査に来て、金を払ってくれた方がいい。
日本の医者はそこまで金儲けに走っていないと思いたいが、やっぱり高齢者にも必要以上に検査をしてしまう傾向はあるだろう。また「癌」は別格に考えられている。私の看護大学ゼミ生の一人は、糖尿病の合併症で全身ボロボロに近いが平然として生活態度も改めなかったくせに、「早期癌の疑い」と言われた途端に恐怖に戦(おのの)いた、という患者を経験したそうだ。客観的にみると癌で死ぬまで生きていられないはずなのに、やはり「癌は怖い」という固定観念が刷り込まれているのである。
まして、自分はまだ元気だと思っている年寄りに、「あんたは癌で死ぬほど寿命はないから、検診を受ける必要なんかない」と説得するのは難しい。最近は特に、「年齢で差別してはいけない」大原則がうるさく言われるから尚更である。だが40歳と80歳では平均余命が違うのは当たり前だろう。それに基づいて健康に関する行動を変えていくことまで「差別だ」なんて噛み付くのは、明らかな間違いである。
しかし相手が「癌は怖い、早期発見が大事、年齢は関係ない」と固定観念に囚われた頑迷な老人であれば、理屈を真正面に振りかざしても仕方がない。というわけで、ジョンズホプキンス大学の先生たちが、「どう言ったら、高齢者に検診をやめさせられるか」の検討をしてくれている。それによると、一番ウケがいいのは「健康のためには、もっと大切なことが他にあります」、次が「ガイドラインによると、やらなくていいそうですよ」だそうだ。悪い方のトップは「検査を受けても、その結果が役に立つまであなたのご寿命はもたないでしょう」だったという。本当のことをストレートに伝えるのはやはり反発されるらしい。
文/里見清一