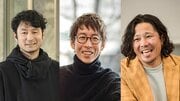早見 漫画の場合、そのあたりはいかがですか。たとえば主人公に対してどのような距離感を取っているのか、興味深いです。
クロマツ 僕の場合は客観視を大切にしています。『ドラフトキング』であれば、主人公の郷原というオッサンを遠巻きに見て、それを身近な感じに描いていくというか。
早見 確かに、郷原についてはどこか俯瞰したような描き方ではありますよね。それによって郷原が何を考えているのかが隠され、ミステリアスな雰囲気が生まれている気がします。
クロマツ でもその半面、僕自身が彼を好きになれていないと、読者も郷原を愛してくれないと思うので、その塩梅を大切にしています。
鈴木 やはりキャラクターとの距離感について、日々いろんなことを考えた上で答えを導き出しているんですね。
クロマツ そうですね。なので日々の中で出会った人たちも、僕にとっては重要なモチーフかもしれません。でもそもそもで言うと、僕は野球漫画を描こうと思っていたわけではなくて、もっとお洒落な作品で世に出たいと考えていたんですよ。全然ウケなくてダメでしたけど(笑)。
鈴木 ちょっと意外な気がします。
クロマツ それがある日、編集者から「野球漫画でやってみませんか。それもギャグで」と言われて方向転換したことが、『野球部に花束を』の連載につながりました。そこからはもう、野球漫画しか依頼が来なくなってしまって(笑)。
早見 僕は大学を三度留年して追い出されてくすぶっていた時に、たまたま知り合いの編集者から「小説を書け」と言ってもらったのが、『ひゃくはち』を書いたきっかけでした。自分の人生をひもといていった時に、一番商品になるのは高校時代の体験しかないと思って、それを剝き出しにして書き上げたんです。
鈴木 高校生活が商品になるというのは、その時点で確信があったんですか?
早見 明確にありました。単に手持ちのカードが他になかったというのもありますが、世の中にある野球の話というのは、弱小高に天才ピッチャーが入ってきて甲子園を目指す、みたいな物語ばかりだと感じていて。それに対して僕が体験したのは、甲子園に出るのが当たり前の強豪校の補欠だったので、これは売り物になると確信していました。
鈴木 その頃から逆張りの視点に目覚めていたんですね(笑)。
クロマツ 一読者としては、早見さんが高校時代にそういう体験をしてくれていてよかったですよ(笑)。
後編 鈴木忠平×早見和真×クロマツテツロウ “最高の野球本”を語るに続く
構成=友清 哲 撮影=樋口 涼
(集英社クオータリー コトバ 2025年春号より)