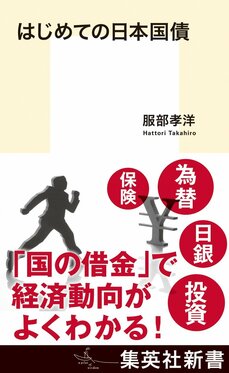金利をもっと上げた方がいい
服部 一般の個人投資家も数学的な知識をちゃんと学んで、資本市場に向き合った方がよいと思われますか。
松本 そう思いますね。株式投資や、ポートフォリオの設計にも使えますし。マネックスでは「マネックス・アクティビスト・ファンド」という投資信託を運用していて、私の今までの経験とネットワークを存分に活用しています。物言う投資家として投資先の企業にエンゲージメント(対話)を行うファンドで、自慢になりますが(笑)、運用成績がすごくいいんです。これは単にアクティビズム(投資先企業の経営への関与)やエンゲージメントの効果というだけではなくて、やっぱりポートフォリオのリスク管理をはじめとする金融工学的な、外からは見えにくい作業を色々やっていることの効果がすごく大きいんですよ。
服部 とはいえ一般的には債券や金利についてはハードルが高いという意見もあり、一方で、書店に行っても、金利や債券、国債の解説書は少ないと感じています。特に日本では金利が低く推移する期間が長くつづいているので話題も少なかったですよね。しかし、日銀が利上げを始めており、金利が世間的にも注目され始めている感覚はあり、これからだと思っています。
松本 金利については多くの人が誤解している部分もあると思います。民間の銀行が潰れないようにするために、日銀が低金利を長く続けたというようなことを、有識者扱いの人が言うわけですよ。でもそれは間違いで、銀行は貸し出しで稼ぐわけですから、低金利では銀行は儲かりません。日本で低金利が続いた 10~15年の間、米国は日本よりずっと金利は高かった。つまり、邦銀より米国の銀行のほうが儲かっていました。
この結果、米国の銀行は研究開発を活発に行うことができ、テクノロジーで邦銀に大差をつけました。低金利政策が邦銀を弱くしたんですよ。このことをわかっていない人がすごく多いのも、金利が理解されていないからです。
今だって本当は、個人的には金利をもっと上げた方がいいと思うんですよ。金利を上げることによって預金金利がついて、そのお金で消費が活性化する効果のほうが大きいと僕は思います。だけど、金利を上げると経済を止めちゃうという意見があまりにも多くて、そうすると「景気は気から」で、間違った意見が多くなると自己実現してしまう。だから、大本の理解を正していかないといけないと思いますね。
服部 金利や債券はやはり難しいといわれることが多いので、債券や金利の話を一般に広く理解してもらうためには、読者にとってわかりやすい書籍やレクチャーが必要だと思います。私の経験では、金融機関に働いている人にとっても、デュレーションやコンベクシティなどの概念は必ずしも簡単に理解できるものではないと感じています。松本会長のお話をうかがって、改めて私が頑張ってわかりやすい書籍を書いて、債券や金利についての理解を広げたいと思いました。
取材・構成/日野秀規 撮影/内藤サトル)
注
*1期間構造:債券の利回りと満期までの残存期間の関係。
*2信用(クレジット):投資家は債券の発行体の信用力に応じた金利を求めるので、一般的に信用が低いほど債券の利回りは高くなる。
*3 イールドカーブ:債券の利回りを縦軸、満期までの残存期間を横軸に取った曲線グラフで、金利の期間構造を表す。
*4デリバティブ:日本語では金融派生商品といい、金利や株価、為替などから派生する金融取引。
*5 資金運用部ショック:1998年12月に、大蔵省の資金運用部が国債の買い入れを停止すると市場参加者が予測したことをきっかけに日本国債が急落。10年債利回りが0.7%から2.4%台に急騰した。
*6 デュレーション:金利変動に対する、債券価格の変動しやすさを示す指標。デュレーションが大きい方が金利変動に応じて価格が大きく動く。債券投資のリスク指標として広く用いられる。