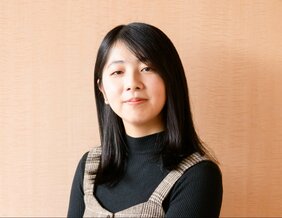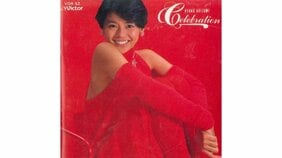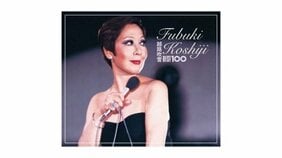「世界99」の世界設計
――全体の構成としては、主人公である如月空子 という女性の、四歳、一〇代の思春期、二〇代、三〇代、そして老年期へと至るクロニクルの形式で進みます。四章立てながら章の長さはランダムで、大まかに言えば第一章は空子の幼少期から若年期。第二章が大人になった空子と世界の分裂。第三章はボリュームがあって、「リセット」という出来事が起きたあとの世界というSF的な要素が展開されます。第四章はいわばエピローグ的な短さです。この構造も書きながら決まっていったのでしょうか。
村田 当初は二章で終わるという希望を抱いていたんです。世界の分裂を書きたかった第二章の最後に何か大きなことが起きて物語全体が終わるんじゃないかなと。
岸本 そういう大きな心づもりがあったんですね。
村田 ところが第三章が始まったら、あれ、この小説の本当の冒頭はここだったのかもという気がしてきて……。そのことを次の作品でお待たせしていた別の版元の編集者さんに話してみたら、おろおろされていました。自分では第三章ですっきり納得感のある出来事が書ければ終わると踏んでいたんですが、じっさい第三章に入ると時間も飛び、叙述のモードも変化し、どんどん予想外の方向に膨らみ、本当に終わらなくて大変でした。
岸本 それは小説に対して誠実な態度ですね。予定通りではなく、作品の要請に従って書くわけだから。
村田 そう言っていただけると、心が安らぎます。
岸本 まず感想として、これはすごいものを読んでしまったぞと、くらくら眩暈がしています。これまでも村田さんの作品を読むと、自分の足元の地面がひゅっとなくなって正常と異常の境目が曖昧になる感じを覚えていましたが、今回は質も量も熱もすごいのをぶっ込んできたなという気がします。私は小説を通じて、常識だと考えられているものや世界のルールが無効化されていく感覚を持つのはすごく好きなんです。おそらく自分も幼稚園の頃から世のルールが分からずに煮え湯を飲まされてきたタイプなので、ある種の解放感が得られる。今作だと「リセット」によってそれぞれが属していた世界が崩壊してみんなが大混乱するなか、空子が〈世界99へようこそ〉って言うじゃないですか。胸がすく思いでした。
村田 いつもですが今回も小説を書くとき、実験室の大きな水槽に自分の過去の体験を結晶にしたものやいろんなパターンの人間の似顔絵や現実のさまざまな要素をぶち込んで、その変化を実験者として冷静に書き留めたいという感覚でした。自分は入りこまず水槽と距離をとり、外側から化学反応を眺めるような。一方で毎月書いていると、無意識にその時々の自分の考えや体験も水槽に投げ込まれ、実験材料になってしまいます。私自身がばらばらに分かれて実験台にもなれば、観察者にもなるという分裂です。
私は幼少時に、ワープロで小説を書けば小説の神様が読んで選んで、自動的に本として出版してくれると考えていたんです。なかなか神様、選んでくれないなあと(笑)。その感覚は抜けず、今回も小説の神様とともに水槽の実験を宗教的な儀式のように見つめている心持ちでした。私に小説を教えてくださった宮原昭夫先生が、事前の設計図通りに書こうとしてもぜんぜん違う方向に小説が動き出すことを「神様が降りてくる」とおっしゃっていて、先生はもちろん比喩的に話されていたでしょうが、私は上から見る神の存在をもうすこし具体的に意識してしまっている気がします。
岸本 いまから十年以上前でしょうか、トークイベントをご一緒した際、人間を観察するときに「くもじい」の視点を持つとおっしゃったこと、覚えていらっしゃいますか。くもじいはテレビ東京の「空から日本を見てみよう」のキャラクターで、世界を俯瞰するんですよね。
村田 はい。くもじいの視点で、NHKの「ダーウィンが来た!」の人間の生態観察をやりたいと思っていて。ヒゲじいも一緒に、「人間の繁殖行動はこうなっておるんじゃな、おもしろい習性じゃ」みたいに。
岸本 今回の空子という語り手が、空っぽであるという特徴を持ち、他者をトレースして演じる女性であるという設定は、フラットな、何の情報も持たない者の視点で人間の生態を観察したら、人はすごく滑稽でグロテスクでもある生き物に見えてくるという発見につながっています。『コンビニ人間』もそうですが、村田さんの作品には、何者かをトレースする、擬態する主体というのがよく出てきます。空子はその最たるもので、空っぽという自己認識ゆえに、周囲の人間を観察して真似て生きているんですね。「人間ロボット」や「人格をダウンロード」という強い言葉で表されてはいますが、その場その場にふさわしいちょうどいい人格をだんだん学習して作っていくという意味では、空子だけではなくて自分だって、誰だってそうじゃないかという気がします。人間がこれまで知っていたのとは別のものに見えてくるという感覚と、自分も空子なんじゃないかと感じる感覚、両方が成立していると思いました。
――空子は、歴史のない新しい住宅造成地〈クリーン・タウン〉に育ち、コミュニティごとにキャラクターを使い分けます。父に愛される純真な「そらちゃん」、幼稚園時代はしっかり者の「空子お姉ちゃん」、小学四年生で出会った同級生の白藤さんの前では「キサちゃん」と、アイデンティティを〈分裂〉させる。バイト先では自衛のために男性っぽい「おっさん」になるのが意外で、切実でした。
村田 以前書いた「孵化」(『生命式』に収録)という短編は、大学やバイト先といったコミュニティごとにキャラを使い分けていた子が結婚することになり、結婚式というばらばらのコミュニティの人たちが一堂に会してしまう場面でどのキャラでいくか悩む話なのですが、これを長編にしたかったんです。自分自身、コミュニティに合わせて人格がすこしずつ違い、幼稚園と小学校のころの友達は私をおとなしくて人畜無害な人と思っているようで……。
岸本 たんに成長して変化したというより、使い分けということなんでしょうか。
村田 そこも難しくて、たとえばいま私がこのしゃべり方でしゃべっているのも、他者のトレースかもしれないんです。もうずいぶん前ですが素敵な編集者さんとお会いしたとき、世界に対する戸惑いとか違和感を話される口調が、すごくこちらに伝わってくる感じがして、自分の精神性もこれなら伝わるかもと思ったんです。そうしたら自分が緊張するお仕事の場面で、その話し方を試してしまったんです。だんだんその割合が増えて、いまでは自分のしゃべり方のベースになりました。でもコンビニで働く際の私はテキパキなめらかで、そっちだと生きづらそうな人に見えず気を使われないし、部屋も整理整頓されてそうと誤解されます。
岸本 それはすごくおもしろい。口調が似ちゃったというより、トレースの意識があるんでしょうか。
村田 やってみたらしっくりきたというか。でも先日その編集者さんにお会いしたら、ぜんぜんこんなしゃべり方じゃないんですよ。
岸本 オリジナルを超えて実装されてしまった(笑)。ご本人にはトレースしたことを話しました?
村田 いや、お伝えしたことがなくて。しゃべり方はあなたのトレースなんですと言ったら多分パニックになりますよね。でもそれが書きたかったんです。
――しかも空子はバリエーションが豊富です。『信仰』のなかの「書かなかった小説」という短編は、「私」が自分のクローンを四台買い、自分を夏子Aと呼んで他のBCDEと同列に扱う。特権的な「私」がメタ的にキャラを使い分けるというより、アイデンティティを分裂させますね。
村田 そうです。第一章の空子はその徹底です。
岸本 空子が周囲に合わせて「呼応」するあたりは、地獄の千本ノックというか、地獄見本市になっています。それも架空の世界の地獄ではなく、現実の世界で女性として生きていく上で誰もが日々経験する「あるある地獄」です。ここが本当に恐ろしい。同級生である白藤さんの兄の匠には〈女の賞味期限なんて14歳だ!〉と言われて「プリンセスちゃん」になったり、恋人の明人の前では「そーたん」として、つねに相手の求めに応じます。それがお母さんとの関係においては反転して、母親を「人間家電」として扱うんですよね。村田さんは以前から、自分の小説では「母親が隠れた第二の主人公になる」ことが多いとおっしゃっていますが、今作も意識されたんでしょうか。
村田 はい。そもそもデビューの短編「授乳」でも主人公と家庭教師の男の人との関係が主軸だったはずが、母親の存在が膨らみました。今作では母親を「無料の家政婦」とみなす空子を書いています。被虐だったのが加虐に反転するんです。この母と娘の関係は、自分で読み返しても食らっちゃうものなので、読者の皆さんにはご負担をおかけして申し訳ないです。
岸本 たしかに食らいました。
村田 仲のいい作家さんからは、ちょっと元気が出てからじゃないと読めない、ごめんと連絡がきました。空子と自分ではだいぶ性格が異なります。私自身は『ギンイロノウタ』の主人公に結構近いと感じていて、おどおどして人間に対して恐怖心があってうまく話せない。でも空子は異性に対してもそつなくやれてしまうタイプで、関係を持つからこそ地獄が広がるんです。
岸本 そうですね。痴漢の被害に遭っても〈もっとちゃんと痴漢されている人がいっぱいいるのに〉と恐縮したり、匠や、学校の教員から心無い言葉をぶつけられても反論しなかったりと、空子が男たちの価値観を内面化している節があってしんどいです。匠というキャラクターはどのように生まれたんでしょう。
村田 『コンビニ人間』に白羽さんという男性が出てきます。彼は当初、主人公の優しい夜勤の仲間としてちょっとしか出てこない予定でした。ただ自分が男の人だったらどういう日常を送るのかと考え始めたとき、キャラクターが膨らみすごく嫌な人間ができました。自分のなかで彼が忘れがたい存在としてあって、すこし別の角度で捉えたのが匠です。
匠も本当に認知が歪んでいて、女性に対する加害性が強いです。でも彼は自分が被害者であると感じています。男性同士のホモソーシャルな関係性からも疎外され、友達にも恵まれず、うまくいかないフラストレーションをためていたら、こういう人格になるのかもと想像します。自分にはまったく理解できないモンスターを描く方が楽かもしれませんが、モンスターになる以前の痛みを生々しく想像してしまうことがあって、だからこそ本当に嫌な人になってしまいました。
岸本 空子は恋愛を「肉体労働」ととらえていて、母親からの、〈素敵でお金のあるしっかりした人に見初められるような素敵な女の子にならないとね〉という価値観をどこか受容しています。結果、二〇歳にして二〇人目の恋人が明人です。
村田 匠よりもある意味では気持ち悪いです。自身がラロロリンキャリアだから被差別的な扱いを受けていると信じていて、その反発で空子への攻撃性に転じるんです。「なんでお前は自分が被害者みたいな顔してるんだよ? 俺は、男で、しかもラロロリン人なんだよ? 女のラロロリン人と違って、女を使って媚びてうまいことやるわけにもいかない。そんなこともわからないんだな!」と言ったりもします。
――この物語世界ではDNA鑑定が一般化していて、人種でも国籍でもなく「ラロロリンDNA」を持つ人間が差別の対象となっています。過去のないクリーン・タウン育ちの彼らもじわじわ差別意識を醸成させ、ラロロリン人だったレナの自死が悲劇的な記憶として空子のなかにはあります。
岸本 だからこそ、この男と結婚するのかという驚きがありました。
村田 私も明人は本当にぞっとする人で。第二章で明人と結婚していることになって、すごいつらかったです。私は幼少期から、そもそも自分の性愛を体に宿らせていいと思えなかったんです。それはあくまでも受動的なもので、自分の体は男性のための清潔な性欲処理のマシン、もうすこし強い言葉でいえば家畜のようなものとして考えていました。女の子の夢を描いた少女漫画ですら彼女たちは危険な目にあっていて、強姦されそうになったりするところでヒーローが助けに来てくれる。でもすでにそこそこ被害を受けていて。テレビのなかで描かれる女性像もそんな感じでした。
岸本 たしかにモノ化された女性の表象がそこらじゅうにあふれていた。
村田 だから山田詠美さんの小説を読んだときに、自分の意思で性行為をし、受動ではなく対等でそれが行われることにびっくりしたんです。でも二〇歳のころまで、嫌な目にあってもぼんやりやり過ごし、立ちすくんでいるという状況だったなと思い出します。
岸本 空子は「自分は頭が悪い」ということを再三、言います。そのことも関連しているんでしょうか?
村田 私自身、小説家としては希有なほど馬鹿かもしれないと自分のことを思っていて。だからこそ知識がなかったり、愚かで浅はかだったりする人にしか見えない光景を描きたいんです。理屈や理由が理解できれば改善も打開もできる。でもそうではないから世界を受け止めてしまう感覚を、自分は大事にしています。
岸本 それは馬鹿という言葉で呼ばなくていい気がします。村田さんだけの独自の視点なんだと思います。
――空子のキャラクターは不思議で、明人が性的衝動を抑えられないことも、母親の価値観が古臭いことも、自分ではシビアに見て把握できているんですよね。でもその場所から逃げようとしない。簡単に戦わないのがこの小説のユニークネスだと思います。
村田 この点は自分の記憶と経験がかなり投影されているかもしれません。私の母は五人きょうだいですが、女の子は四年制の大学に行けず、お見合い結婚でずっと子育てと家事をして生きてきました。母は心を殺しながら、思考を停止させながら生きてきたかもしれないと想像することがあり、空子も似ています。
岸本 私の母も、村田さんのお母様より年齢は上でしょうが、似たところがあります。勉強が好きだったのに大学に行かせてもらえなかった憤懣を抱えていた。だけど昭和四十年ぐらいのころって、世の母親にはそんな人が多かったのかもしれません。そして現代でも、この洗脳は続いている。空子の母は白いエプロンを空子にプレゼントし、いわば呪いを連鎖させます。
村田 一方で私は小説を書くことで呪いを解き、母や母の鬱屈を見捨てたのではないかとも思います。母を本当に孤独にしてしまった。そう考えると、この水槽の中には自分が体験したり感じてきた地獄が凝縮されているのかもしれないですね。
――本作では「ピョコルン」という動物の存在が重要になります。ピョコルンはパンダやアルパカやウサギなどの遺伝子が偶発的に組み合わさった可愛いルックスと愛嬌を持ち、人々を魅了します。如月家でも空子の父が独断的に飼うと決め、母親にお世話が押し付けられてきました。このピョコルンはペットとしての役目にとどまらず、人間の性欲の処理を担い、やがて生殖も担います。
岸本 母や女性の役割をアウトソーシングしたのがピョコルンです。でも、それをさらに助ける「母ルン」がいればいいのにということも言われるんですよね。空子の母親はピョコルンにも使われる存在で救いがない。搾取構造、差別構造が何重にもねじれています。
村田 解決を拒否する思考に固まる人っていると感じます。楽になること、救われることの否定というか。地獄状態に慣れて麻痺したまま暮らし、その外に出たらむしろ壊れてしまう人の不幸です。今作では母親がそうですね。