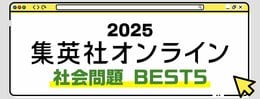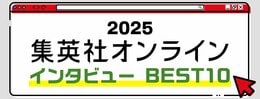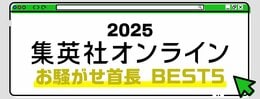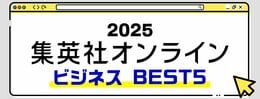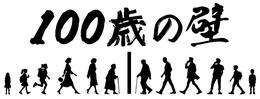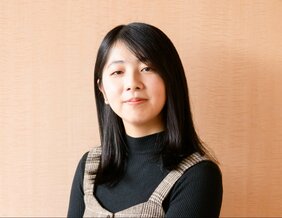○○小説ではなく実験報告
――このあといよいよ第三章と終章で、村田さんの独自のディストピア性が立ち上がります。岸本さんはどう読まれましたか?
岸本 ディストピアなのかどうかはいったん留保するとして、第三章は「リセット」が起きて一年後、「人間リサイクルシステム」ができあがっています。十パーセントの「恵まれた人」と八十パーセントの「クリーンな人」、そして残りが「かわいそうな人」です。そして第四章に至るとみんなが「記憶ワクチン」を接種し始め、個々の人格が均質化されるわけです。「エヴァンゲリオン」の人類補完計画をちょっと思い出しましたが、それは意識的だったんでしょうか。
村田 あまり意識してないんですけど、たまに言われます。私は旧劇の最後に、それこそ人類補完計画が発動されて綾波がめっちゃ大きくなるところ、あれが好きです。
岸本 表面的にはすごく穏やかで、みんな怒りもなく紛争も起きない平和な世界になっていく。ちょっとブローティガンの『西瓜糖の日々』の世界「アイデス」も連想しました。これはディストピアともユートピアとも判断しづらいですね。
村田 パラレルワールドは、ある人にとってはユートピアで、ある人にはディストピアでしかない。『殺人出産』もそうです。幸せそうではあるが気持ち悪いというような。
――『地球星人』のラストで展開された、主人公を含む三人の融合体も、個別性が失われて溶けていく同様のビジョンを持ちます。
村田 たしかに、実験が大体同じ結果になっていくのかもしれません。
岸本 海外のディストピア小説、例えばアトウッドの『侍女の物語』に顕著ですが、独裁政権によって女性が人権を失うさまを極端なシチュエーションで描き、リアルな現体制に対する批判や提言や予言を盛り込むわけです。オーウェルの『動物農場』も『1984年』も、こんなにひどいディストピアが予想されるから、こうならないために今どうするべきかといった視点から書かれている気がします。でも村田さんはそうではない気がします。
村田 そうですね、はい。
岸本 だから最初におっしゃった、水槽に入れてみたらこうなったというのは、読者にも指針になるかもしれません。いわゆる世界文学的な意味でのディストピア小説を目指しているというよりは、個別の実験結果に誠実で、そこが魅力的だなと思います。
――小説世界を実際の事件やエピソードの映し鏡にはしていない。読み解こうと思えばいくらでも現代文明批判として読めるんだけれども、それだけではない。むしろ汎用性を持つんですね。
岸本 せっかくなので小説と離れた質問もしてみたいのですが、このところ村田さんはレジデンシーや文学フェスに呼ばれて、頻繁に海外に行かれます。その国で自身の作品はいかに受容され、あるいは日本の女性作家がどのような存在と受け止められていると感じますか?
村田 国によって微妙に異なりますが、イタリアは日本文学ブームらしく本屋さんに「日本文学コーナー」があったりするんです。でも私の作品を翻訳してくださった日本文学研究者のジャンルーカ・コーチさんなどにお聞きすると、誤解も多い状況だそうで。というのも、日本文学イコール、猫とコーヒーと喫茶店が出てくるほっこりするお話だと考えられているらしいんです。世界で戦争が起きて殺伐とする現実にあって、そのつらさを忘れさせてくれるものだというような……。『殺人出産』がちょうど出版されたタイミングでイタリアに行ったら、なぜ村田さんは日本人作家でありながらこのような温かさのない作品を果敢に書くのかと問われ、むしろ日本文学のイメージがおかしいのではないかなと思いました。
岸本 ははは。川口俊和さんの『コーヒーが冷めないうちに』がベストセラーになったとは聞きます。
村田 表紙を似せた本まで作られていて、でもその作者はイタリアの人だったりして面白かったです。
岸本 先日アメリカのウェブ文芸誌を見ていたら、「お勧めの日本文学10選」として選ばれた本十冊すべての表紙に猫が描かれていた。びっくりしたんですが、今のお話を聞いて腑に落ちました。とすれば村田さんは異色すぎません? ほっこりとは程遠いから。
村田 “『コンビニ人間』は明確にADHDについての小説で、当事者が書いた事実だ”という文脈が用意されていることもあります。オランダの翻訳家さんに「自伝である」と書いてあるよと教えられたり。だからADHD当事者の読者の方から涙ながらに「あなたが書いてくれて楽になりました」と言われて困惑したこともあります。明確な目的やメッセージがあって書かれたわけではない、漠然とした実験結果の報告としての小説で申し訳ない……とは思います。
岸本 私はそういう作品を翻訳するのが好きですけれども。
村田 『コンビニ人間』は他にも、日本社会の同調圧力の中でもがき苦しんだ女性主人公が、ようやく現代になって活躍できた物語ですねと決め打ちで質問され、いやいやそんなことはないと丁寧に説明したのに、記事としてはそんな感じにまとまっちゃったこともありました。
岸本 日本についてほとんど知らないということもあって、いまもばりばりの封建社会で、女は書くことも許されないというイメージを持っている記者もいるんですよね。
村田 東アジアの抑圧されているフェミニストががんばってマイナー言語で発信しているという文脈ですね。
岸本 ただそれを聞いて、ちょっとドキッとしました。私だって、たとえばアフガニスタンやイランの作家たちの作品を読むのに、何らかの色眼鏡をかけていないとも限らない。日本女性が、ヨーロッパやアメリカの人にとって同じ生き物としては受け止められていないのかもと思うと、もやもやします。
村田 そういえばイギリスのマンチェスターの芸術祭に行ったとき、意外なことを言われました。リラックスした喋りで心を開いた姿を見せるのが場のマナーだそうなので、できるだけゆったりしていようと思っていて。でも自作の朗読も教科書を読むみたいにどこかかたくなっちゃう。着ているものも私だけがある程度フォーマルで。そうしたら仲よくなったパレスチナの作家さんに、沙耶香はすごく日本という感じがすると言われました。何か日本特有の精神性とかイメージが、やっぱりあるのかもしれません。
岸本 ああ、そういう違いはありますよね。得意の「トレース」能力は発揮できず?
村田 ハグはだんだん上手になってきたと、自分では自負しております(笑)。
岸本 いや、たいへん面白いお話です。
クリアに物事を見るために
岸本 もう少しだけ小説について気になっていることを伺いたいのですが、ラストの重要な展開にかかわるので踏み込みすぎないように話すと、空子はピョコルンにだけ性的関心を持ちます。一方で白藤さんは空子といっしょに暮らし、白藤さんのダウンロードを完了させてほしいと考えます。その中で名前の漢字であるというのを超えて、藤の花のイメージが濃厚に立ち上がってきますよね。ピョコルンとの性行為の際にも藤の花が関わってくる。この、藤のイメージは村田さんにとってどういう意味を持つのでしょう?
村田 久しぶりにほぼ空き家になっている千葉の実家に帰ったとき、ここに白藤さんと空子が同居しているというビジョンが浮かびました。その古い庭に、昔から藤が植わっているんです。藤の花には野趣というか、放っておくと家を殴るような暴力性があって、実際に有毒です。でも花自体は可憐ですよね。毒性の強いものですが、砂糖漬けにして食べることもできます。
岸本 白藤さんが空子に食べさせるシーンもありますね。
村田 はい、怖かったです。
岸本 しかも藤の花房はちょっと異様なかたちをしていて、ペニスっぽいといえばそうです。
村田 藤は獰猛で可憐で不思議な花ですが、人間はその藤の花にもかなわないのではないかと考えました。一方で現実世界を見渡すと、どんどん公園の木が伐採されたりしている。そんなこと起きるわけないと思っていたことが起きていて驚きます。
――そういったリアリズムベースのエモーショナルな感覚と、人間が脳の操作によって一体化したり個を手放したりする、そのSF的なファンタジー性が隣り合っているラストシーンは、やはり異様なんだけど美しいですね。透明な水槽のガラス越しにすべてが見えてしまう感覚は村田さんの独特のものです。
村田 現実は色々なものが詰まりすぎているので、もう少し物事を、事実よりクリアに見られるようにはしたかったです。
岸本 事実だけ書いていたのでは到達できない、その先に行くためにファンタジーやSFの枠組みはあるのだから、私はほんとうに三章以降がすごく好きでした。
村田 よかった、ありがとうございます。
岸本 今回はあまり話題に出ませんでしたが、「鼻の穴のホワイトニング」とか「権現堂さんの習字セラピー」とか、村田さんらしいブラックな笑いの要素も満載です。この作品が読者にどう受け入れられていくか楽しみですね。
村田 読んだ方々が具合悪くならないか、ちょっと心配です。
(2025.2.10 神保町にて)
「すばる」2025年5月号転載