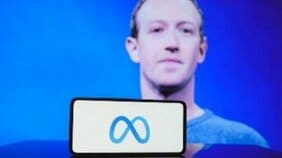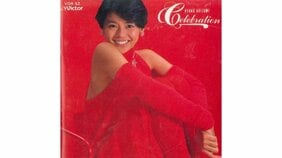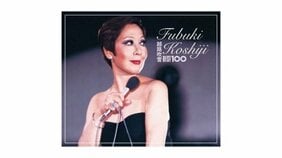ビジネス
会員限定記事
〈急増するリベンジ退職〉休日返上10連勤、充電器忘れ3時間叱責…上司のハラスメントの末に若手社員が取ったまさかの行動
業務量の急増や厳しいノルマ、ハラスメントなど職場でのネガティブな体験を引き金に、労働者が対抗措置として退職する…その名も「リベンジ退職」。近年、アメリカで急増しているというが、日本も他人事ではない。
なぜ彼らは“リベンジ”という形で退職を選択するのか。その背景には、正当な形で訴えても対応や改善の見通しがない会社の在り方に絶望した末の“最終手段”の意味合いが強く込められていた。
この記事は会員限定記事(無料) です
続きを読むには会員登録(集英社ID)が必要です。ご登録(無料) いただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。
次のページ
画像ギャラリー
関連記事
会員限定記事(無料)
-
-
松田聖子の声が大衆をとらえてやまない“特徴的な歌唱法”とは…「瞳はダイアモンド」のアレンジに隠された斬新な手法ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか #1
-
-
-
-