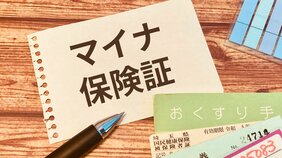年金制度の問題点と解決策
現在の年金制度には問題もある。ここでは二つの事例を紹介しよう。
一つめは、2016年に問題となった「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)だ。GPIFは、国民年金と厚生年金の年金積立金を運用する組織である。かつて問題とされた理由は、5兆円を超える運用損失を出したからだ。
もっとも、株式の運用には、上昇もあれば下落もある。民主党政権下では、経済不況により運用利回りが低くなったが、安倍政権が発足した後は回復した。2016年は、その利回りが一時的に下がっただけで、その後に株価は上昇して再び収支が好転した。
トータルでみれば、市場運用開始以降の2001年度から2023年度第2四半期までの収益率は年率プラス3.91%、累積収益額はプラス126兆6826億円(うち利子・配当収入は49兆2195億円)と着実に資産を積み上げており、運用資産額は219兆3177億円となっている。
とはいっても、GPIF自体は根本的な欠陥を抱えており、筆者としては不要な組織だと考えている。その欠陥とは、GPIFによって運用されている積立金の原資が、本来は存在しないはずの公的年金の積立金である点だ。公的年金は賦課方式なので、積立金があること自体がそもそもおかしい。
もし年金を積立方式にした場合、インフレによるお金の目減りに備えて、積立金を株式などで運用する必要がある。しかし、現在の公的年金は賦課方式で、物価スライドの仕組みを取り入れており、インフレヘッジをしているので問題はない。
百歩譲って、どうしても公的年金を市場で運用するのなら、株式ではなく、インフレ対策として「物価連動国債」での運用が適している。ただし、GPIFの運用が全体に占める割合は小さいため、問題が生じても年金制度が破綻する心配はほとんどない。
二つめの問題は「徴収漏れ」だが、これが最も厄介で、早い話が「脱税」だ。
そもそも、日本の年金は全国民が加入する「皆保険」制度であり、その意味では社会保険料は税金と同じ性格のものだ。
年金保険料は本来、全ての滞納者に対して強制徴収されるべきだが、これまでは年金保険料を納めていなくても、強制徴収されることはほとんどなかった。そのため、「年金保険料は払わなくていい」と思っている人も少なくないが、それは大きな間違いだ。
そもそも「未納」という表現が正しくない。「滞納」こそが正しい表現で、意図的に滞納しているのなら、それはもはや脱税だ。
保険原理からいえば、年金財政が厳しくなった際には、税の投入ではなく保険料の引き上げが適している。だから、まずは歳入庁を創設して、税と社会保険料を一体的に徴収し、社会保険料の取りっぱぐれを減らす必要がある。