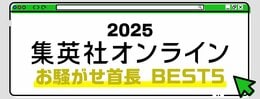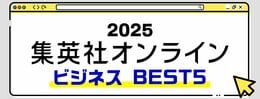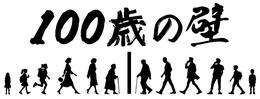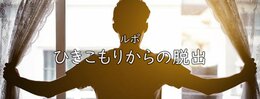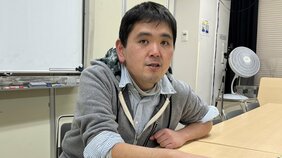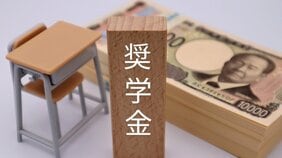「ゼロ・トレランス」と「スタンダード」
さらに、同団体が2022年3月に実施したインターネット調査「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査」によると、子どもの権利について「内容までよく知っている」教員は、約5人に1人(21.6%)のみ。「全く知らない」「名前だけ知っている」教員は、合わせて3割にのぼる(30.0%)ことが明らかになった。
ちなみに、若者の政治参加が世界で最も進んでいるスウェーデンでは、12歳(小学校6年生)時点で、88%の子どもが「子どもの権利条約」について知っているという。
この1994年の文部省の通知は、今も有効なため、改めて見直し、積極的に子どもの意見表明権を認め、学校や教職員に子どもの意見を尊重するよう求める必要がある。
こうして自主的な取り組みが広がった1990年代だが、2000年代に入ると、トップダウンで物事を決め、生徒の行動も縛る管理教育が強化され、子どもの意見尊重だけではなく、教員同士の話し合いも弱まった。
2000年、学校教育法が改正され、それまで実質的に意思決定機関となっていた職員会議の位置付けを見直し、職員会議は「校長の補助機関」となり、校長の権限が強化された。
さらにあたかも職員会議で議論するなと言うように、2006年には東京都教育委員会が職員会議で、「挙手」「採決」などの方法で教職員の意思を確認する運営を行ってはならないとする通知を都立学校長に出した。
2014年には文科省が東京都教育委員会と同様の内容の通知を出し、翌年にはそれが守られているかどうかの全国調査を実施して、守っていない学校には是正させた。こうして教員同士の合議制が失われ、生徒に対しても、言われたことを守る態度が求められるようになっていく。
2006年、教育基本法が改正され、そこでは、「国を愛する態度を養う」とともに「規律を重んずる」教育(第六条)が定められ、自分の頭で考えて、批判的に物事を見る子どもより、規律を重んじ遵守する子どもが「良い子」とされた。そして、翌年には文科省が「問題行動を起こす児童生徒」には毅然とした指導を行うよう通知し、「ゼロ・トレランス」と「スタンダード」が広がることとなった。
「ゼロ・トレランス」とは、1990年代にアメリカで広がった生徒指導で、学校側があらかじめ規律と懲戒規定を明示して、それに違反した生徒を例外なく処分するという方法である。トレランスとは、寛容さという意味で、無寛容に対応していくということである。
「スタンダード」は、「授業中は姿勢よく座る」「掃除は黙って行う」「廊下は静かに右側を歩く」といった、持ち物の規定や授業を受ける時の望ましい姿勢などを示したルールである。これが小学校から始まっており、細かく〝正しい〟行動が求められている。こうして、「期待通り」、「上」が決めたルールに自分を合わせる子どもが増えている。
写真/shutterstock