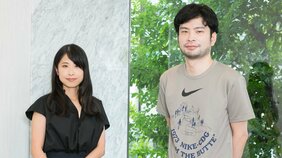小川哲さんの『地図と拳』(集英社刊)が、第13回山田風太郎賞に続き、第168回直木賞を受賞。受賞発表から一週間、各種取材でご多忙の中、お話を伺った。
*
担当編集者と一緒に受賞の報を受けたときには嬉しさよりも「ホッとした」ほうが大きかったという小川さんだが、やはり直木賞という賞の重さを日々実感しているという。
本作は、義和団事件から第二次世界大戦後までの満洲(中国東北部)のある都市で繰り広げられた知略と謀略を描いたものだが、そこには「戦争」という問題が大きく横たわっている。戦争を描くには事実を正確に押さえておくことと同時に、「戦争から時間が経てば経つほど、当事者として考えることがどんどん薄れてきてしまう。そういう遠くなってしまった戦争と、今生きている自分たちを当事者として結びつけることは重要で、昔の戦争が実は今とつながっているんだということを感じるために必要な回路を、フィクションは提供できると思っている」と。
ただその回路は日々更新されているので、その時代時代の作家がそれぞれの時代に合わせて戦争というものを問い直していくことが大切だとも。だから今回の作品でも「ぼく自身が今戦争を書くことのリアリティを追求しようということは、ずっと考えていた」という。
『地図と拳』という構えの非常に大きな作品に、三十代前半の今の時期に挑めたのは良かったし、作家として必要だったという。今後四十歳くらいまでは、「いろいろな書き方を試しつつ、ぼくができることとできないことを見定めていきたいと思っています」。
学生時代、岩波文庫の古典名作の千本ノックを受けたという小川さん。『地図と拳』にはイタロ・カルヴィーノの『見えない都市』に触発された挿話が挟まれているという。今後の作品で、どのような形で千本ノックの成果が結実するのか、大いに楽しみだ。