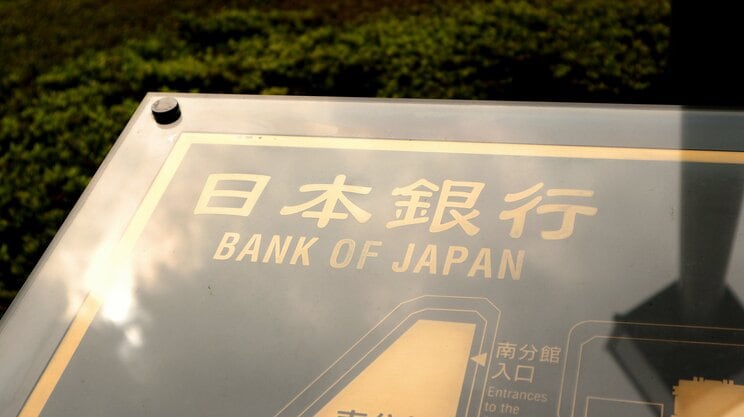* 2001年1月6日、中央省庁再編によって、それまでの大蔵省から財務省に名称変更になりました。本書では煩雑さを避けるため、基本的に「財務省」の名称で統一していますが、場合によっては「大蔵省」としている箇所もあります。
米国に操られる財務(大蔵)省、財務省に操られる日銀
田村 日銀は〝財務(大蔵)省日本橋本石町支店〟と呼ばれるような存在でした。公定歩合を決めるのは日銀の専管事項のはずなのに、実際は大蔵省銀行局の銀行課長が決めているような状況でした。
日銀は1998年10月施行の改正日銀法によって政策運営についての「独立」が保証されましたし、「大蔵省」も2001年1月に「財務省」に名称変更しましたが、財務省が日銀に対し強い影響力を持つ構図は1998年以前とさほど変わりません。
日銀総裁、副総裁、さらに政策審議委員は首相の指名によりますが、首相は財務省の意向を重視します。こういうかたちで財務省は内閣府を支配しているので、日銀に対して支配力を持つのです。
石橋 日銀が主体的に決めるのではなく、財務省に言われた通りに動いているだけなのが、日銀というわけですね。
田村 1985年9月に国際協調介入によるドル安・円高誘導を決めたプラザ合意があり、いきすぎたドル安・円高を是正するための各国の市場介入を決めたのが1987年2月のルーブル合意(*1)でした。
*1 1987年2月22日、パリのルーブル宮殿で開催された先進七ヶ国(日、米、英、独、仏、伊、カナダ)の財務大臣・中央銀行総裁会議で、1985年9月のプラザ合意によるドル安がいきすぎたため、歯止めをかけるための合意。
米国としてはドル安を止めたいが、金利は下げたい。しかし自分のところだけ下げると、他国との金利差が開いて、米国から資金が他国に流れていって、ドル安がさらに進んでしまいます。
そこで、当時のベーカー財務長官は、日欧、とくに日本と西ドイツに協調利下げを要請します。
日本で金利を動かすのは日銀の専管事項のはずですが、財務(大蔵)省を使えば日銀を簡単にコントロールできることを米側は知っていました。そこで、大蔵省のワシントン公使と示し合わせて、日銀にプレッシャーをかけるわけです。
日本は1986年前半、二度にわたって米利下げに協調して利下げし、さらに翌年2月のルーブル合意直後までに二度単独利下げしました。
それに対して西ドイツは、金融政策は自国のためにあるという原則を盾に、頑として応じません。
そして起きたのが、1987年10月19日のブラックマンデー(暗黒の月曜日)(*2)です。
*2 1987年10月19日の月曜日、ニューヨーク株式市場で起きた史上最大規模の大暴落。またたく間に世界中に波及した。
米国のダウ平均株価は1日で508ポイントも下落し、世界大恐慌の発端となった1929年10月24日のブラックサーズデー(暗黒の木曜日)を上回る株の大暴落を記録しました。

そのとき、私はワシントン駐在でとめどもなく下がるニューヨーク株価の模様をテレビ画面で見ていましたが、トレーダー、米政府関係者、エコノミストの誰もが茫然自失というありさまでした。
するとCNNのワシントン支社から電話があり、スタジオでの討論会に急遽、出演してくれとのことです。米国や欧州の記者も呼ばれましたが、真っ先に質問されるのは日本人記者の私で、「日本はどうするのか」というわけです。
私は、「ルーブル合意のG7の政策協調が崩れたためにニューヨーク市場が急激なトリプル安―株安、ドル安、債券安―に見舞われた。円高が進む日本が金融緩和を継続することで、市場安定に貢献できるはずだ」と答えました。
G7といっても、金融市場を動かすのは米・日・西ドイツの三ヶ国の政策です。その一角の西独連銀が動きそうにないし、米国はドル安を高進させる利下げには踏み切れません。アンカー(碇)役は日本しかなかったのです。
当時、米連邦準備制度理事会(FRB)議長―ボルカーに代わって就任したグリーンスパン―が9月に利上げしたばかりで、日銀も「この機を逃すな」とばかりに、利上げによる金融引き締めに動いていました。
しかし、ブラックマンデーを目の当たりにし、断念せざるを得なくなりました。もちろん、その背景には米財務省、FRBと気脈を通じている大蔵省の圧力もありました。
それで日本の公定歩合は0.25パーセントという低利のままで据え置かれることになります。
モノの生産が円高のために押さえつけられているなかでの超金融緩和ということで、余剰資金が株式や不動産市場に流れ込みます。
企業はエクイティファイナンス(*3)によって巨額の資金を株式や不動産投資に向けるので、株と地価が急騰する。いわゆるバブル経済となっていきます。
*3 時価発行増資などによる、株式市場での資金調達。エクイティとは「株主資本」のことで、発行会社からすると、返済期限の定めがない資金調達である。財務体質を強固にする効果が望める。