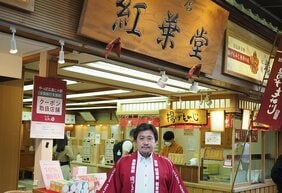美食家の間でミュシュランガイドより評価されているものとは?
ここ数年の外食文化をめぐる大きな流れは、インターネットの普及、そして国際化、情報共有のスピードの速さです。
まず、食べログやレッティがネットの情報収集や拡散機能を使った日本人による日本人のための食ガイドであるのに対し、世界レベルでネットを使って世界のレストランを位置づけようという試みができました。
「The Worldʼs 50 Best Restaurants(世界のベストレストラン50)」がそうです。
これは世界中のフードライター、シェフ、美食家ら1000人以上がベストレストランを50軒選ぶというシステムで、年に一度、毎年違った国でランキングの発表会が行われます。ネットでも発表されますが、活字版は出ません。2022年版では、トップはデンマークの「ゲラニウム」、2位はペルーの「セントラル」と、これまで欧米の一流店が並んだレストランガイドとはまったく違った様相を見せています。
しかし世界中の食を食べ歩く最先端の人々にとっては、最近ではミシュランよりもこちらのほうが評価されているのです。
しかも日本のレストランは、20位に「傳(でん)」が入賞、「フロリレージュ」が30位、大阪の「ラシーム」が41位、「ナリサワ」が45位と4軒がランクイン。世界のレストランの中で日本のそれが占める位置をみても、日本がいかに美食の国であるかがわかります。
※「世界のベストレストラン50」とは、世界中の食通や批評家からなる審査員によって選出される、世界最高峰のレストランランキング。