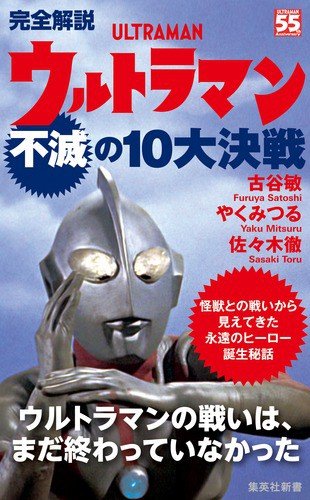角川春樹が夢見る最後のロマン
──死を意識することによって〝生きることへの飢餓感〟を沸き立たせるという話なのですが。
「ええ」
──それを踏まえ教えてほしいことがあるんです。角川さんは70年代前半に自ら進んで危険な中近東や東南アジアの紛争地帯を旅していますよね。当時の心境を『最後の角川春樹』(伊藤彰彦、毎日新聞出版)では、次のように語っています。
角川 旅に出るたび、死を覚悟していましたね。いま思うと、不慮の事故で死のうとしていたのかもしれません。死ぬかもしれない冒険に駆り立てられたのは、妹を死なせてしまった、もっと俺が彼女の悩みに気づいてやれば……という思いが強く後悔として残っていたからでしょう。それに、どれだけ成功しても認めてくれなかった父親との関係に疲れはてていたこともありました。
ーつまり、当時の角川さんにとって、危険地帯を突き進んでいく冒険の旅というのは、消極的な自殺だったのでは?
「そうですよ。これは共感も理解もされないと思うのですが、あの頃の私は漠然と死というすべてを無に還すものを受け入れてみたかったというか。だから、死ぬことなんか、まったく恐れもしていなかった。ただし、妹を自殺で失っていますから、私も自殺するわけにはいかないと思っていました。まあ、旅の途中で何かしらのハプニングやトラブルに巻き込まれて死ねればいいなと。そういう意味では、あなたがいま消極な自殺とおっしゃったけども、違います、積極的な自殺願望です」
──冒険の旅で死ぬのは、ロマンですか。
「ロマンじゃないです、アリバイですよ」
──それは卑怯なアリバイ作りじゃないですか。
「卑怯と思うかは、人それぞれの評価であって、私自身はそう感じていません。いまも言いましたように、妹を自殺で失っているから、自殺とわかるような死に方をしたくなかったんです。いや、わざわざ危ない場所に無防備で飛び込むようなことはしませんでしたよ。冒険の旅の結果として死ねればよいなと思っていて。そういう意味で、アリバイと言ったまで」
──わかりました。それで教えてほしいのは、死を身近に感じ、常に死を覚悟していた冒険の旅に出発しながらも、結果的に生き残れたのはやはり、〝生きることへの飢餓感〟がそうさせたのでしょうか。
「そうでしょうね。もしかしたら、無意識のうちに飢餓感より、生き抜くことへの渇望があったからかも。それと、私の生命力がやたらと強いせいもあったと思います(笑)」
──そういえば、『最後の角川春樹』でも、このように語っていますね。
角川 私にとっての冒険は、「現実」の束縛を振りほどいて〝野生〟を取りもどすための旅で、その旅を通じて「人間は生き抜くということ以上に価値あることはない」と気付くんです。正義とかモラルより、生き抜くということに人生の意味があると。
ーーその『最後の角川春樹』を読むたびに、角川さんの生命力の強さには驚かされます。獄中での〝絶望3大苦難セット〟でもわかるとおり、普通は絶望の苦難に耐えられないですよ。そのせいで生命力が弱り、死んじゃう人だっているんですから。
というか、角川さんは〝私の生命力がやたらと強いせい〟とおっしゃいますが、私からすれば、強さの他にプラスαがあると思っているんです。そのプラスαとは、弾力性。命を失いかねない苦難が押し寄せてきても、その都度、角川さんは生命力の光を失うことなく、逆にしなやかにボヨヨンと弾き飛ばしてしまう。
「私の生命力に、そんな弾力性があるのかわかりません」
──いや、あります。というのも……個人的な話をしてもよろしいですか。
「はい」
──2002年、私はあることで税務調査を受け、えげつない金額の修正申告をしなければいけなくなりました。一括で追徴金などを納付できず、購入したばかりの公団のマンションを税務署に担保として押さえられたんです。
悪いことは重なるもので、フリーライターとしての仕事がうまく回らなくなり、それでも己の運命に抗うようにがんばってみたのですが、事態は好転せず、呆然とする毎日でした。そして、次第に納付が滞り、マンションは競売に。その日の夜、マンションに帰ると、妻と娘たちの姿がありませんでした。私に愛想を尽かし、出ていったのです。
「うん」
──私はひとりになった部屋で〝心が折れる〟といったレベルではなく、胸の奥にある生命力が通った棒のようなものがボキンと真っ二つに折れてしまったような感覚に襲われました。それからは気力も消え失せ、死ぬことばかりを考えていたんです。
でも、人間というのはなかなか死ねず、年月を重ねていくうちに再び仕事も増え、今はこうやって角川さんの前に座っている。
「そんな経験をした私だから、繰り返しになりますが、お聞きします。私以上に自殺願望も含め、幾多の苦難に苛まれ、結果的に死んでもおかしくない状況ばかりだったのに命を落とさなかったのは、生命力が通った棒が私の硬直した棒とは違い、苦難に遭うたび、折れることなく、逆にしなやかにしなり、苦しみごとボヨヨンと弾き飛ばしていたからだと思います。では、どうやって、どうすれば生命力の棒をしなやかにしならせることができるのでしょう。
もう5、6年前のことになりますか。私は俳句を作りました。
にんげんの 生くる限りは 流さるる
私の人生は流されるまま、今に至っているという句です。結局、与えられた運命には抗うことはできませんから。振り返ってみれば、これまでに何度も死の淵を歩いてきたわけです。でも、奇跡的に生き残っている。それはあくまでも結果でしかありませんが、死に損なっているのは確かなんです。
だから、たぶん、そういう運命なのでしょうね。つまり、私の場合、角川春樹の運命という川に流されているだけなんだと思いますよ。父親の出版社に勤めることになったのもそう、映画界に進出したのもそう。思い返してみると、私にはこうしたい、こうなりたいという動機がないんです。
その時々で周囲の環境や思惑に流されるまま日々が紡がれ、結果的に父親の出版社の社長となり、角川映画を生み出すことができた。そういう意味で、あなたの問いに答えるなら、流されていくうちに自然と胸の奥にある生命力の棒がしなるようになったとしか言いようがない」
──目の前の苦難に立ち向かわず、抗うこともせず、ただ流されていけば、生命力の棒はしなるんですか。なんかカッコ悪いな。
「(笑)。十年前 、作家の唯川恵さんと江國香織さんで食事をしたんですよ。その時、唯川さんが、こう言ったんですね。〝春樹さんは、やすやすと常識を超えていく〟と。別に私は常識を超えているという意識もなく、ただ流されているだけなんですけども、あなたが表現した生命力の通った棒の弾力性と、彼女が指摘した〝やすやすと超えていく〟……まあ、ピョンと跳ね上がるみたいな感覚だと思うんですが、その2つの言葉が妙に重なりましたよね。そう考えると、私の場合、与えられた運命の川に流されているうちに棒がしなるようになったのかもしれません。ピョンと跳ね上がる弾力性を備えるようになったというか」
──昔から、例えば子供たちのヒーローだったり、困難や苦難を乗り越え、成功を収めた偉い人たちが励ますように言うじゃないですか。努力することによって自分の人生はいかにも変えられると。今の自分に決して満足せず、精進せよと。まるっきり角川さんと逆の主張を唱えているわけですが。
「努力しても無駄でしょ(笑)。いや、仕事や家庭間などのトラブル? そういうことに対しては常に前向きに対処しなければいけないとは思いますよ。仕事上の悩みや対人関係に苦しんでいても、感謝を忘れずに努力を続けていけば叶うこともあるでしょう。しかし、私が言う〝流されるままのほうがよい〟というのは、それこそ生き死にの重大な問題に直面した時のこと。
例えば、あなたでいえば税務調査、私でいうと収監。あなたがマンションを取り上げられ、ひとりになった時、何をどう抗っても事態は好転しなかった。私だってそうです。どんなに努力を重ねても、どんなに理不尽に耐えてみせても、刑期が軽くなるわけではなかった。
もちろん、祈りもしましたよ。手を合わせたりしましたけど、さきほども言いましたように、それで刑期の日数が短くなることはほとんどありませんでしたからね(笑)」
──流されているのに、無理に抗って足や手をバタバタさせていたら疲れ果て、ブクブクと沈んでしまう。そうではなく、なんとかして川面に顔を出し、静かに呼吸を繰り返すことが大事なのかもしれませんよね。
「私の場合、手や足をバタつかせることが無意味なのを本能的に察知していたのかもしれないです」
──流されるままにしているうちに、奇跡も起き、生き延びることもある。
「そういうことだと思います」
──やがてどこかの海にたどり着く、あるいは、それでそのまま死んでしまっても、それもまた人生と受け止める。今の世の中、生が善で、死が悪、だから何が何でも生き延びなければいけないんだ、と思いすぎる人が多いような気がするんですが。
「そういうことなのでしょうね。とにかく、流されているうちに私の棒は湿り気を帯び、しなるようになったのかもしれません。こんな境遇、絶対に跳ね返してやる、と無駄に突っ張っていたら、間違いなく棒は折れていたでしょう。それに抵抗せず、流されるままのほうが案外と順調にいくもんなんですよ。抗っても何も生み出せはしない」
──そうかもしれません。私も死ぬことさえ諦め、ただぼんやりと日々を流されるまま過ごしていたら、急に仕事が忙しくなりましたし。
「私が言った〝たかが刑務所、たかが胃がん〟は、流されているから言えたんです。しんどいことに対し、いちいち敏感に反応しても状況が変わるわけではない。それだったら〝たかが〟でやり過ごす」
──たかが新型コロナウイルス、たかが税務調査じゃねえか。
「そう、そういうこと。それにしても、80まで生き延びられるとは考えもしなかった。生きられても70過ぎまでだろう、と思っていました。流されたまま80まで生きてしまった」
──このまま流された先に、死ぬこと以外に何が待っているのでしょうね。
「この出版社、『角化春樹事務所』という個人名で『ハルキ文庫』なんていう自分の名前を冠した文庫もある。なぜ、そうしたかといえば、一代限りのつもりだったから。でも、息子と『日本のドン』を観終わった時に、〝お前、パパの後を継ぐか?〟と聞いたら、〝継ぎます〟と言ったんですよ。
これから息子が後を継げるまでに成長するかわかりませんし、その成長過程において私が何かしらのアドバイスを与えることもできないかもしれない。明日、死んでしまうかもしれない年齢ですしね。それでも明日死んでもいいという覚悟と同時に、おぼろげながら、そういう灯りがあるのも悪くないんじゃないかと思えてきて」
──父・角川源義氏との長きにわたる父と子の確執の歴史を考えると、感慨深いですよね。大河ドラマを観ているようだ。
「角川書店に入社した頃から盟友だった武富義夫(翻訳家)という男がいましてね。彼はいわゆる死後の世界、幽霊なんてものをまったく信用していかったし、嫌ってもいたんですよ。そんな彼がくも膜下出血で倒れ、逝ってしまったんです。彼を弔おうと友人たちと食事会を開いた時、外に出た際に呼びかけたら姿を現さなかったのに、ワインを飲んでる最中に出てきたんです」
──武富さんがっ!
「うん(笑)。服装も手に持っている鞄も、私のイメージのまま現れた。他の友人たちにはまったく見えていなかったんですが、私には彼の霊が見えたんです。あんなに嬉しかったことはなかった。その時、会話もね、できたんです。お前は幽霊なんか絶対にいないと言い張っていたけど、自分が幽霊になっているじゃないかって。やっと私が言っていたことが、彼に通じました(笑)。
だから私もね、息子が成人した頃には、この世にいないでしょうが、それでも幽霊にでもなって息子に必要なアドバイスができればいいなとは思っています(笑)。それが角川春樹の人生という濁流の先に浮かんでいる最後のロマンなのかもしれません」

撮影/五十嵐和博
関連書籍