それでは、手塚治虫の場合はどうでしょうか。手塚は16歳で大阪大空襲に出逢い、焼夷弾で無数の死体が黒焦げの山になる現場を経験しました。それは「ダンテの『地獄篇』のようなすさまじさ」だった、と手塚は自伝『ぼくはマンガ家』に書いています。その結果、手塚は生涯、戦争への絶対的批判者でありつづけました。
しかし、手塚は大阪大空襲という個人の体験から出発しながらも、水木とはまた異なった角度から、戦争をひき起こす社会的メカニズムを解明しようという普遍的な視点を失いませんでした。その集大成というべきマンガが、『アドルフに告ぐ』です。ここで手塚は、戦争をひき起こす根源的原因が、民族、国家、宗教それ自体にあること、そして、それらが架空の観念(共同幻想)にすぎないことを明らかにしました。
このマンガには大阪大空襲の場面も出てきますが、それがナチスのユダヤ人虐殺や、イスラエルとアラブ諸国の戦争と完全に地続きであることを、巧緻なドラマの展開で読者に納得させます。手塚の最後の大長編『アドルフに告ぐ』は、彼の精神的遺言というべき位置を占めているのです。
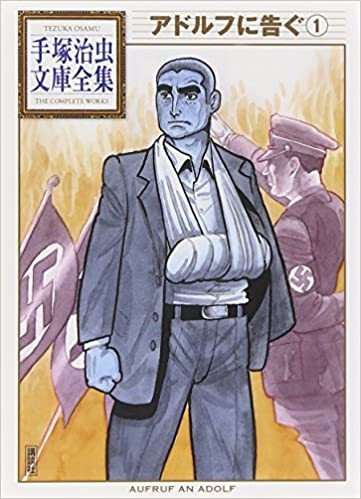
滝田ゆうのニヒリズムの視点
敗戦時に水木が成人、手塚が青年であったとすれば、滝田ゆうは13歳の少年でした。彼の代表作『寺島町奇譚』は、戦前・戦中の私娼の町・玉の井を少年の視点から描く連作集ですが、最終話「蛍の光」では、東京大空襲で玉の井が焼きはらわれて消滅する風景が描かれています。しかし、そこには、同じ大空襲を経験していても、手塚治虫とは違う、すべてを受動的に受けいれてしまうような感情のゼロ地点が刻まれているのです。そうでもしなければ、この苛酷きわまる戦争の現実に耐えることができなかったのでしょう。ここには、戦争を経験した多くの日本人に共通する、精神と感情の風景の底が描かれているように思われます。
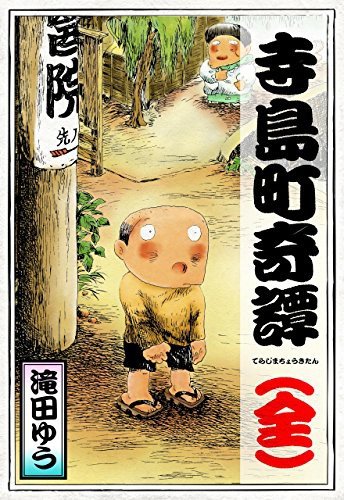
滝田が東洋的なニヒリズム(虚無主義)のうちに戦後を生き延びるすべを見ていたとすれば、終戦時に6歳の小学生として広島で被爆した中沢啓治は『はだしのゲン』で、かつての日本人の信じた価値体系への激烈な怒りを、戦後を生きぬくエネルギーの源泉にしています。
とはいえ、戦前は大日本帝国に服従し一体化しながら、戦後は易々とアメリカ流の民主主義と物質的繁栄に追随した大方の日本人からすれば、『はだしのゲン』は忘れたい傷痕をわざわざ掻きむしるようなマンガに見えることでしょう。何年か前にも『はだしのゲン』を子供たちの目から遠ざけようとする閲覧制限の運動が起きましたが、それは逆に、いまでも衰えない『はだしのゲン』の怒りの力を実証するものといえるでしょう。
ここまでは、戦争を経験した人々のマンガによる戦争の表現の諸相です。
























