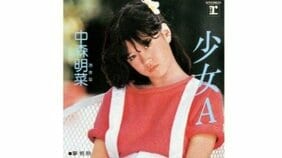産むを語る難しさ
中村 出産や母について語るのってすごく難しい。安易に母を名乗れば母性主義神話に加担させられてしまうし、シスターフッドという連帯の形に産む産まないの断絶を持ち込むなと批判されることもある。ポジション・トークのように聞こえてしまって誰かを傷つける恐れだってある。そういう状況のなかで、そもそも母という体験の凄まじさを主体的に語る言葉が社会の側に不足しているなと感じます。その点、本作で谷崎さんは、ご自身の身体性や内在性にもとづきながら、出産の異界性をダイレクトに言葉にして照らしてくださいましたよね。
谷崎 振り返ってみれば、産むことや母になることは、自分がこれまで無意識的にもテーマとしてきたことでした。以前書いた『藁の王』という小説の結末に、ずっと文章を書き続けてきた女の子が妊娠するというエピソードを置きました。そしたら、それを読んだ批評家や編集者の皆さんが口を揃えて「この子は書くことを捨てて、その代わりに出産を取ったんですね」とおっしゃった。私の力量不足だったとは思うんですけど、その読まれ方は意図とはまったく逆で、本当はその産むという経験をこそ、言葉にしてこちらに持ち帰りたいと彼女は望んでいたんです。まさに中村さんが『マザリング』で「哲学者たちは『他者』『語り得ぬもの』『物自体』……つねに理性や言語の果ての参照点を、さまざまな形で逆説的に指し示すが、捉えられないとされているXがこの私の身体の中にはある、確かにあるんだ、と言いたかった」と書かれていましたが、言葉が消失していくその地点をこそ言葉は見据えようとしてきたのではないでしょうか。デビュー作『舞い落ちる村』で「言葉のない国に、わたしは行く」という一文を結末としたのですが、そうやって私はずっと「向こう側」に行ってみたかったんですね。それを今作で、多少なりとも言葉にして見せることができていたらと思います。
中村 すごくよく見せてくださったと思います。班女や猿といった異界の生きものたちがたくさん登場したり、深い海や暗闇や檜の舞台が突然現れたりするのも、腹の内から覗く語りがたい世界をなんとか表現するためなのだろうなぁと納得感がありました。
谷崎 そう読んでいただけたのならうれしいです。生まれたときと死ぬときに、人間は完全に社会性を失った状態になりますよね。言語以前から始まり言語以前に戻るという、それがやっぱりあの世的という気がして、今回はその領域を母の目線からなんとか言葉にしてみました。ただ、先ほど母性主義神話という言葉をあげてくださいましたが、こうして実際に自分が母を経験したり書いたりしていると、あらためて母や母性というのは社会のなかでひどく美化され、利用され、搾取されていることに気づきます。母性ってもっと苛烈で激しいものなんじゃないんでしょうか。少なくとも私にとってはそうです。
中村 そう、結局母ってずっと利用されてきているんですよね。産めよ増やせよから始まって、戦争が起きれば今度は息子を戦力として差し出せと言われて。そのときに既存の母性主義、母概念に乗っかっていると、女性もまた内的にその圧力を強化してしまうことになる。いや、それは違うぞと。母が体験することは、そんな喜び勇んで豊かな包容力を持てるとか、盤石で超越的な存在になれるとかではなく、子どもとともにもっと脆弱で不安定でゆらゆらする状態に戻るということなんじゃないのか。存在論的不安のなかに置かれることなんじゃないかと言いたい。
谷崎 わかります。強く見えるのだとしたら、それは子どもを守ろうとしているだけでしょう。子どもの命を守るのにかけてだけは自他の命を顧みない獰猛さを覚えますし、子どもを奪われるのではという不安もひどくて、正気ではない感じでした。だからこそこれを、母性という花柄の包装紙みたいな言葉でくくって操ろうとするものには抗いたいです。
中村 母という既成の社会通念から全力で逃げ出したいですよね。ただ逃げ出しつつも、同時に犠牲を伴うケアの喜びのことは危険を承知で語っていきたいとも思うんです。むろん、母になれば自動的に子どもへの愛が育まれて、自らを犠牲にすることを厭わずいくらでも尽くせるようになるし、そうするのがいいのだというのは馬鹿げた神話です。でも一方で、子どもや弱い立場にある他者に対して自分を開いて尽くすことは実はすごく豊かで大切な営みだと思います。それは弱さへの感度をいつでも持ち続けるということともイコールです。身体が労働市場に適さないとか精神的にタフじゃない弱さって、たまたま今この時代だから弱いことにさせられているだけで、他の背景や時代だったら尊ばれるものだったかもしれない。そういう力に触れることは、世界を新しく切り開く契機にもなり得ると思っています。
谷崎 弱いもののなかにこそ困難を反転させる強い力があるんじゃないかということは私もずっと感じています。言葉にならなさに注目したいというのも同じ理由だろうなと。言語とは規範であり、強さなので。初めて書いた長編小説『囚われの島』では、俊徳丸伝説ならびに「弱法師」をモチーフにしたのですが、家を追い出され、何もかもを失い、病気で目も見えなくなった俊徳丸からこそ何かひっくり返しの力のようなものを感じられました。
中村 現代の個人主義は元気でいられる数十年のことしか見ていないけれども、私たちにはそもそも弱さが織り込まれている。誰だっておむつを穿いて始まって、最期はまたおむつを誰かに穿かせてもらって、みんな必ず誰かのお世話になって死ぬ。私たちは元より、ケアしケアされるべき存在なんです。先日、喫茶店に絵本の『あんぱんまん』の初版本が置いてあって、その後書きにやなせさんが、ほんとうの正義というものは捨身、献身の心なくしては行なえないから、かならず自分も傷つくのだ。だからあんぱんまんはやけこげたマントを着て自分を食べさせるのだ、と書かれていました。
谷崎 正義は傷つくものだという言葉に、含蓄がありますね。アンパンマン、アニメ版だとマントがやけているとかそういう設定まではわかりづらいのですけど、本当は深いアンチヒーローの物語なんですよね。私の夫がどういうわけかアンパンマンを毛嫌いしていた時期があって、それで育児に支障が生じていることをSNSで愚痴ったら、批評家の岡和田晃さんがアンパンマンの原型が初めて出てくる『十二の真珠』という短編集のことを教えてくれました。そこに描かれていたのは、強くもかっこよくもまったくない、ヒーローたちからのけ者にされるアンパンマンの姿で印象深かったです。
中村 自分を削って与えることで誰かが元気になって、削れた自分はまたパンを焼いてもらって、誰かに膨らましてもらってという救い合いの循環。それが大事で必要なんだというメッセージが素直に届いている。
谷崎 乳児期を抜け出るくらいの年齢の子どもが、異様なくらいアンパンマン大好きなのは、そうしたことを本能的に察知するからなのかもしれないですね。
中村 みんな潜在的には分かっているんだと思います。でも残念ながら、それを押し殺すような声が強い。弱い人のことは排除したり無視してしまい、利己的に振る舞えばいいという社会、とくに新自由主義のなかで経済原理が優位の世界においては加速度的にそうなっていると思います。だからやっぱり語らなきゃいけない。誰かにケアの役割を押し付けることは当然暴力だけれども、本来ケアの行為それ自体には喜びがあるはずだということを。簡単ではないけど、どうにかして悪用されない言葉を探しながら、他者に自己を開く喜びも伝えていけたら良いなと思います。
谷崎 同感です。母やケアというものにまとわりついているあれこれを一枚一枚ひっぺがしながら、この体験のつらさも素晴らしさも奇怪さも、すべてを言葉にしてみたいと願います。
私たちのリプロダクティブ・ヘルス
谷崎 私はいざ妊娠しようと決めるまでは、自分は産まないかもしれないという気持ちで生きる時間が長かったんです。結婚とちょうど同じタイミングでデビューが決まり、それからずっと必死に小説を書いていたので、自分のことに精一杯なまま気づけばどんどん時間が過ぎていきました。
中村 その一方で、そういえば自分は子どもを産みたいなって少女の頃から思っていたと回想する場面も出てきました。
谷崎 矛盾するようなのですが、あれもまた私の実体験に根差しています。実は幼い頃から、私の母の子育て、つまり私の育成は、あまり上手くいっていないんじゃないかと思っていた節があり、だから自分が子どもを産んで子育てをやり直すんだ、と思っていました。子どもって謎の全能感があるので、何もできないくせに、自分のほうがよくできると思いがちですよね。産まないかもと思っていた十数年の間はそんなふうに考えていたこと自体すっかり忘れていたんですが。
中村 子どもながらにして自分がもっと上手いこと産み育てたいとは面白い発想です。私がいま書いている集英社新書プラスの連載「なぜこの世界で子どもを持つのか 希望の行方」では反出生主義を支持する方のことをとりあげているのですが、彼らの話を聞いていると、親子関係に傷や呪いを抱えていて、自分が子どもを持ってその関係性を再生産してしまうのが怖いし重荷だと感じていらっしゃる。かつての谷崎さんとは逆の発想ですよね。
谷崎 今考えれば当時の気持ちは、お人形に優しくしてあげたいっていうのと変わりなくて無責任もいいところです。大人になってから熟慮のうえで産まないと決めた方々は、今この時代に子どもを生きさせることに対する責任を真剣に捉えておられるのだろうと思います。実際、これだけ気候が変動していたら、ひとつの種として絶滅に向かっていくのが自然なような気もするくらいで、その意味では産まない決断は頷けることにも思えます。
ただ勤め先の大学で若い方と接していると、もっと個人の実感としてのしんどさというか生きる意味の見出せなさを感じ取る瞬間があって。私自身生きるのが楽な人間では全然ないので、その感覚に共鳴を起こし、引きずられるところもあります。でも、私の場合はですが、赤ん坊が自分の方を見てうれしそうに笑ったときに「私生きてていいのかな」って初めて思えました。小さいものに初めて自分の生を全肯定してもらえた感覚があったんです。そう思うかどうかには個人差もあるだろうし、だから産んだ方がいいとか、そういうふうに繫げる気はまったくないのですが。
中村 わかります。子どもは笑って泣いて全身で私を求める。自分が必要とされているというその紐帯の強さは並々ならないです。そのことがある意味、呪っていた自分の生を反転させる可能性もあるよということは私も伝えたいです。あと同時に、子育てをしていると自分がかつてしてもらいたかったけれど果たされなかったことをしてあげたくなりますよね。もちろん、そうした方が子どもにとっていいだろうと思うからだけど、でもやっぱりそうすることで自分自身の子ども時代も癒えるという面がありますね。
谷崎 自分のために産んでいるんだなとは思います。それがいいのか悪いのかは置いておいて。一方で私は子どもというのが、抽象的な意味でですが、あらかじめ失われている存在のような感覚がどこかにあることも否めなくて。いま子どもがいて、その子はとても愛しいけれど、子どもがいて幸せ、とは言い切ってしまえないところがあります。それは先ほど中村さんがおっしゃった、子どもとの未分化な状態がなくなっていくということや、第一次、第二次反抗期への予感のようなものでもあるのかもしれないですけど、一方で子どもを産んだことの負い目、それこそある種の無責任さへの自責とも繫がります。だからこそ作中の「わたし」は班女に魅入られるのだろうし、班女との境目をなくしていく。産むことになった自分だけでなく、現実的に産まなかったかもしれない自分や、漠然と産みたいと思っていた幼い日の自分、あるいは子どもを失うことになるかもしれなかった自分が、そうした思いのなかで繫がっていく。様々な女たちと自分が交錯するような、そんな感覚を書けていればいいなと思います。
中村 本当にこの小説に書かれてあるのは女性のリプロダクティブ・ヘルスの全てでした。女の人にとって、産むか産まないかとか、私の人生のそばに子どもはいるんだろうか、いないんだろうかというのは、大人になったときだけじゃなく子どもの頃から折に触れて色んな場面で想像するし、させられる。もしかしたらそれは死ぬまで続く。そうやって延々と広がり重なるレイヤーがひっちゃかめっちゃかな宝箱のように開かれていて、ああこの混沌こそが産む産まないという身体のぎりぎりのリアリティーなんだと。そういう印象が読み進めるにつれてどんどん深まりました。女性の混沌とした身体をわし摑みにした本作を読めて、私自身さまざまな連想が広がりました。ありがとうございました。
谷崎 こちらこそ、ありがとうございました。
(2025.8.6 神保町にて)
「すばる」2025年10月号転載