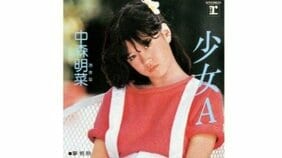原発とお水送りの力学
谷崎 若狭湾には産小屋のほかにも点在しているものがあって、それが原発なんです。原発銀座と名指される通り、たくさん建っていまして、見渡すと産小屋があり、原発があり、そしてそれらを抱く美しい海、というちょっとふしぎな構図になっているんですよね。
中村 ひとの命を産み出す現場である産小屋のとなりに、エネルギーを生み出す原発があるという。若狭湾における誕生の混み合いっぷりみたいなものを今作であらためて認識し、非常に面白く思いました。
原発については、3.11直後に中沢新一さんが『すばる』で興味深い議論(『日本の大転換』集英社新書)をされていたのを思い出します。簡単に言うと、人間をふくめ地球上の生きものたちはみんな、光合成にしろ火を起こすにせよ、太陽光という圧倒的なエネルギーを借りて生きてきた。とくべつ人間は石油の採掘にせよ火力発電にせよ、太陽光の時間的蓄積であったり堆積物の利用という、いずれも何らかの媒介を通して太陽エネルギーを使っていた。ところが原発というのは人が太陽の原理を盗み出して作った、何かの介在なくして太陽エネルギーを無媒介に生み出せる装置である。ゆえに原発銀座とはすなわち、小さな太陽がたくさんあることなのだ、と。出産もまた無媒介に生み出す行為で、あちら側のエネルギーに触れる経験である。原発は核分裂を起こし続けなければならないし、妊娠は絶えざる細胞分裂である。谷崎さんが掬い取られた産小屋と原発の重なりって、まさにこのことなんじゃないでしょうか。
谷崎 なるほど。すごく腑に落ちるし、小さな太陽がたくさんあるってイメージがすごいです。原発って、錬金術に似ているなあと感じます。私はシオニズムには反対ですが、ハシディズムにはずっと興味があって。錬金術師たちの、人間を作るというゴーレム神話にも興味があります。一種の禁じられた技というか、神の模倣でもあるけれど、それは確かに女性のリプロダクトの模倣でもある。
中村 あとはもう一つ、若狭の神宮寺で行われる、お水送りについても取り上げられていますよね。若狭井という井戸から神聖なお水を汲み上げて東大寺へ送る儀式で、千年以上前に東大寺の盧舎那仏を製作したときの水銀運搬の再現と書かれていますが、これ実際にご覧になられたんですよね?
谷崎 そうなんです。お水送りを見に行ったのは、やっぱり先述の「さかなの娘」を書いていたときでした。その取材で若狭にはすでに何度か行っていたんですが、あるとき朝起きて急に、お水送りというものを必ず見なくちゃという思いが生まれ、ばばっと見に行きました。ここには、そのときに感じたことを書き入れています。
中村 急に思い立って行かれたんですか、それはちょっと意外の感があります。もしかして谷崎さんは結構直感的な方なんでしょうか。いつも綿密なリサーチと精緻な文章で時代を切り取った作品を書かれているから、勝手に研究者的なところがあるんじゃないか、直感的なことはしないとイメージしている節がありました。
谷崎 たしかに調べるのは好きなのですが、途中で妄想に入っていってしまうので、あまり研究には向かない気がします……。お水送りについての考察も、本当に学術的な裏付けのない想像なので、研究者の方からすれば何を言っているんだと思われてしまうかもしれません。でもやっぱり、人が読経をし、舞い、見つめるうちに、神宮寺の真っ暗な内陣から突然大きな火が生まれてくるというのは、言われているもの以上の何かを表しているんじゃないか。つまり内陣を子宮と見立てて、出産の再演をしているように感じたんですね。そして、それは人間、というか男性が、女性の子宮からではなく自らの手で生命を作り出したいという欲望に紐づいている……と頭の中の回路がばーっとつながっていきました。
中村 すごくわかります。私はこの部分がすごく印象的で頷けるところで、というのもここから派生して世界中のイニシエーションのことが想起されたんです。
たとえば出羽三山の修験道。ここではかつて女人禁制の男性結社が山伏衣装を纏い、ある意味山を母体と見立てながら彷徨うことで死の世界を感じながら、生きて帰ってくる。とくに湯殿山は一切口外禁止なのでうまく言えませんが、男性性と女性性を象徴する山を巡る「生まれかわりの旅」とも呼ばれていて、まさしく妊娠・出産の再演だと思いました。
それから私、以前にアメリカインディアンのホピ族の儀式を見学したことがあるのですが、そこでは半地下にある祠みたいな薄暗い空間に七、八人の男性だけが入ってずっとたばこみたいな煙を吸うんです。たぶんあの煙には少し幻覚作用があって、あれは越境行為でありあの世とこの世の接続で、そのうちに彼らは突然スイッチングしてみんなで踊り出す。それがホピのカチーナという精霊の踊りなんですが、あれはたぶん地下に存在するあちら側の世界からこの世に生誕することを象徴している。つまりこの儀式もまた出生の模倣であるように感じ取れたんですよね。その他にも、長野の善光寺で真っ暗な地下をくぐって御本尊との「縁」を探して進むお戒壇巡りもまた、生まれ変わりのための胎内巡りだと言われていることとか、あれこれと連想が広がりまして。同様に、やっぱりお水送りにも男性的な組織や社会がもつ性質なり欲望が潜められていると思います。
谷崎 言ったらフロイトの逆ですかね。ファルスがあって羨ましいじゃなくて、子宮があって羨ましいみたいな。
中村 そうそう。初めて高校でフロイトの考えに触れて「女の人たちはファルスに羨望のまなざしを持っている」と読んだときの圧倒的違和感を思い出します。えっ、うそでしょと(笑)。私はそんな羨望をこれまでもこれからも感じる兆しがなかったから、それを精神医学の礎とするのはさすがにちょっと違うんじゃないかと目を疑いました。
谷崎 子宮への羨望を否認するために、そんな理論を考え出したのかなと勘ぐってしまうくらいです。それにしても修験道をやったことがないので無責任なことも言えないですが、身重の身体との付き合いとか新生児期の深夜の授乳とか、こっちのほうが過酷なのでは……とも感じます。歴史的に考えて女性はこれだけ出産で苦労しているんだから、すでに修験道をしているようなものかもしれません。
中村 まったくです。いずれにしても近代の男性優位社会は、太陽や女性が行っている生み出すという大きな営みを自分たちで再現したい、手のうちに収めたいという欲望を潜ませていた。そのことが原発とお水送りというモチーフにつながって表れていると思いました。
谷崎 そして、とくにお水送りについては、もっと清浄な方法で命を生み出したいという気持ちも表れているんじゃないかなと思ったり。古くから月経や出産やそれにともなう出血は、不浄のものとして忌避されてきたのですよね。月経小屋、産小屋という施設には、体調の優れない女性たちを家事労働から切り離し安静にさせる一面もあったそうですが、一方では穢れた体を隔離するという目的があった。そうやって女性の生理的な部分が穢れとして扱われてきたことには憤りも感じていたのですが、ただ私自身がチョウバエと戦っているなかで生殖と不浄さの関連について考えたこともありまして……。
中村 そうだ、チョウバエ! あの大量の♡ですね。♡が何かということについては、ぜひ本文で直接読んでほしいので詳細は語りませんが、あそこは表現として新しくて面白くて気持ち悪くて最高でした(笑)。
谷崎 それはうれしいのですけど、実態は本当に最悪でした。この箇所を書いていたときはリフォームのため仮住まいをしていたのですが、そこにこの虫が出まして。小さい子もいるわけだから衛生的にもなんとか殲滅したいと躍起になっていました。でもふと、チョウバエが殖えるということもまた命の誕生だよなと思い至ったんです。誕生は誕生なのに、どうしてこんなに不浄だと感じてしまうのだろう、もしかして、これはこの作品で考えるべきことそのものじゃないかと思い、元々は組み込むつもりなんかなかったのですが書き入れることにしました。今はもうリフォーム済みの自宅に戻ったので、虫が出ることもなくてひと安心です。
中村 大変でしたね、解放されてよかった。しかし、なんでしょう。もしかしたら私たちには生殖、あるいはそれがもっと膨大な数行われる増殖というイメージに対する恐怖があるのかな。そういえば、宮﨑駿監督の映画『君たちはどう生きるか』はまさに産小屋的な塔の内部での物語だったと思うのですが、そこでも増殖が、繰り返し鳥のモチーフを使って描かれていて、明らかに不気味なものとして映っているんですよね。そのあたりをあわせて考えると、私たちのなかにあるコントロールを超えて延々と殖え広がっていくものへの忌避感が窺える気がします。それが、増えていくチョウバエの故郷やかつての女性たちに向けられていた穢れの意識につながっているのかもしれません。
谷崎 なるほどです。確かに手に負えない感じ、得体の知れない感じはあります。