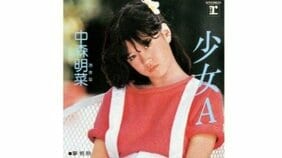教育施設に付きものの机とイスがほとんど見当たらない理由
施設を一見して気づくことがある。教育施設に付きものの机とイスがほとんど見当たらないのだ。座学を行う教室のような空間はパソコンが設置された4か所のワークショップルームくらいで、階段状のベンチシート、波打った床面のボックス席などが目立つ。
コーチ6名、ワークショップリーダー8名、運営スタッフ3名の計17名を率いるセンターマネージャーの清水義教(53)が言う。
「寝そべってパソコンを操作したり、隣り合って制作したデジタル作品の出来を論議したり。とにかく利用者には自由に学んでほしいという考えから、あえてこんなアスレチックジムのようなレイアウトになっています」
外国人初の米ハーバード大学寮長補佐に任命された経歴も持つ清水はこの春まで、東大大学院でハーバード大など、米大学システムについての講義を担当していた。
17歳で渡米し、米国の高校、大学を卒業。東大大学院、ハーバード大大学院で修士号を取得した国際教育政策、大学経営政策のプロである。
その清水が「TUMO Gunma」の存在を知ったのは今年春のこと。アルメニアにある「TUMO」本部を視察したドイツのメルケル首相(当時)ら世界各国の指導者がひと目惚れし、自国への「TUMO」誘致を即断したと聞き、「TUMO」のIT教育プログラムとはどんなものだろう?と、興味を持ったという。
その清水が言う。
「『TUMO』で使うデジタル教科書を見て驚きました。内容が破壊的に面白い。本当によくできているんです」
「TUMO」の教育プログラムは「セルフラーニング」と呼ばれるオンライン上の対話式自学習60%、そこで身につけたスキルを駆使し、グループでゲームやアプリなどを開発するワークショップ40%の比率で構成されている。
「ワークショップの面白さはいわずもがなですが、残り60%の自学習がとても魅力的なんです。内容はドローイングなら『丸形や台形を描く』、プログラミングなら『簡単なゲームを作ってみる』といったもの。
動画やイラストを見ながら、クイズ、ミニプロジェクトに挑戦して遊ぶみたいな感覚で、5~20分ほどもあれば文系脳の人でもIT苦手の人でもこなせてしまう。
エリート教育でもなければ、手とり足とりの押し付け教育でもない。まさに自力で楽しみながら学べる。そこで知識を得るというより、『学び方を学ぶ』という感じ。このカリキュラムなら自分が長年考えていた教育イノベーションを起こせると確信しました」