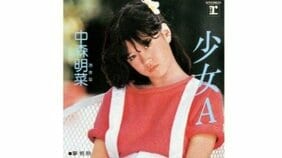――宮田さんのキャラクターの作り方と、『虚池〜』でのキャラクターの作り方は違ったアプローチかもしれませんね。
森 そうですね。それこそ先に句を考えたりもしてないですし、肝心のメインの謎になる句は、物語が固まるまでXって置いているぐらいでしたから。こういう推理でこういう展開になるから、じゃあこの言葉は入れなきゃいけない、この言葉も入れなきゃいけないと。そういった作品の要請に応える形でX(自由律俳句)が形成されていきました。ただ、それ以外のところで虚池が言っていることなどは、なるべく感性に任せて自由律俳句っぽくというのを心がけつつやりました。
宮田 逆にそのほうが大変そうですよね。これ入れなきゃいけない、これ入れなきゃいけない、でも自由律俳句にしなきゃいけないという。
森 そうですね。そこは少し大変だったなとは思いますけど、でも、ただロジカルなだけの日常の謎だったらいろんな人がやっているので、そこを成立させないと自分がやった意味がなくなってしまうので、そこはマストだなと思って、やらざるを得なかったです。
宮田 どれぐらい時間かかりました? 一句つくるのに。
森 連載でやっていたので、各話大体二十日ぐらいで執筆していました。だから一句完成するまでの時間も同じですね。二週間ぐらいで仕上げて、もう一回見直すときに最後まで迷いながら言葉を入れ替えたり、やはりこの形にしようとか、少しずつ微調整してという感じでした。
宮田 書きながらつくっていた感じだったんですね。
森 はい。僕はミステリ作家でやってきましたけど、ロジカル重視ではなくて、どちらかというとペダンティックさで煙に巻くみたいなスタイルだったんです。ペダンティックなことを言っていたらついでに事件が解けちゃったみたいな、そういう少し目くらまし的なことをやっていたんですけど、今回に関しては、むしろ今までで一番ロジカルにやろうみたいな気持ちでやりました。ハリイ・ケメルマンの「九マイルは遠すぎる」という謎の一言から全部推理していくというスタイルなんですけど、それで全部通すというのが今回のスタイルです。
――かなりのハードスタイルでした。
森 はい(笑)。しかしこういった挑戦をしないと、自分のキャリアにプラスにならない。
宮田 大衆的なミステリーでありつつ、充実したミステリであるというのは存分に味わえました。
――俳句、そして短歌、〈黒猫シリーズ〉では詩を引くなど、その取扱いの難しさをうかがいましたが、小説家としてこの作業はどうでしたか?
森 確実にフィードバックはあると思います。短歌や俳句を小説に取り込むことの、小説というものへのフィードバック。豊かになりますよね。それが別にそういう俳句や短歌が入っているからというわけじゃなくて、それによって何か散文が影響を受けるというんですかね、そういう波及効果みたいなのがあるような。
僕はデビューしたときから、探偵小説をメインでやっているので、探偵小説は詩と構造が交換できるぐらい、価値を交換するものだということを言っていたんです。要は、エドガー・アラン・ポーが詩を書き、探偵小説も書くみたいな。実はポーは詩を書くのと同じ感覚で探偵小説を書いていたんじゃないか、みたいな仮定から、自分で書いて答えを出そうと思ったのが『黒猫の遊歩〜』でした。なので、結局今回もその延長の試みだろうというふうには思っています。
宮田さんの『春、出逢い』を読んでいて、これもミステリじゃないけど、でも少し近いところはあるなという感じが。
宮田 そうですね。私は万葉集をメインに勉強してきていて、今も読むんですが。解釈をするときって、何でこの言葉を使ったんだろう、この言葉を使うということは、こういう状況だったのではないか?といった解釈を、私自身で繙いて、みんなに差し出さなくてはいけないというのがあります。そうなるとやっていることって結構探偵と変わらないような気がしていて。ここにこういう証拠があるから、これがこうなるんですって、明らかな証拠を提示して、そこをつなげていくのが私の役割というのを大学の授業で勉強していて。そこは確かに言われてみれば近いのかもって、今思いました。
森 そういう描写が幾つか出てきて、これは小説自体の強度と結びついているなと思って。
宮田 読むという行為自体、読み解いて解釈していく、言葉をつなげていくというのは、そもそもとても探偵っぽいのかもしれませんね。
――宮田さん、次にこういったジャンルに挑戦してみたいなというのはありますか?
宮田 私、結構いろんな場所でミステリ書いてみたらって勧められるというか。私、ミステリは絶対無理だと思っているんですけど。
森 いや、書けると思いますよ。名探偵宮田愛萌みたいな、そういうのを見てみたいですね。
宮田 この作品読んで、言葉から読み解いていくというやり方が、そういえばあったと。私もやっていた、謎解きって、今日の対談でも思って。少しね、無理かな。でも……。
――森さんはここ数年で、幅広くいろいろ書かれています。さらに次、チャレンジしたいことはありますか。
森 そうですね、『あの日、タワマンで君と』のやり方で一つ分かったのは、ミステリってそんな狭いものじゃないんだなという、何でもできるんだなというのが分かったので、逆に自分がやりたい物語、何でも全部ぶち込んでも成立させられるなと感じています。昔は着陸できるかなみたいな不安要素を抱えながら、着陸できなかったときの悲惨さを考えて冒険ができなかったから、しっかり「これはミステリです」と分かりやすいものしか書かないようにしたほうがいいのかなとか思っている時期もありました。今はもうどんな形で出発しても着陸できるようになってきたので、恋愛小説でもいいし、見た目はどんなふうに見えても、最終的に僕はミステリ作家としてどうせ見られるので、ミステリとして着陸しますという、そこだけ外さないようにして。
宮田 いつから着陸できるなと思うようになったんですか。
森 三、四年前ですかね(笑)。
宮田 遠いなあ。頑張ろう(笑)。頑張ります!
「小説すばる」2025年10月号転載